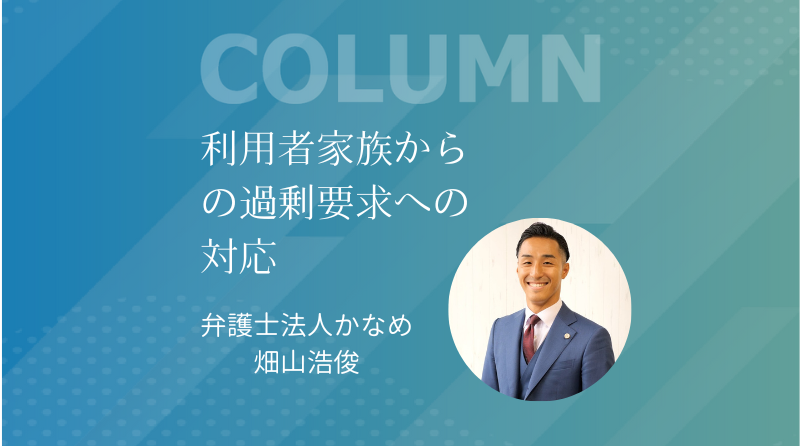こちらの連載では、介護現場におけるカスタマーハラスメントの事例や対応についてこれまでも取り上げてきました。今回はグループホームで起きた事例を交えて考えてみましょう。
転倒事故によって障害を負ってしまった利用者の息子が、賠償対応完了後も様々な要求を続けているため施設長を悩ませているようです。
1.グループホームで生じたトラブル事例―賠償対応完了後も利用者の息子が特別対応を要求
<相談内容>
私はグループホームの施設長です。
去年、利用者(女性)がグループホーム内で転倒し、大腿骨頸部骨折という怪我を負ってしまいました。
この事故の原因を調査すると、うちのスタッフの不注意で生じた事故でした。
保険会社とも協議したところ、最終的に賠償額300万円をお支払する形で賠償対応は完了しました。
しかし、この利用者のキーパーソンである息子が賠償対応完了後も様々な要求をしてきており大変困っています。
一番困っている要求は、「入浴介護を一般浴で継続してくれ」というものです。
というのも、この利用者は元々お風呂が好きだったのですが、事故後、車椅子生活になってしまいました。その関係で計画作成担当者が一般浴は危険だと判断し、シャワー浴に変更すると判断したのです。
これに対し、息子が激怒し、「グループホームが引き起こした転倒事故のせいで母親は車椅子生活になってしまったんだ!シャワー浴に変更だなんて納得できる訳がない。何人がかりになっても良いから母親には一般浴を継続しろ」と要求しているのです。
息子の主張にも一理あるような気がしておりますが、一般浴を継続することは利用者本人にとって危険を伴うことですし、うちのスタッフの業務も圧迫されてしまいます。
どのように対応すれば良いのでしょうか。
2.賠償対応とその後のケアの在り方―ポイントは線引きの明確化
今回の相談のような事例は、現場の方々も非常に対応に苦慮されることでしょう。
転倒事故の原因が介護事業所側にある訳ですから、息子の要求はもっともなように感じますね。
ですが、仮にこの息子の要求を受け入れてしまうと、今後、入浴介護の度にスタッフが複数名で車椅子の利用者を抱きかかえて一般浴で入浴させるという過度な負担が発生し、現場は疲弊してしまいます。
また、息子の過剰な要求をひとたび受け入れてしまうと、要求はその先もどんどん肥大化することでしょう。
「車椅子になったことで今までできていた●●もできなくなってしまった。スタッフ総動員で担当してくれ」というように、入浴介護と同じ構図で●●の部分が際限なく増えていくのです。そして、これを断わると、「何故断るのだ?入浴介護はこちらの要求を受け入れて実施しているじゃないか。それと同じ理屈だ。必ず実施してくれ」というように、ひとたび要求を受け入れたことを根拠として、要求を強く通そうとしてくる訳ですね。容易に想像できる情景です。
重要なポイントは、賠償対応とその後のケアの在り方はしっかり線引きして考える必要があるということです。
あくまで賠償対応は金銭賠償です。保険会社と協議の上、保険金の支払いを済ませたのであれば、事故に対する法的責任は果たしたことになります。法的には、それ以上の要求に応じる義務は無いのです。
その後の利用者の状態に応じたケアの在り方については、介護事業所側がプロの視点から考えて実践していくべきです。
怪我をする前の利用者の状態と怪我を負った後の利用者の状態が異なるのであれば、今の状態に応じてケアの在り方を考える必要があります。
いくら事故原因が介護事業所側にあったとしても、怪我を負う前のケアの在り方が、現時点での利用者にマッチしていないのであれば継続すべきではありません。
利用者に対する安全配慮義務を負う介護事業所としては、無理な介護を引き受けてケアをすることで、利用者をより危険な目に遭わせる可能性が高くなってしまいます。
また、過剰なサービスに対応するためには人手も多く必要になります。その分、他の利用者へのケアが手薄になってしまいます。介護サービスは介護保険制度のもと、利用者の要介護度に応じて受けられるサービスの内容が決まります。一部の利用者に対して、過剰サービスを実施することで、他の利用者へのケアが手薄になることは介護保険の制度上でも想定されていない事態と言って良いでしょう。
今回の相談事例についても、計画作成担当者が今後はシャワー浴が妥当であると判断したのであればそれを息子に伝え、一般浴でのケアの継続はできないことをはっきりと説明しましょう。
3.施設での対応:ケアチームとクレーム対応チームとを切り分ける
相談事例のような過剰要求があった場合、事故に直接関わったスタッフに対応を任せてはいけません。施設長や計画作成担当者が家族への説明を行うべきです。
要するに、ケアチームとクレーム対応チームを分けるということです。
事故に直接関わったスタッフは、ただでさえ「自分が悪い」と自責の念にかられています。この状態で激怒している息子に接してしまうと、「言い分はごもっともだ。無理してでも引き受けよう」という心理状態になってしまうことでしょう。実際にこのような家族にケアチームが対応した結果、過剰要求を無理に引き受けてしまうという事例は枚挙に暇がありません。
しかし、施設長や計画作成担当者なら、現場で事故に関わったスタッフとは違う視点で家族対応を実施することが可能です。むしろ、このような過剰要求に対して、冷静に対応することが職責であると言っても過言ではありません。
もちろん、「事故原因が介護事業所側にある」という点に対する謝罪の意思表明や共感を示すことは必要ですが、同時に、できることとできないことの線引きをはっきりと伝えることも可能です。いくら家族側が激怒しても、できないことを安請け合いしてはいけません。過剰な要求を引き受けてしまうと、その後、要求は雪だるま式に増えていき、何年も特別な待遇を実施することになります。私は、実際にそのような施設を数多く見てきました。だからこそ、最初が肝心です。
4.過剰要求が収まらない場合の対処法
筆者の経験上、事例のような過剰要求があっても、施設長や計画作成担当者が謝意は示しつつも、できることとできないことの線引きをはっきりと説明するという適切な対応を行うと「こんな施設は辞めてやる」とご家族側が退所を申し出ることが多いように感じます。
しかし、仮に、利用者の家族が過剰要求を辞めない場合は、押し問答が続く状態になります。介護事業所側としては、何度も何度も話し合いを行い、家族側の納得が得られるように説明を尽くす必要があります。
もっとも、このようなプロセスを経てもなお過剰要求が収まらない場合は、もはや介護サービスを継続していく上で必要不可欠な「信頼関係」が破壊されています。つまり、介護利用契約を継続していくことは難しい局面になっています。
そのような場合は最終手段として契約解除という方法を検討する必要があります。契約解除という文言を持ち出すことで、家族側はより一層激怒することが予想されますが、信頼関係の無い状況でサービス継続など不可能です。
過剰要求への対応や契約解除の対応は、法的に専門知識を伴う部分ですから、弁護士に相談しながら対応することが大切です。
今回は過剰要求への対応について具体例を踏まえて検討しました。
このようなハードクレームの問題は介護現場を悩ませ続けている問題の一つです。介護経営ドットコムでは、過去にもハードクレームやカスタマーハラスメントへの対処法について記事を公開していますので、こちらも合わせてご覧下さい。
【介護現場におけるハードクレーム・カスタマーハラスメントに関する過去記事】
・カスタマーハラスメント:総論編―介護現場におけるカスハラの実態と対応を怠った場合の問題点
・カスタマーハラスメント:各論編―事故対応の心得とお金を要求された場合の対応
・カスタマーハラスメント:組織づくり編
・カスタマーハラスメント対応指針の策定と実装