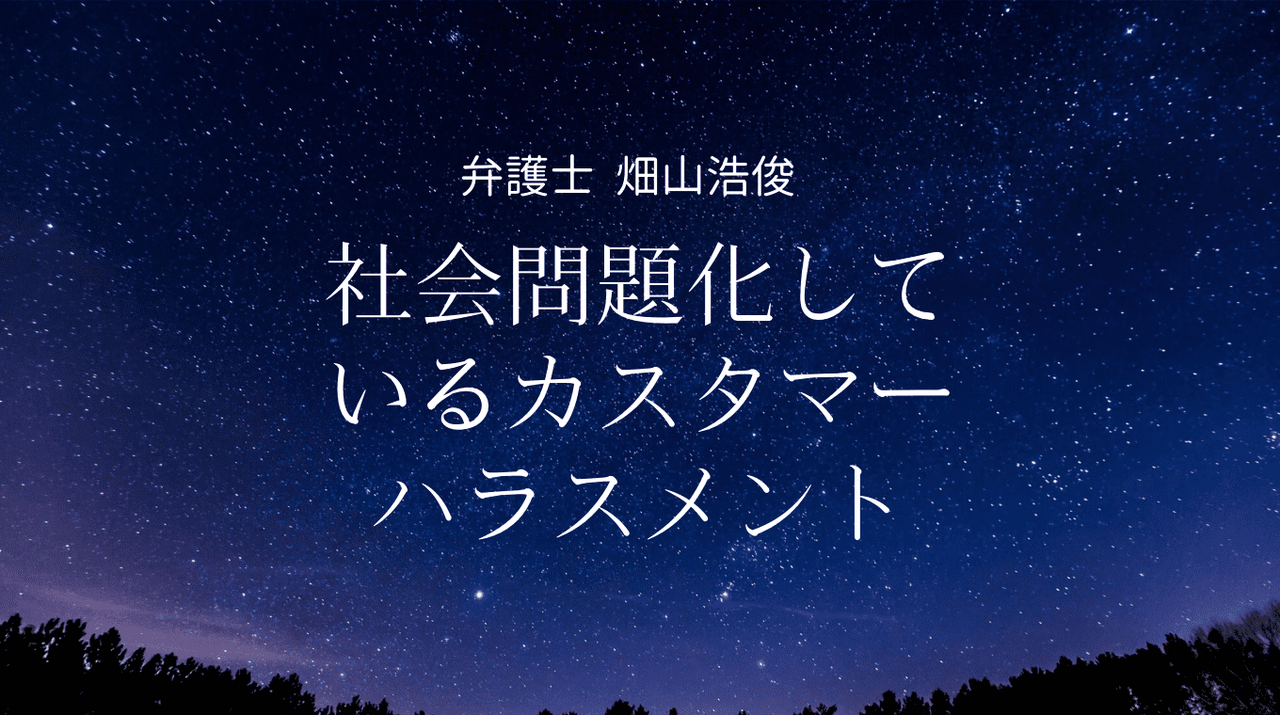最近、顧客が従業員に対し、恫喝や理不尽な要求、過剰な要求を突き付ける「カスタマーハラスメント」(以下、「カスハラ」といいます。)が社会問題となっています。
介護現場でも、利用者だけではなく、利用者のご家族やその関係者が従業員に過度な要求、理不尽な要求を突き付ける不当要求が問題になっており、我々弁護士法人かなめには頻繁にカスハラに関する相談が寄せられています。
そこで、今回から3回に渡って介護現場におけるカスハラをテーマに論じていきましょう。
まずは、カスハラの実態と、法人が対応を怠った場合の問題点について解説します。
1.介護現場におけるカスハラの実態
当法人に寄せられるカスハラに関する法律相談の一例を紹介します。
- ヘルパーが利用者宅を訪問したところ利用者の家族からセクハラの被害に遭った
- グループホームの利用者の家族が、2週間に1回、必ずミーティングを開くよう要求し、細部にわたるまで指導、口出しする状態が3年続いている
- 事故発生直後、事業所に利用者の家族が乗り込んできて「担当者だけでなく、ここにいる職員全員呼び出して謝罪会見を開け!」と大声で騒ぎ立てる
- 事故報告書を閲覧し、意に反する書き直しを命じ、書き直しをしないと行政に苦情申入れを行うという圧力をかけてくる
- 他のスタッフの見ている前で「お前のような無能な人間は担当を外れろ」などと人格権を侵害する発言を繰り返す
- 「必ずこちらの指定する時間に折り返し電話しろ!夜10時しか電話に出ることができない」などと時間を指定した対応の要求を繰り返す・・・等々
弁護士法人かなめでは、介護業界の経営者、管理者、施設長がチャットで相談できる体制を設けているので、上記のように現場が困ったタイミングですぐに相談が来ます。私の肌感覚では、近年このような相談事例は増加傾向にあります。
実態調査としては、2017年にUAゼンセン流通部門が実施したアンケート結果 及び2019年に厚労省補助金(老人保健健康増進等事業)の助成を受けて株式会社三菱総合研究所が実施した「介護現場におけるハラスメントに関する調査研究」 等があります。
2.法人がカスハラ対応を怠った場合に生じる問題点
(1)問題点①:法人が職員に対して賠償責任を負う
仮に、介護事業を運営する法人が、職員から上記のようなカスハラ被害の訴えを受けた場合、法人がその訴えを放置したり、中途半端な対応に終始し、現場に任せきりにしたならば、どのような責任が発生するのでしょうか。例えば、訪問系サービスでは職員がセクハラ被害に遭う事例が目立ちます。利用者や家族からセクハラ被害を受けた職員が、運営会社に相談したときに、「ヘルパーがセクハラを受けるのはこの業界だと当たり前。そんなこと一々言ってたらこの仕事は務まらないよ」と言われ、一切対応してもらえなかった場合、運営会社はどのような責任を負うのでしょうか。
一つ裁判例を紹介したいと思います。
学校法人M学園の講師が、授業中に生徒から臀部を触られるというセクハラ被害に遭い、この講師が学校法人に被害を訴えました。学校法人は、調査の結果、セクハラの事実があったかもしれないと認識したにも関わらず、それ以上対応せず、セクハラは無かったという結論を下しました。この杜撰な対応について、講師が学校法人を訴えたという事件です(もちろん加害者の学生も訴えています)。(【学校法人M学園ほか(大学講師)事件】:千葉地裁松戸支部平成26(ワ)第1013号。)
これは筆者の推測ですが、学校法人側は、「セクハラがあったかもしれないけど、そんなことで一々騒ぐなよ。学生を辞めさせる訳にはいかないし。ある程度対応した形式だけ整えておいて、無かったことにしよう。」という考えの元、杜撰な対応をしたものと思われます。
この裁判では、学校法人が敗訴しました。敗訴した理由は、学校法人と講師との間で締結している雇用契約に基づいて、学校法人が講師に対する安全配慮義務・職場環境配慮義務を負っているにも関わらず、その義務をきちんと履行しなかった、というものです。
法人は、雇用契約に伴い、職員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をする義務を負っているのです(労働契約法第5条)。この安全配慮義務・職場環境配慮義務に基づいて、カスハラに対応することも法人に求められる法的な義務だと理解して下さい。
(2)問題点②:対策を講じないと優秀な職員が辞めていく
このように、カスハラの事実に対して対応しない場合、法人に賠償責任が生じる可能性があることも問題ですが、もっとシンプルかつ深刻な問題は、法人がカスハラ問題に真正面から取り組まないと、やる気のある優秀な職員から辞めていってしまうということです。
冒頭に、グループホームの利用者の家族が、2週間に1回、必ずミーティングを開くよう要求し、細部にわたるまで指導、口出しする状態が3年続いているという例を紹介しました。
この問題に取り組み続けていた管理者から言われたことがとても印象に残っています。
その管理者は、私に「先生、法人がきちんと向き合ってこなかったから、この施設では若くてやる気のある職員がどんどん辞めていきました。どうせ法人は何もしてくれない、対処してくれない、という虚無感が職場に流れており、これを何とか断ち切りたいと思っています。」と悩みを打ち明けてくれました。このような「やる気のある職員が辞めていく」という声は、カスハラ事例を放置してきた法人から非常に多く聞く悩みなのです。
しかし、法人側が全て悪い、という話でもありません。
実は、法人は「このような問題を誰に相談して良いかわからない」という悩みを有していることが多いのです。
これは私の個人的見解ですが、カスハラ対応が満足にできないという法人の抱える問題の根っこには、法的対応が必須であるカスハラ対応において本来力を発揮すべき弁護士と、法人の現場を束ねるマネジメント層との間でスムーズなやり取りができていないという、コミュニケーション不足もしくは、弁護士への常時接続可能な相談窓口が無いという体制の不備があるのではないかと感じました。
本稿では、カスハラという社会問題に十分に対応し、現場で働く職員を守る体制を構築する重要性や、弁護士と介護事業所が常時接続できる環境づくりが必要という、筆者の問題意識を理解して頂けたかと思います。
次回以降では、具体的に、介護事故の事例を元にカスハラ対応を実践的に掘り下げていきたいと思います。