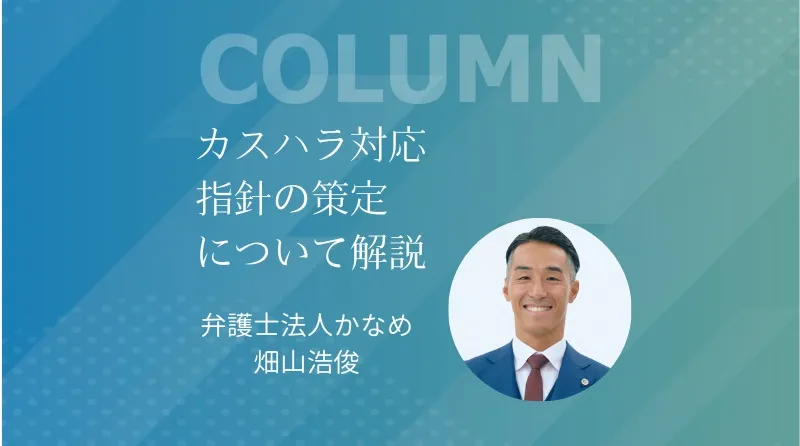1.介護現場のカスタマーハラスメントへの高い関心
筆者は以前、「社会問題化しているカスタマーハラスメント」という題で3回に分けて介護経営ドットコムに記事を寄稿しました。これらは、1年以上前の記事にもかかわらず、未だに多くの方々からの反響を呼んでおります。
以下、カスタマーハラスメントのことを「カスハラ」と略します。
(※編集注:掲載開始当時(2022年10月31日)に掲載していた特典資料の申し込みは受付終了しました)
2.「カスハラ対応指針」を作成・公表することで得られる2つの効果
カスハラとは、利用者・家族等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、サービスの範囲を超えた要求、不当な要求等の著しい迷惑行為のことです。
筆者は、カスハラ対応指針を作成することで、大きく分けて2つの効果が得られると考えています。
まず、介護事業所で働く職員を守る効果です。
法的に言うと、カスハラ対応指針を作成することは、法人が職員に対して雇用契約上負っている職場環境配慮義務(労働契約法第5条)の履行に繋がります。
例えば、ヘルパーが利用者宅から帰ってきた際、「利用者の夫からセクハラの被害を受けました。」と訴えがあったとしましょう。まさにカスハラ対応の場面ですが、相談を受けた管理者や経営者が「利用者宅でセクハラの被害に遭うことなんて当たり前。そんなことを気にしていたら仕事にならない。」と真剣に受け止めず問題を放置することがあります。これでは、働く職員の職場環境に配慮しているとは言えません。結果としてこのセクハラが原因で職員が精神疾患になったり、それが理由で退職せざるを得なくなったりした場合、法人はこの職員に対して職場環境配慮義務に違反したとして賠償責任を負うこともあります。
「介護現場ではカスハラは当たり前」という風潮は、未だなお介護現場で当然視されている側面がありますが、この空気が蔓延している職場では職員は定着しません。カスハラ対応指針を作成することは、法人そのもののカスハラに対する意識を変えることに繋がります。結果として、対応方針を作成することは職員を守ることに繋がります。
次に、カスハラ対応方針を公表することで利用者やその家族等からの被害を事前に抑止する効果があります。
弁護士としてカスハラ問題に対応していると、一部の利用者や家族の中には、「介護事業者には何を言っても許される」と勘違いしている人がいるように感じます。「自分たちが介護保険を払ってその報酬で介護事業所の職員は給料をもらっているのだから、利用者のいうことを聞くのは当然だ」と発言し、職員をまるで奴隷のように扱うケースが後を絶ちません。「ダメなものはダメ」とはっきりと公表することで、利用者や家族等にカスハラには毅然と対応する姿勢を示しましょう。筆者がサポートしている介護事業所の中には、利用者との契約締結時に契約書や重要事項説明書とは別に、カスハラ対応方針を記載したリーフレットを交付しているところもあります。このリーフレットを受け取った利用者や家族から「今の時代はこういうことも大切だね。」という声を頂くこともあり、理解が得られることも多いです。
今まで明確に「カスハラはダメ」を伝えてこなかったことがカスハラ問題を増長させる一要因になっていたことも事実です。恐れずにカスハラ対応指針を公表することが大切です。
3.「カスハラ対応指針」の作成方法
(1)法人が大切にしている「想い」をまず書こう
カスハラ対応指針の作成方法は、本来、各法人の自由です。
もっとも、筆者としては、「何故カスハラ対応指針を作成したのか」という法人の想いをしっかりと記載することが大切だと考えています。
冒頭から「カスハラは絶対に許しません」という文言ばかりを記載する指針は、筆者はあまり望ましいと思いません。
禁止行為が羅列された指針を読んだ利用者や家族、これから利用を開始したいと考えている人たちはどのように感じるでしょうか。まるで、自分たちがカスハラを行うことを決めつけているような文章に感じてしまうのではないでしょうか。
大切なことは「共感を得ること」です。何故、カスハラ対応指針が必要なのか、この指針を通じて法人として何を実現しようと考えているのかを丁寧に記載し、読み手の共感を得るようにしましょう。
(2)カスハラとは何かを記載しよう
法人が大切にしている想いを記載した後は、いよいよ禁止すべき事項の記載です。
先にも述べましたが、カスハラとは、利用者・家族等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、サービスの範囲を超えた要求、不当な要求等の著しい迷惑行為のことです。
すべてを網羅的に記載することは困難ですから、典型的な迷惑行為を記載した後にそれらに類する迷惑行為全般も対応対象となることを記載する形式が望ましいです。
(3)カスハラがあった場合の対応方針を記載しよう
カスハラがあった場合にどのように対応するのかをきちんと記載しておくことは、その介護事業所で働く職員の安心感に繋がるとともに、カスハラを未然に防ぐ抑止策になります。
まずは、法人内部にカスハラ相談窓口があることの明記することが大切です。
これを明記することで、カスハラの被害を受けた職員が誰に相談すれば良いのかを明確にすることが可能になります。
次に、その相談窓口と外部機関が連携することも明記して下さい。外部機関とは、顧問弁護士や警察等です。時には行政担当者と連携する場面もありますので、「等」と表記しています。
特に、顧問弁護士の存在は重要です。その理由ですが、上記のように法人内部に相談窓口を設けたとしても、その相談窓口を担当する人の多くは、管理者や施設長であり、法的な素養が十分にある訳ではありません。カスハラに該当するか否かの判断、該当した場合にどのように対応していくか等、カスハラ対応には法的素養が必要不可欠なのです。したがって、法人内部の相談窓口を設けただけでは、結果としてカスハラ問題に適切に対処できず、余計に現場職員や相談窓口を担当する職員の精神的負担が増大することになり問題解決には繋がりません。
きちんと適宜相談できる顧問弁護士をカスハラ対応の仕組みにビルトインすることが大切です。
4.対応指針策定後の注意点
最後に注意点です。
カスハラ対応指針を作成した後、それをHPに公表したり、契約書や重要事項説明書とは別にリーフレットとして作成して契約時に交付したりして運用する場合、決して組織で実際に対応できない内容を指針に記載しないで下さい。
一つ具体例を挙げると、顧問弁護士がいないにもかかわらず、カスハラ対応指針に「顧問弁護士と連携する」と記載してはならないということです。この指針は利用者や家族だけではなく、勤務する職員も目にします。職員は「顧問弁護士が背後にいるのだったら安心だ」と思うはずですが、いざという時に、実際には顧問弁護士などいなかったということが発覚すると勤務先との信頼は完全に損なわれます。
また、指針では存在すると謳っているにもかかわらず実際にはいなかったとなると、カスハラ対応が不十分であったことが原因で精神疾患に罹患したなどと、職員から職場環境配慮義務(労働契約法第5条)違反を理由に損害賠償請求がなされることもあるので注意が必要です。