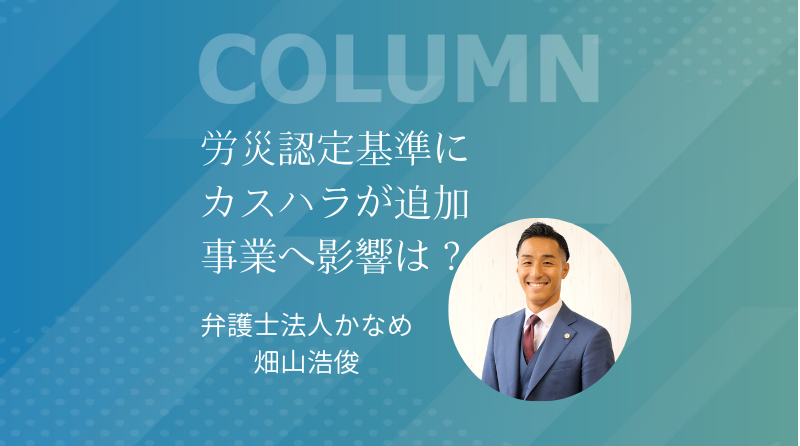6月20日、厚生労働省は、仕事が原因でうつ病等の精神障害を発症した場合の労働災害の認定基準について、カスタマーハラスメントも心理的な負荷が大きいとして、考慮すべき類型に追加することを決めました。
*参考リンク:時事通信社2023年6月20日配信記事
カスハラに関するトラブルが多発する近年、特に介護現場では利用者やそのご家族から受ける被害が社会問題となっています。
現時点では改正時期など詳細は明らかとなっていませんが、厚労省が今回実施する労働災害認定基準改正が介護現場にどのような影響を与えるのかを考察します。
1.うつ病等の精神障害の労災認定とは?
考察にあたって、介護職員が利用者の介助行為の際にぎっくり腰になった場面について考えてみましょう。
その介護職員は当然、治療のために病院を受診しなければなりませんし、少なくとも数日間は仕事を休まざるを得なくなります。この場合、この職員が全く何の補償も受けられないとすると、生活に支障を来しかねません。
そこで、雇用主が労災保険に加入している場合、このような業務上の負傷については労災保険による給付が行われます。具体的には、治療費や休業補償に関して一定の金額の補償を受けることができます。
介助中に起きたぎっくり腰であれば、業務災害であることは明らかなので、労災認定は容易です。
しかしながら、うつ病等の精神障害の場合はその原因が業務によるストレスなのか、業務以外のストレスが原因なのか、はたまたその職員の既往歴・アルコール依存状況・生活状況等(個体側要因)が原因なのか、一目瞭然とはいきません。
そこで、うつ病等の精神障害について業務災害に該当するかどうかを判断するため、厚労省は『精神障害の労災認定』というパンフレット、以下「当該パンフレット」といいます)を公表しており、労働基準監督署では、当該パンフレットを元にうつ病等の精神障害に関する労災保険請求に関して労災に該当するか否かを判断しています。
ここで示されている精神障害の労災認定要件は、次の3つです。
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
今回の労災認定基準の改正は②に関する改正ですので、ここでは、特に②の要件について解説します。
例えば、介護職員が職場でミスをしたことが原因で、上司から職場内で公然と1時間以上も大声で「この給料泥棒が!」「お前みたいな無能はさっさと職場から消えろ!」等と人格や人間性を否定するような言葉で罵倒され続けたとします。
しかも、それがたった一日ではなく、数日にわたって複数回ありました。かなり執拗で悪質な叱責ですね。
このような具体的なエピソードは、当該パンフレットのp.9の項目29のパワーハラスメントの類型のうち、心理的負荷が「強」と判断されるエピソードとして位置付けられます。
このように、実際に生じた具体的な事実関係を当該パンフレットの表に当てはめ、その事象の心理的負荷の「弱」「中」「強」を評価し、出来事が複数ある場合は、総合評価して「業務による強い心理的負荷が認められるか否か」(上記②の要件)を判断することになります。
2.カスタマーハラスメントが追加されることによる実務への影響
上記のようなパワーハラスメントの事例については、当該パンフレットの「具体的出来事」の一覧表に類型が掲載されています。
しかし、顧客との関係については、「顧客や取引先からクレームを受けた」(当該パンフレットp.7の項目12)という類型は存在しているものの、カスタマーハラスメントそのものを対象とした規定はありません。
今後、具体的な類型が追加されることにより、カスハラに関する具体的な事実関係によってどの程度心理的負荷を受けたのかがより直接的に判断し易くなります。
その結果、カスハラに起因する精神障害について労災認定される件数は増加すると言えるでしょう。
3.介護事業所が備えておくべきことは?
カスタマーハラスメントが新たに労災認定基準に追加されることを受けて、「雇用主の負担がより一層重くなる」といった経営者層の反応も見られます。もっとも、筆者はカスハラが新たに労災認定基準に追加されようがされまいが、雇用主がやるべきことは変わらないと考えています。
筆者が介護現場で働く職員からヒアリング調査を実施したところ、カスハラに関して意外な声が数多く聞かれました。
それは、「カスハラの存在そのものはやむをないと思っている」というものです。
理由としては、人それぞれに価値観が異なることに加え、加害者を取り巻く状況(介護疲れ、経済的状況、健康状態、社会活動の中における疲弊等々)も千差万別であり、カスハラが発生する原因を論理的に特定することは不可能である以上、撲滅に至ることは難しいということが挙げられます。
これを踏まえ、カスハラに対応する上でどのような場面が最も精神的に苦しいかを調査したところ、最も多かったのは、「自分が被害に苦しんでいることを職場に相談しても、まともに取り合ってもらえなかったこと」という声でした。
「そういったことはよくあることだから、我慢するしか無いよ」、「介護現場なんだから仕方がない。いくら家族が罵倒するからといって、利用者本人を施設から追い出す訳にはいかないから堪えて下さい」、「あなただけがしんどい訳じゃないのだから、弱音を吐かないで下さい」等々、相談した際に上司が真正面からこの問題に向き合ってくれず、我慢を強いられたことが「最も精神的に苦しかった」と多くの介護職員が訴えています。
筆者は、かねてからカスハラの問題は個人で対処する問題ではなく、組織として対処すべき問題であると述べています。
正確な統計データがある訳ではありませんが、数多くの法律相談対応をしてきた中で感じるのは、この問題に組織として対応する姿勢を持っている介護事業所では、被害を受けている職員が精神的にも支えられている実感を持つことができ、精神障害を発症しにくい傾向にあることです。
これに対して、カスハラが起きても上司や法人本部等が職員個人にその対応を任せっぱなしにしている介護事業所では、対応にあたる職員が精神障害を発症する傾向が高いです。
心理的安全性の高い職場か否かが精神障害の発症リスクの高低に影響を与えることは自明です。
国の動きを受け、この問題に対して率先して組織的に取り組む姿勢を打ち出し、カスタマーハラスメントに向き合う組織作りに注力する介護事業所が少しでも増えることを筆者としては願っています。そうなれば、職員の心理的安全性が高まり、精神障害が発症しづらい職場環境が形成されることに繋がることは間違いないでしょう。
なお、介護経営ドットコムにおいて、筆者は過去複数回に分けて、組織としてカスタマーハラスメントにどう立ち向かうべきか、論考を重ねております。
ここにバックナンバーをまとめて掲載しますので、是非組織作りにお役立て下さい。