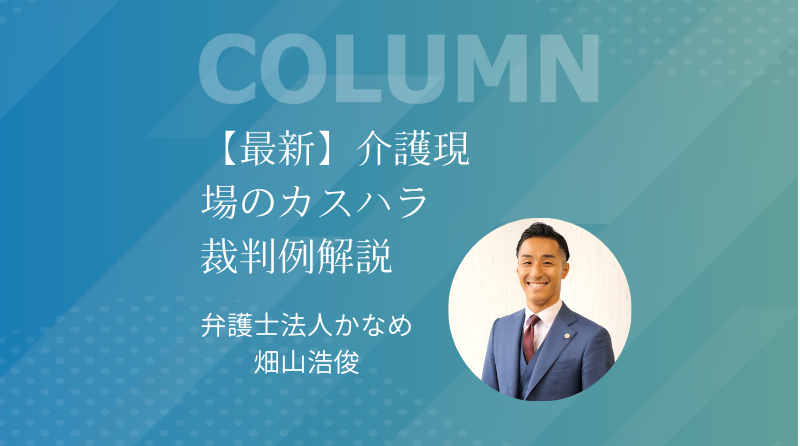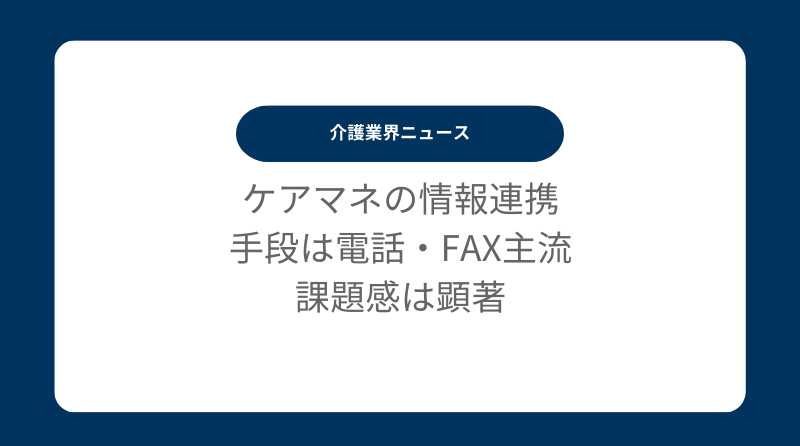1.老人ホームにおけるカスタマ―ハラスメント裁判例の紹介
今回は、老人ホームで発生した利用者の家族が加害者となったカスタマーハラスメント裁判例(東京地判R3.7.8(平31(ワ)1474号))について解説します。
この事案では、大きくは
1.カスハラ加害者(被告)の母と結んでいる老人ホームの利用契約解除が有効であるかどうか
2.利用契約解除後に施設利用料を2倍とする合意が有効であるかどうか
の2つが争点となりました。
①については、カスハラの事実があるかどうかが重要なポイントになります。
②について、入居系サービスの場合は、仮にカスタマーハラスメントを理由に入居契約を解除したとしても、実際に利用者が部屋を明け渡してくれなければ問題は解決しません。そこで、契約解除後に少しでもスムーズに居室を明け渡してもらうために、契約解除後の施設利用料を通常よりも高額に設定する場合があります。この裁判例では、契約解除後の施設利用料を2倍とする合意がされており、この有効性が争われました。
いずれも、近年深刻化している介護現場でのカスタマーハラスメント対応に関して、非常に参考となる判断がされています。
以下、順に見ていきましょう。
なお、「原告」は老人ホームの運営会社です。「被告」は利用者の子であり、カスハラの加害者です。
2.争点①被告の母との間の老人ホーム利用契約解除の有効性
ア 被告の言動
本件では、利用者である被告の母は認知症であり、意思能力がない状態であって、有料老人ホームの利用状況には、特段の問題はありませんでした。
しかしながら、被告は、原告の職員に対して、以下のような言動を繰り返していました。
・原告の看護職員に、「馬鹿野郎」 「お前なんかやめちまえ」 「○○なのに、何の提案もできないナースは辞めろ、いる意味がない」「あんなのクビだろ」「俺が指示しなきゃなんの提案もできない施設か」「医師の指示、医師の指示って、何もしねえ○○かよ」「夜間ほぼほぼ何もやってねえよ」「何が忙しいだよ、ほんと酷い施設だな」などといった暴言、及び 「刑事裁判を起こす」 「裁判の勝ち負けが問題ではなく、訴えを起こすことが大切」 「看護職員から免許を奪う方法はあるのか」 「ここを出ていく時はスタッフを個人名で訴える」といった脅迫。
・ホーム長を「エンドウ豆、チビ」 その他の職員を「デブ」や「ハゲ」などと、人格否定や侮辱等の意味合いを持つ呼び方をしていた。
・被告の母の経管栄養の滴下速度を被告の考えで変更することや、原告の職員に対し、立位を伴う排せつ介助を強要すること、主治医による臨時往診、定期往診をキャンセルすることなどを止めるように強く求めていた。
イ 原告の対応
被告のこのような言動に対し、原告のホーム長は、被告の言動を記録した上で、被告の言動を具体的に指摘の上、言動の改善を求める旨の書面を9回以上に渡って送付しました。
しかしながら、被告の言動が改善されることはなかったため、原告は、被告の母と原告との間の利用契約を即時解除しました(利用契約の内容については、後ろで紹介します)。
もっとも、被告はこれに対して、利用契約の解除の効力を争い、被告の母の退去を拒み続けました。その後、被告の母が入院のため原告の施設を退去したため、これにより、事実上被告の母の退去が完了しました。
ウ 裁判所の判断
被告は、本件に関し、アの言動を行ったことを否定していました。
しかしながら、裁判所は、原告が履践したイのプロセスから、被告による、これらの行為を全て認定しました。
具体的には、原告のホーム長の記録は、原告の職員に対する被告の言動等を詳細に記録しており、その記載内容や体裁から、少なくともその大半は、記載された出来事の都度、記録されたものであると判断されました。
さらに、原告から被告に対して送付した9回の書面についても、もし、被告による暴言、脅迫が実際になかったのであれば、あえて原告の職員らが被告による言動を創作して、被告に対して被告の言動の改善を繰り返し求める理由も必要性がないことから、その信用性が認められました。
被告による言動が認定されたことにより、本件の即時解約は有効であると認定されました。
3.争点②:利用契約解除後に施設利用料を2倍とする合意の有効性
原告の利用契約では、原告側から解除をした場合には、本件契約が終了した日の翌日から本件居室の明渡日までの施設利用料として、本件契約継続中の施設利用料の2倍を支払う旨の規定がありました。
被告は、この規定が消費者契約法10条1項に反して、消費者の利益を一方的に害するものであるとして無効だと主張していました。しかし、裁判所は、この規定の趣旨を、本件契約が終了しているにもかかわらず、利用者が当該契約の目的である居室を明け渡さないためにその使用収益を行えない場合に適用が予定されている条項であって、本件契約終了後における居室の円滑な明渡しを促進し、また、明渡しの遅延によって原告に発生する損害を一定の限度で補填する機能を有するものとし、その賠償予定額は、これらの目的に照らして均衡を失するほどに高額なものではないため、消費者契約法10条1項には反しない旨判断しました。
以上により、利用契約解除後に施設利用料を2倍とする合意も有効となりました。
4.本裁判例のポイントと実務上の留意点
本件では、特に争点①について、カスタマーハラスメントへの対策として非常に参考になるポイントがあります。
まずは、2でも触れた通り、原告は、相手方によるカスタマーハラスメント行為について、記録をとるだけではなく、相手方に対してこれらの事情を記載した書面を繰り返し交付しています。このような原告の行動は、録音や動画がない本件において、裁判所による認定に大きく役立ちました。録音等が難しい中でも、このような工夫により、カスタマーハラスメントを証明することができることを示した点には、非常に意義があります。
なお、この事案では、カスハラ言動が繰り返し行われていたことから、録音を取ることも可能であったと思います。録音がない本件でも上記の記録をもとにカスハラ事実が認定されましたが、より端的にカスハラの事実を基礎付けられるよう、度重なるカスハラが行われている事案では録音することをお勧めします(秘密録音で問題ありません)。
これに加えて、原告は、利用契約の中で、利用者だけではなく、利用者の家族や関係者を含む行為者の行為を禁止し、さらにはその行為の内容を広く捉えていました。具体的には、以下のような規定を置いていました。
利用者、保証人及び利用者の家族その他の関係者は、本件ホームの利用に当たり本件ホーム又はその敷地内において次に掲げる行為を行うことはできない(本件契約第14条)。
⑩号 他の利用者の生活や原告による他の利用者に対するサービスの提供に著しく悪影響を及ぼす言動
⑪号 他の利用者又は原告の従業員の心身又は生命に危害を及ぼす行為
⑫号 本件ホーム又は本件ホームの周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、他の利用者、付近の住民、通行人又は原告の従業員に不安を覚えさせる行為
これらの規定は、契約書策定にあたって重要な要素です。契約書の中には、利用者の行為を禁止する旨の規定はあっても、必ずしも利用者の親族等の関係者の行為について規制しておらず、形式的に見れば、解除事由を充たさないように見える場合があります。
そこで、事前に解除事由を広く定めておくことは非常に重要であり、事業所を守ることにもつながります。
この事例でも、原告の明確な規定を行うという姿勢が、争点②の条項の有効性にも影響を与えたと考えられます。
秘密録音の方法とカスハラの加害者が利用者以外である場合を想定して、解除事由を広く定めておくということの有用性については、こちらの記事でも詳しく解説していますので是非ご参照下さい。
5.最後に:介護現場の法務を向上する書籍のご紹介
弁護士法人かなめ著で2冊書籍を執筆しました。
弁護士法人かなめでは、介護施設や事業所の管理者・施設長の方々から日々法律相談を受けています。
過去の膨大な相談内容の中から「管理者・施設長の方々にこれは抑えておいて頂きたい」というトピックを中心に執筆しました。是非、現場法務の向上にお役立て下さい。
介護現場を運営していると「想定外」の問題がたくさん発生します。
そんなときに慌てないようにリスク管理体制を向上させるためには実際のトラブル事例から学ぶことが最も近道です。
そこで弁護士法人かなめでは、令和3年に判決が言い渡された裁判例を可能な限りピックアップし、それを実務的な目線から分析した書籍を執筆しました。
リスクマネジメント対策の一環にお役立て下さい。