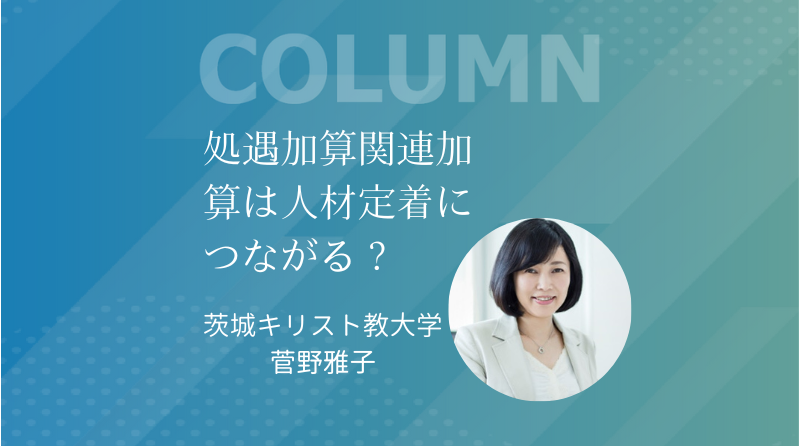この連載では、介護事業所におけるキャリアパスの諸制度についての実態や効果について検討しています。前回までは、キャリアパス制度の重要なサブシステムである「教育訓練」や「人事評価」の効果的な運用について検討してきました。
今回は、処遇改善施策による賃金改善の影響について考えてみたいと思います。処遇改善施策による賃金改善は、政策の意図どおり介護職員の離職防止に貢献しているのでしょうか?
【シリーズ「介護事業所におけるキャリアパス制度を考える」】
①キャリアアップとスキル向上につながるキャリアパス制度とは?
②教育訓練の充実は職員の成長につながるのか
③能力や働きぶりの評価結果に応じて個人の賃金に差をつけるべきか
処遇改善加算等の施策で介護職の賃金は23.2%上昇
2009年よりスタートした処遇改善施策は、介護職員の離職率の高さや採用の難しさが、賃金の低さに起因するという考えによるもので、介護職員の賃金改善とキャリア形成支援が一体的に進められてきました。一連の処遇改善にかかる加算等を通じて、この10数年の間に介護職員の平均賃金は他産業を上回る水準で上昇しています。
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)により、処遇改善施策が始まる前の2008(平成20)年と、2022(令和4)年の平均年収を比較してみると、この14年の間に産業計の賃金上昇率が2%程度であるのに対して、介護職員は23.2%、訪問介護員は35.2%の上昇率を見せています*1)2)。
賃金改善が「離職を抑制している」という経営側の実感
このような処遇改善施策による賃金改善は、離職防止に貢献してきたのでしょうか?
介護労働実態調査により離職率平均の推移を見ると、2007(平成19)年度の21.6%をピークに、この10数年の間に徐々に改善され、2022(令和4)年度調査では14.4%となり、全産業平均15.0%(令和4年雇用動向調査)よりも低い数値となっています*4)5)。この離職率改善傾向に対して、一連の処遇改善施策(賃金改善、キャリアパス導入、職場環境改善など)の効果が少なからず反映されていると考えても良いように思います。
筆者が経営側の方にお話をお聞きする限り、一昔前から考えるとまさに隔世の感で、介護職員の賃金は上昇しており、それが介護職員の満足を高め、離職の抑制につながっている、という実感を持っておられる様子がうかがえます。
介護職がケアマネや相談員になりたがらない傾向も
一方で、処遇改善加算の魅力から、介護職からケアマネや相談員などの他職種になりたがらない傾向が出ているといった話も耳にします。
例えば、一昔前は介護職のキャリアアップの目標はケアマネになることだったのに、今ではケアマネを目指そうとする人が少なくなってしまったという話。
あるいは、以前は学校で社会福祉を学んだ学生は、相談員や地域包括での仕事を希望していたのに、今では逆に介護職から離れたくないという人が多いという話。
また管理職になるより、処遇改善手当と時間外労働手当がつく一般職の方が良いと、管理職になりたがらない傾向もさらに強まったという話。
どちらかというと現状維持を望み、新たな資格にチャレンジしたり、より責任ある仕事を目指そうとする姿勢が弱くなってしまったとおっしゃる経営者の方もいらっしゃいました。
こうした傾向の是非はさておき、それくらい処遇改善の威力は大きいということがうかがわれます。
処遇改善施策による賃金改善は、離職意向を減じていた
上記は経営側の実感としての話ですが、現場で働く介護職員は賃金改善をどのように受け止めているのでしょうか?
筆者はその点について検証したいと考え、処遇改善施策による賃金改善と、介護職員の離職意向の関連について、介護職員を対象にしたアンケート調査のデータを用いて統計的な分析を試みました*5)。
その結果、処遇改善施策による賃金改善は、情緒的コミットメント(組織に対する愛着や帰属意識)を高め、それを通じて離職意向を減じる効果があることがわかりました。
加えて、処遇改善施策による賃金改善には、離職意向を直接的に減じる効果があることも示されました。
この調査では、処遇改善施策による賃金改善について、「私の会社では、介護職員処遇改善加算や特定加算、ベースアップ加算などを算定し、職員に適正に還元している」という質問項目を設定し、「とてもそう思う」から「まったくそう思わない」までの5段階で回答してもらうようにしました。
つまり、加算を算定しているだけではなく、職員が「適正に還元されている」と認知していることが重要になります。せっかく加算をとっていても、説明が不足していたり、納得した支給形態になっていないと、必ずしも介護職員の心理面に良い影響を与えるとは限らないということです。
もちろん、限られたサンプルでの分析ですので一般化はできませんが、この分析の限りでは、処遇改善施策による賃金改善は、政策の狙いどおり介護職員の離職防止に効果があると考えることができる一材料になると言えるでしょう。
政策的に引き上げられた給与は、ありがたがられない?
ただし、ここで一つ考えたいのは、仮に離職の抑制に貢献しているとしても、政府主導の賃上げという外発的な動機づけで組織に留まっているとすると、その効果が長続きするのか不透明な要素があるのも否めないということです。
経済学の立場からは、政府主導の意図的な賃上げは働き手の意欲を上げるとは必ずしも言えないという議論もあります。企業独自の判断による賃上げに比べて、労働者は「高い賃金を受け取る権利がある」と感じ出す傾向があり、賃上げが生産性やモラール上昇を生む効果を期待しにくいのだそうです*6)。
また、外発的なインセンティブが内発的動機づけを損なうことがあることはクラウディング・アウト効果(あるいはアンダーマイニング効果)としてよく知られており、賃金が必ずしも仕事への動機づけになるとは言えない面があることにも注意が必要です。
賃金による動機づけの限界も考える必要があるでしょう。
キャリア自律を育てていく
とはいえ、介護職員の処遇改善は引き続き重要なテーマであることは変わりません。
ただしそのような流れの中で、介護職員が自分自身のキャリア形成に対するオーナーシップやチャレンジ精神を失ってしまうようなことがないよう、自律的なキャリア形成を支援する方向性を強めていく必要があるのではないかと感じます。
例えば、キャリア研修など自分自身のキャリアについて考える機会を設けたり、メンター制度、キャリア面談などキャリアに関する対話を行なう機会を設けたり、自己申告制度や社内公募制度などを通じて職員が自らのキャリア意向を表明する機会を設けるといったことが考えられます。
業界や職種を問わずキャリア自律が問われる昨今ですが、介護職員においても同様で、一人ひとりが能動的にスキルアップ/キャリアアップを考え、自らの処遇を自ら高めていこうと思えるような働きかけが、今後ますます重要になってくるのではないでしょうか。
その先には、法人内で完結するようなキャリアパスではなく、地域の中で複数法人が連携して、より付加価値の高いポジションを数多く作り出していくことも必要かも知れません。
<参考文献>
厚生労働省(2009)「平成20年賃金構造基本統計調査」
1)厚生労働省(2023)「令和4年賃金構造基本統計調査」
2)介護労働安定センター(2023)「令和4年度介護労働実態調査(事業所調査)」
3)厚生労働省(2023)「令和4年雇用動向調査」
4)菅野雅子(2023)「介護職員の離職防止に関する研究: 処遇改善施策とワーク・ライフ・バランス支援施策に着目して」『茨城キリスト教大学紀要』第57巻,pp.125-140
5)横山泉(2022)「賃上げへの課題(中): 要請、生産性波及には限界も」『日本経済新聞』2022年2月17日.