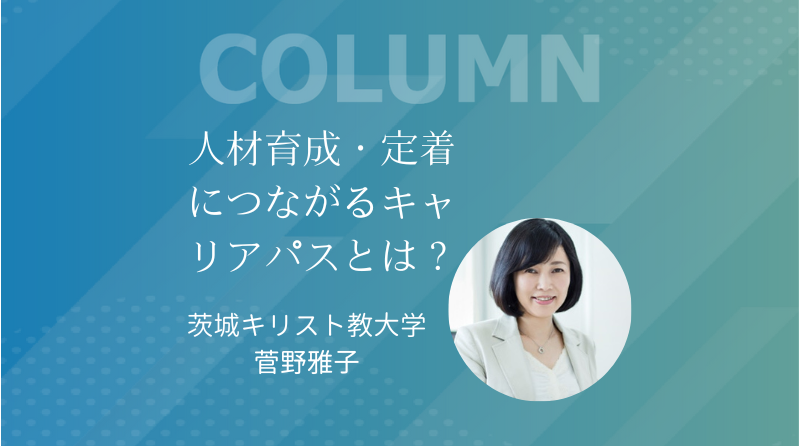皆さまの法人・介護事業所では、キャリアパス制度は有効に機能していますか? 「制度はあるが、うまく運用できていない」とか、「査定のためだけの存在になってしまっている」という現場の声も時折耳にします。
今回から数回にわたって、キャリアパスの制度設計や運用に目を向け、それが本当に人材の定着や育成に有効に機能しているのか、もしうまくいっていないとすれば、どうすればうまくいくのか、切り込んで考えてみたいと思います。
初回は、「キャリアパス制度は機能しているのか」と題して、キャリアパスに関連した問題提起をします。
キャリアパス制度とは人事の基本システム
まず、今さらの話ですが、介護事業所へのキャリアパス導入が政策として進められてきた経緯などを振り返っておきたいと思います。
一般にキャリアパスとは、組織内でのキャリアアップの道筋を指します。
介護業界で「キャリアパス」が大きくクローズアップされたのは、2009年よりスタートした介護職員処遇改善交付金がきっかけでしょう。支給にあたって「キャリアパス要件」が示されたため、介護事業者は大急ぎでこれを満たすための施策を講じる必要がありました。
厚生労働省が示した「キャリアパス要件」を解釈すると、組織内での昇進・昇格の要件を明確にした等級制度を基盤として、それに対応した評価・報酬制度、さらにキャリアアップを支援する教育制度を導入することが求められていると言えます。つまり、人事の基本システムを導入せよということです。
大手法人なら、そのような制度は当たり前にあったかも知れませんが、規模の小さい法人ですと、制度化やルール化の必要性が小さいこともあり、そこまで作り込んだ制度はなかったのではないでしょうか。
多種多様な開発が進んだ「介護版キャリアパスモデル」
「キャリアパス要件」を受けて、当時、業界団体や経営者団体等が、コンサルタント等の力を借りながら、それぞれのサービス分野や業態にマッチしたキャリアパスモデルを作成して公開していました。厚労省のホームページにも紹介されており、今も閲覧することができます。
こうしたキャリアパスモデルを参考にしたり、社労士さんや人事コンサルに相談したりしながら、制度を新たに導入、あるいは既存の制度を手直しした法人は多いでしょう。
本来なら時間をかけて自法人に合った制度構築をするのが望ましいのですが、そんな時間も余力もないケースも多かったかも知れません。
「キャリアパス制度がうまくいかない」という現場の声
介護職員処遇改善交付金はその後、介護職員処遇改善加算として介護報酬に組込まれ、さらに介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等加算と次々加算が積み上げられてきました。
いずれもキャリアパス要件をベースとする施策なので、介護事業者にとってキャリアパス要件をクリアする人事管理システムの導入・運用は欠かせません。厚労省の調査によると、何らかのキャリアパス要件をクリアし、加算を算定している事業所は9割以上と報告されています。
制度も運用も年月とともにブラッシュアップされているのではないかと思うのですが、その一方で、「制度はあるが、うまく運用できていない」、「査定のためだけになってしまっている」、「現場の負担になっている」といった現場の声も時折耳にします。
皆さまの法人・事業所のキャリアパス制度はしっくりくるものになっているでしょうか。
制度整備も定着はマイナス?キャリアパス制度導入の効果検証はまだ不十分
実際にキャリアパス制度の導入・運用は、介護事業所にどのような効果をもたらし、現状どのような課題感があるのでしょうか。それについて明確に検証した調査や研究等は管見の限り見当たりません。いくつかの関連する調査や研究を手掛かりに考えてみましょう。
筆者も委員として参画させていただいた三菱総合研究所の調査(法人調査) (*1)によれば、キャリアパス施策のうち、法人として人材の定着に効果があったと人事担当者が回答しているものとして、「資質向上のための研修の機会を確保した」、「職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系を定めた」、「資格取得のための支援を行った」などの結果が示されています。人事担当者の感覚なので、実際に定着に寄与したのかは検証が必要です。
筆者が介護労働安定センターの「介護労働実態調査(事業所調査)」2017年度のデータを用いて分析を行ったところ、キャリアパス関連の施策が人材定着に対して有意な負の影響を示しました(*2)。具体的には、訪問系と通所系では「能力や仕事ぶりを評価し、賃金などの処遇に反映している」、入所系では「職員の仕事内容と必要な能力等を明示している」、居住系では「賃金水準を向上させている」という施策が人材定着にマイナスに働いているという結果を示したのです。
何が人材定着にプラスに働いているかというと、サービス系列によって少し違いはありますが、「職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている」や「福利厚生を充実させ、職場内の交流を深めている」といったコミュニケーション系の項目でした。
上記は事業所調査で「人材が定着している」という定性的な回答との関連を検討したものなので、実際の定着率との関連の検証が必要です。また、直接効果が見られなくても、事業所の属性や環境条件によって結果が異なることも考えられるので、この分析結果だけで「うまくいっていない」と決めつけることはできません。
とはいえ、「もしかしたら制度を導入してもうまくいっていないケースが多いのかも?」という疑問も捨てきれません。
次回からは、もう少し個別の人事施策に立ち入って考えていきたいと思います。
<参考文献>
三菱総合研究所(2020)『介護サービス事業所の職場環境等に関する調査研究事業報告書』.
菅野雅子(2021)「介護事業所の定着促進策に関する一考察: キャリアパス制度導入の影響に着目して」『ビジネス・ブレークスルー大学レビュー』7(1): 46-59.