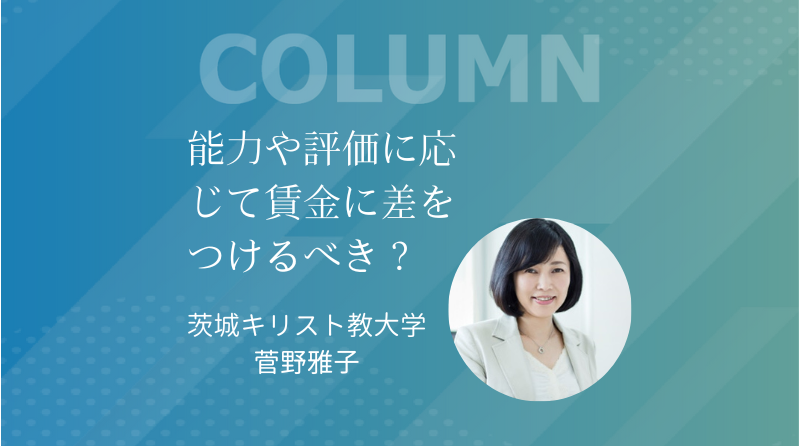この連載では、介護事業所におけるキャリアパスの諸制度について、その実態や効果について検討しています。
前回は、キャリアパス制度の重要なサブシステムである「教育訓練」の効果について、「教える」という方法論の限界や、経験学習理論を踏まえ仕事を通じて成長する職場環境作りが重要である点を指摘しました。
今回は、「人事評価」について考えてみたいと思います。「評価制度がうまく運用できない」「手間や時間がかかって現場の負担になっている」という声もよく耳にします。
個人の能力や働きぶりを評価し、それに応じて賃金に差をつけるという人事評価は、職員のやる気につながるのでしょうか?研究事業などを参考に考察します。
人事評価に対する従業員の満足度は低い
令和4年介護労働実態調査(労働者調査)1)によれば、「人事評価・処遇のあり方」に対する満足度は、下表のようになっています。

満足している割合は2割強(22.5%)程度で、満足度D.I.は-4.7となっており、不満を持っている人の方が多いことがわかります。
誰もが満足のいくような評価制度の構築が難しいのは、他の業界でも同様です。この結果だけで介護事業所の人事評価がうまくいっていないとは言い切れません。
人事評価は職員のやる気を促すのか? 一貫していない研究結果
次に、人事評価が介護職員の職務態度や行動にどのような影響を及ぼしているのか、もう少し詳細に学術研究から確認しておきましょう。
介護事業所の人事施策と離職意向の関連を検討した原口恭彦先生の研究2)では、人事施策のうち「教育訓練」「内部昇進」「業績と報酬のリンク」の3つの施策が介護職員の組織コミットメントを高め、さらにそれが離職意向を減じる効果があるという結果が示されています。
一方で、「個人の能力・働きぶりの評価と賃金の連動」が、介護職員のストレスを有意に高めるという報告3)や、人材定着にマイナスに影響しているという報告4)など、ネガティブな結果を示す研究結果もあります。
このように、これまでの研究では、人事評価が職員の職務態度や行動にポジティブに影響するという結果とネガティブに影響するという両方の結果が見られ、一貫性のないものとなっています。これをどう解釈すれば良いのでしょうか?
人事評価の動機づけ効果は運用次第で変わる
筆者は、こうした一貫しない研究結果は、人事評価そのものには職員の動機付け効果はほとんどなく、その運用次第でポジティブにもネガティブにも作用するということを示しているのではないかと考えています。
例えば、期初に上司と十分に話し合って目標設定を行い、期中には上司や仲間からの支援やフィードバックがあり、期末には評価項目や目標に対する達成度を上司とともに確認しあうといった、日常的なコミュニケーションやフィードバックがある場合と、ない場合はどう違うでしょう?
日頃からコミュニケーションをよくとり信頼できる上司から評価される場合と、部下の働きぶりを十分に把握していない上司や尊敬できない上司から評価される場合はどう違うでしょう?
上記は運用の違いを示す一例ですが、フィードバックの有無、上司との信頼関係、評価プロセスの透明性など、様々な運用の違いによって、人事評価はポジティブにもネガティブにも作用する可能性があるのではないでしょうか。
賃金に格差をつけずコミットメントを高める人事管理の考え方
もう一つ考えたいのは、人事評価の結果を賃金にダイレクトに結び付けることの影響です。実はこれについても、学術的研究で結論が出ているわけではありません。
参考になる考え方として、米国で中心的に研究されてきた「ハイコミットメント人的資源管理」(high commitment human resource management)という概念モデルがあります5)。この人事管理の特徴は、雇用保障や丁寧な教育訓練、スタッフの平等性などを重視し、信頼と互恵性の規範(お互い様の関係)を育み、従業員のコミットメントを高めることを通じてパフォーマンス向上につなげるという考え方に立つものです。
金銭的インセンティブも重視しますが、個人レベルで格差をつけるよりもグループインセンティブ(組織やチームの業績に応じた報酬や、ストックオプションなど)を重視するという考え方に立っています。
医療福祉分野において、社会保障費の上昇を背景にコストダウンとサービス品質向上の両立が要請されており、人材の定着やスキルアップを通じた生産性向上を意図する「ハイコミットメント人的資源管理」が効果的な人事施策になり得ると期待されています。
差をつけるなら月給ではなく賞与や昇格・昇進で
とはいえ、賃金に差がつかないのであれば。「頑張っても頑張らなくても同じだからやる気にならない」と考える向きもあるかもしれません。
しかし、介護サービスの提供は本質的に成果が測りにくい職務であることや、チームケアが基本であること、さらに仕事への内発的モチベーションが相対的に強い人々が多いことなどを踏まえると、賃金に差をつける施策が効果的なのかどうか、検討の余地はあるように思います。とくに月齢給与に反映させると、生活給としての賃金が不安定になってしまう懸念もあります。
人材定着率の良いある社会福祉法人では、月齢給与は一律昇給とし、賞与で評価に応じて差をつけるという方法をとっています。賞与は変動給的な性格を持った賃金なので、賃金の差がある程度受け入れやすいと言えるでしょう。
また、やはり人材定着率の良いある大手民間営利法人では、月齢給与は一律昇給としていますが、評価結果の蓄積を昇進・昇格に結びつけるという仕組みをとっています。少し長い目で見ると、能力の伸長や職務に応じて確実に賃金が上昇しています。
以上は、あくまでも事例にすぎませんが、人事評価と賃金の連動の仕方を考えるバリエーションとして参考になると思います。
育成重視の評価運用を目指す
いずれにしても、前述のように、人事評価そのものは動機づけ要因になりにくい性質のものであり、運用次第でポジティブにもネガティブにも働く可能性があることを踏まえると、まずは運用力を高める必要があります。
評価を通じて、一人ひとりが自分の存在意義と自己成長を感じられるような育成重視の運用を目指すことが重要ではないでしょうか。
そのためには、上司と部下が信頼関係を築くことや、上司の評価力・フィードバック力を高めることなど、組織的に人材育成力を高める努力を最優先させたいものです。
<参考文献>
介護労働安定センター(2023)『令和4年度介護労働実態調査結果報告書(労働者調査)』.
原口恭彦(2015)「介護事業所における内部育成志向人的資源管理が離転職意思に与える影響に関する考察: 組織コミットメントによる媒介効果の検討」『介護経営』(日本介護経営学会), 10(1): 33-42.
堀田聰子(2010)「介護保険事業所(施設系)における介護職員のストレス軽減と雇用管理」『季刊・社会保障研究』(国立社会保障・人口問題研究所), 46(2): 150-163.
菅野雅子(2021)「介護事業所の定着促進策に関する一考察: キャリアパス制度導入の影響に着目して」『ビジネス・ブレークスルー大学レビュー』(ビジネス・ブレークスルー大学), 7(1): 46 - 59.
Baron, J. N., & Kreps, D. M. (1999) Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers, John Wiley & Sons,Inc.