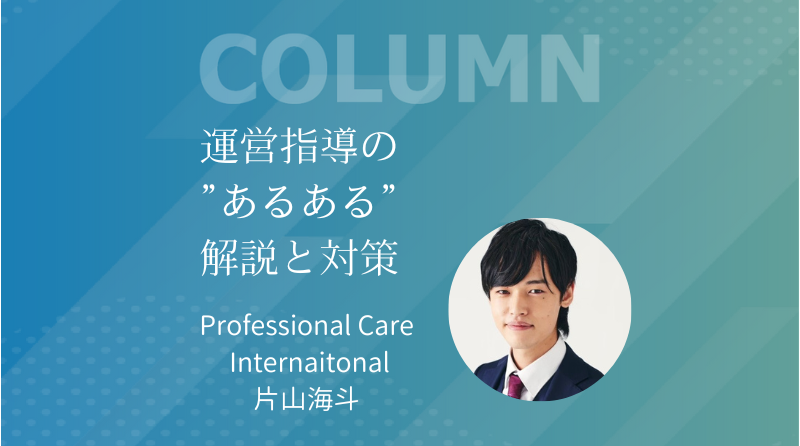サービスや介護報酬請求の適正化を目的に行政によって実施される「運営指導」。
原則は在宅系サービスの場合で6年に1度の実施ですが、不正請求・虐待の疑いや・内部告発があった場合は、抜き打ちで実施されることもあります。
重大な違反が見つかった場合は、監査へ即移行し、さらに厳しい調査が行われることも…。
弊社では、これまで200社以上の運営指導対策に関わってきました。クライアントの中には、過去に運営指導で返還を求められた経験がある方や、周囲の事業者が返還を受けるのを目の当たりにし、不安になって相談された方も多くいらっしゃいます。
その際に伺った返還事例や、弊社独自の調査をもとに、運営指導で指摘されやすい“あるある”とそれに応じた具体的な対策を解説いたします。
1. 運営指導の“あるある失敗事例”と対策
運営指導では、些細な発言や管理の不備が思わぬ指摘につながることがあります。
実際に運営指導を受けた事業者が、「こんなことで指摘されるとは思わなかった」と驚かれるケースも少なくありません。
早速、よくある失敗事例と事前に準備できる対策を紹介しましょう。
① 不用意な発言が問題に… 運営指導では聞かれたことだけ答える!
【失敗事例】
運営指導の際、指導員から「この研修は定期的に実施されていますか?」と質問された際、事業所の担当者が「頻度ってどのくらいでしたっけ?」と答えました。
この発言を受け、指導員は「どれくらいの頻度かご存知ないのですか? ということは、定期的に実施していないのでは?」と疑いを持ち、 その後、詳細な調査が行われ、結果として数十万円の返還を求められることになりました。
【対策】
- 指導員に聞かれたこと以外は話さない
- 「曖昧な受け答え」や「質問で確認」は避ける
- 事前に指摘されやすい項目を整理し、適切な回答を準備する
② 従業員の周知不足が思わぬ指摘に… 全員が理解できる体制づくりを
【失敗事例】
運営指導では、管理者だけでなく、その場にいた従業員に質問が及ぶことがあります。
ある事業所では、指導員がたまたま近くにいた介護職員にこう尋ねました。
「処遇改善加算はどのように使われていますか?」
この質問に対し、従業員は「知りません」と回答。
指導員はこれを受け、処遇改善計画はすべての介護職員に周知しなければならないという基準を満たしていないと判断し、不適切な運用と評価しました。
結果、加算が取り消され、多額の返還が発生することに。
特に処遇改善加算については数千万円単位の返還事例も多く報告されており、細心の注意が必要です。
【対策】
- 従業員にも運営指導の意図やリスク、対策を事前に周知する
- 全員に周知しなければならないものはきちんと周知する
③ 書類の不備で返還リスクが拡大… 記録の確認と管理を徹底する
【失敗事例】
運営指導では、書類の整備状況が細かくチェックされます。
- 指針が策定されていない
- 計画書や議事録が未作成
- 個別計画の整合性が取れていない
これらの不備があったケースではそれぞれ、数百万円の返還を求められることに。
特に、加算の要件や計画書関連の不備は指摘されやすく、返還につながるリスクが高いため、慎重な管理が求められます。
【対策】
- 提供記録・ケアプラン・請求内容の整合性をチェックする
- 加算要件に関する「指針・会議記録・研修記録」などの抜け漏れを防ぐ
- 記録管理システムを導入し、データの一元管理を行う
2. 今すぐできる運営指導対策
運営指導で指摘を受けるリスクを減らすには、日頃の管理体制の見直しと事前準備が欠かせません。特に、一度返還を受けると、その後の事業運営に大きな影響を与え、場合によっては事業が継続できなくなることもあります。指導当日に慌てることのないよう、今からできる対策を実施していきましょう。
① 定期的な内部チェックを実施
運営指導で特に確認されるのが、提供記録・ケアプラン・請求内容の整合性です。日頃から書類を確認し、加算要件や人員配置が適正であるかチェックしましょう。
- ケアプランの記録と提供記録が一致しているか
- 請求した加算の要件を満たしているか
- 勤務実態と配置基準が合致しているか
また、事業所内で自主点検を行う体制を整え、定期的に記録の不備を確認することが重要です。
② 従業員教育の強化
運営指導では、管理者だけでなく、現場職員も指導員から質問を受けることがあります。そのため、職員全員が加算や制度の基本的な仕組みを理解しておくことが求められます。また、日頃から加算の要件に沿って定期的な研修や会議をしましょう。
③最新ツールの導入による書類管理
運営指導では、書類の不備や記録のズレが指摘されやすいため、書類の管理を徹底する必要があります。
加算に関する書類は、運営指導で重点的にチェックされるため、常に最新の状態に更新し、記録の整合性を確保しておきましょう。また、書類管理の負担を軽減するために、電子データ化やシステム導入を検討するのも有効です。
④ 外部監査の活用
法改正により運営指導の指摘ポイントは変化するため、外部の専門家による監査を活用するのも有効です。
- 第三者の視点で書類のチェックを受ける
- 不備を指摘された場合の具体的な改善策を講じる
- 指摘されやすいポイントを事前に把握し、対策を講じる
事業所内部での確認だけでは見落としが発生することもあります。外部の監査を受けることで、事前に問題点を洗い出し、対応策を準備できるため、リスクを最小限に抑えることができます。
運営指導は、事業運営の見直しを行う良い機会でもあります。普段から適切な体制を整え、書類の管理や従業員教育を徹底することで、運営指導に慌てることなく対応できる環境を整えることが重要です。
今回のまとめ
運営指導は、事前の準備がどれだけできているかが大きな分かれ道になります。
「何から始めればいいかわからない」「運営指導が不安だ」という事業者の方は、運営指導の通知が来る前から早めに対策を講じることが重要です。
事前に準備を整え、万全の体制で運営指導に臨みましょう。
連載記事一覧
①中小規模の介護事業者が直面する3大課題とその解決策
②介護事業所における人材獲得に向けた戦略立案の方法
③とにかく数をこなす営業”を脱するための根拠ある活動とは?―介護事業所における営業戦略の見直しポイント