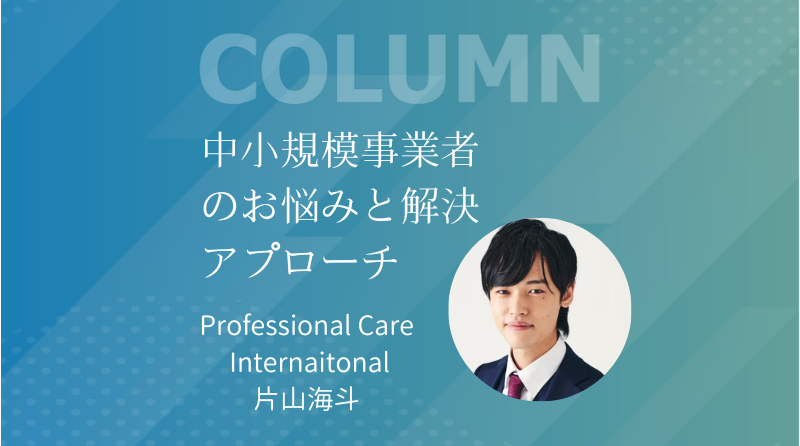近年、中小規模の介護事業者の倒産が相次いでいます。2024年度改定で基本報酬が引き下げられたことを受け、訪問介護を巡る経営環境の悪化はとりわけ深刻です。
そこでこの度は、介護事業者様の経営課題解決をお手伝いする立場から、特に、中小規模の事業者様が直面している3つの問題を提起し、具体的な解決策について解説します。訪問介護事業特有の課題にも触れてまいります。
本記事が、問題解決のヒントとなれば幸いです。
介護事業者からの3大相談「採用」「営業活動」「運営指導」
初めまして、Professional Care Internaitonal株式会社の片山海斗と申します。
これまでの経歴として、10代で起業して訪問介護と居宅介護支援事業を手掛けきたほか、介護の学校やWEBマーケティング会社の立ち上げも経験しました。これらの経験を生かして現在は福祉・介護専門のコンサルティングファームを運営しています。
これまで100社以上を支援してきた経験から、多くの事業者が抱えておられるお悩みは「採用」に関するもの、「営業活動」に関するもの、「運営指導」に関するものに整理できると考えています。
今回はこの3つの課題について、実際にあったご相談をご紹介しつつ、その解決に向けたアプローチをご紹介いたします。
採用の課題:人材獲得を外部に委ねる「丸投げ広告」
まず、採用に関連する課題についてです。
介護事業所が求人広告を出す際には、ハローワークや広告代理店などに求人広告で訴求する内容を丸投げしてしまっているケースが多いようです。
しかし、この方法をとった事業所では、自社が求める人材と実際に面接に来る人との間に乖離が生じてしまい、採用に繋がらなかったり、早期離職が起こってしまったりといった問題が発生しています。その結果、一人あたりの採用コストが上昇し、介護サービスの質が低下する原因となっています。
丸投げ広告をやめるには?
自社にあう人材獲得を外部に丸投げしてしまっている状況を抜け出すために、まず第一歩は、介護職員が自社で働くメリットを可視化(見える化)することです。
例えば、以下のようなイメージです。
- 急な休みにも対応できる
- 副業・ダブルワークOK
- 昇給制度がしっかり整っている
このように自社で働くメリットを明確にして求人媒体に掲載することで、より多くの求職者の目に留まり、面接数が増加する傾向があります。インターネットの求人に掲載する場合ではPV数(ページビュー数)や応募者の面接移行率に影響します。
人材不足は介護業界全体の課題。だからこそ事業所が取るべき戦略
いくら介護事業所が人材獲得の施策に力を入れても、2040年には介護職員が約70万人不足するという統計が出ている以上、人材不足の根本的解決には国の施策が必要です。地域の事業所がどれだけ投資をしても、人材そのものの母数が不足しているため、面接に至らないことが多いのが現実です。だからこそ、事業所でできることは「個別の働き方支援」であり、離職率の低下に主眼をおいた人材獲得戦略が必要なのです。
営業活動の課題:新規利用者の獲得ができず、売上が上がらない
弊社には多くの事業所から「赤字続きで潰れそう」「営業の方法がわからない」といった相談が多く寄せられます。
その背景には、経営者が現場出身であるケースが多く、営業経験がないことや、効果的な方法を知らないということがあります。よほど人口が少ない地域ではない限り介護需要が高いにもかかわらず集客できないのは、適切な営業戦略やマーケティング手法を知らないからと言えるでしょう。
訪問介護事業所の強み訴求は難しいからこそ、しっかり考えるべき。
特に訪問介護は、通所介護や介護施設と比べると事業所の差別化が難しいと言われています。それでも、他社との差別化を図らなければ、利用者を獲得することはできません。差別化のポイントとしては、個別対応のようなサービスの質を高める取り組みや、自立支援に特化したサポート、24時間対応といった強みを打ち出すことが大切です。こうした取り組みによって、利用者やケアマネ、相談員に選ばれる事業所としての地位を築くことができます。
運営指導対策:7割以上の介護事業所は法令遵守ができていない
最後に、運営指導の対策についてです。
介護事業所における運営指導対策(法令遵守)は、サービスの質を向上させ、利用者の安全を確保するために不可欠な要素であり、経営上の機会損失を防ぐための重要な施策です。しかし、現実にはコンプライアンスが十分に行き届いていない事業所が全体の7割を占めています(弊社独自統計(全国124社対象:運営指導対策サービス提供時における指摘・指導割合)。その結果、多額の報酬返還(国に報酬を返すこと)に繋がることもあります。
事業所の対応を複雑化させるローカルルールの存在
介護事業は、原則として介護保険法に基づいて運営する必要がありますが、各県や市町村には独自のルール(ローカルルール)も存在します。このローカルルールが原因で、全国的に書類や運営指導の確認項目が統一されないという問題が生じています。その結果、運営指導員によって指導内容が異なったり、口頭指導の厳しさが変わるといった事象が発生しています。
さらに、ローカルルールによって介護事業者に求められる対応が地域ごとに異なるため、事業者はそれぞれの地域に適応するために時間を費やす必要があります。このような非効率性は、事業者にとって負担となり、ひいては利用者へのサービス提供にも影響を及ぼす可能性があります。
内部監査を徹底することが健全な経営の第一歩に
運営指導での返還を防ぐためには、内部監査の徹底が第一歩となります。これが、健全な事業経営にもつながります。
「そもそもモニタリングって何?」「介護計画書の同意日はいつ?」など、書類を作る際に気軽に相談しやすい環境を整備したり、そのような相談ができる機会を定期的に設けることで、サービス提供責任者や管理者、相談員といった従業者のストレス緩和が期待され、離職の防止にも効果を発揮します。
弊社では、事業再生や事業展開といった多岐にわたる相談をお受けしてきていますが、まずは運営指導の観点から足元をしっかりと固めることを徹底しています。
次回は、自社にあった人材獲得の戦略について、さらに掘り下げてご紹介してまいります。