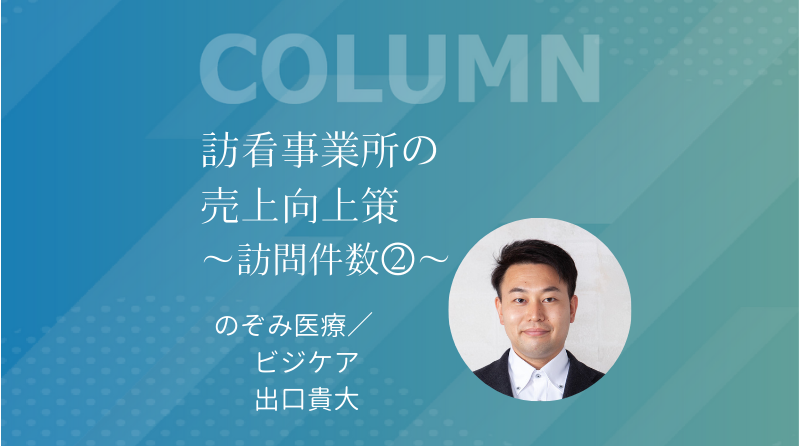これまでに訪問看護ステーションの『売上を向上させていくための考え方』についてお伝えしてきました。今回は、このシリーズ最後のテーマである『訪問頻度』についてお伝えしていきます。
これまで前回の記事をまだ読んでいない方は合わせて読んでいただけたらと思います。
■これまでの記事まとめ
訪問看護ステーションにおける売上を上げる戦略思考
・訪問単価を上げよう(1)(単位、診療点数)
・訪問単価を上げよう(2)加算を取る意識の醸成
・訪問件数を上げよう(3)(新規顧客、既存顧客)
軽視されがちだが、1番着手しやすい「訪問頻度」
訪問看護ステーションの売上を上げようとしたとき、まず「新規利用者の獲得をしよう」と考える方が多く、訪問頻度は軽視されがちかもしれません。
しかし、実は売上を上げるために即効性があり一番取り組みやすい方法は「訪問頻度」を上げることです。
今回は訪問頻度に関して以下の4点をお伝えしていきます。
1.現在の訪問頻度に関する意識チェック
2.訪問頻度が変わる事の利益へのインパクト
3.訪問頻度は他人任せにしない
4.意識して取るべき行動とは
1.チェックが多い方は気をつけて
以下普段の業務で行っている事をチェックしてみて下さい。いくつ当てはまるでしょうか?
□医師から依頼を受けた訪問頻度の通り、そのまま依頼を受け入れている
□もっと訪問回数を増やした方が良いと考えているが、提案できずにいる
□訪問する頻度に応じた提供サービスの違いをイメージしたり説明したりすることができない(週1回場合と週2回の違いなど)
□ご利用者様やケアマネジャー、医師に対して言われたこと以外に新たな提案できていない。また、状況が変わっても新たなケア内容を提案していない
□ご利用者様のニーズを探す努力が出来ていない
上記についてあてはまる項目が多い場合、訪問頻度が低くなったり不安定になったりする可能性が高いです。
以下の内容を踏まえ、考え方や取り組みを見直してみましょう。
また、訪問頻度が変わることで利益にも大きな影響がで出てきます。そのことについてもお伝えしていきます。
2.訪問頻度が変わる事の利益へのインパクト
訪問看護の売上は「平均単価ご利用者様数訪問頻度」で構成されます。
ここで、
平均単価:9,000円、ご利用様数:100名、費用(支出):600万円
の時に訪問頻度が変わることでどれくらい売上や利益が変わるのかを比べてみます。
1人あたりの訪問が7件/月のとき
これまでに約100事業所の決算書を見てきましたが、
多くの訪問看護事業所では、ひと月当たりの1人のご利用者様に訪問する頻度(訪問頻度)は「8~9回」です。
介護保険の週2回訪問をベースとしながら、医療保険で週3回以上の訪問が1割あり、同じくらいの割合で週1回、隔週訪問の依頼もお引き受けしている、そういったイメージです。
一人に対する訪問頻度が7件/月だと、週1回訪問の割合が多く占める状況になります。
その場合の利益を見ていきます。
売上(収入)=平均単価お客様数訪問頻度
=9,000円100名7
=6,300,000
利益=売上(収入)-経費(支出)
=6,300,000-6,000,000
=300,000
という結果となります。
 訪問頻度を変えた結果を見ていきましょう。
訪問頻度を変えた結果を見ていきましょう。
1人あたりの訪問が7.5件/月のとき
売上(収入)=平均単価お客様数訪問頻度
=9,000円100名7.5
=6,750,000円
利益=売上(収入)-経費(支出)
=6,750,000-6,000,000
=750,000円

今回の例を比べてみると、訪問頻度自体は「7」から「7.5」と約1.07倍の変化でしたが、利益は「350,000」から「750,000」と約2.14倍変わってきました。
少しの訪問頻度の変化で利益が大きく変わるという事が分かると思います。
3.訪問頻度を他人任せにしない
訪問頻度を自分たちで管理していくために重要な事は、「誰が訪問頻度を選んでいるか」を把握し、それぞれに対して適切な対応を行う事です。
訪問看護で主に訪問頻度を決める主体となるのは、ケアマネジャー、ご利用者様、医師のうちの誰かとなります。 この方々にこちらが必要とする回数を納得してもらえるように説明をしていく必要があります。
以下、それぞれの特徴と提案方法をご紹介します。
ケアマネジャーの場合
ケアマネジャーは「単位」と「ご利用者様の目に見える課題」を検討の上、訪問回数を提案します。
しかし、これは絶対的なものではなく、「大体これくらいだろうか」と必要性について予測した頻度です。
そのため、「こういった方には、こうしたケアの内容が必要になるので、訪問頻度を週1回ではなく2回で関わらせてもらえないか」と医療的な視点で根拠を明確にして伝えることで必要性を理解してもらいやすくなります。
これはご利用者様、医師に伝える際にも当てはまりますが、こちらから提案する“必要性”については押しつけて強引に変更してもらうのではなく、あくまでご提案という姿勢でお伝えして下さい。
ご利用者様の場合
ご利用者様はそもそも訪問看護を使ったことがないので、何回来て貰えば良いのか分かりません。ケアマネジャーから言われたとおりに決めていたり、感覚で決めたりしていることがほとんどです。また、本人の訪問看護への動機付けが弱く、「必要ない」と考えていたら「来て欲しい」と思う回数も減ります。
そのため、実際に訪問看護でどういうサービスが提供できるのか、自分の状態なら週に何回くらい利用することで、生活課題の改善につながるのかを、お伝えすることが大切です。
ご利用者様が病気や障害を抱えながらも叶えたい希望やのぞみは何なのか、どうやってご利用者様らしい生活を送ってもらえるのかをしっかりとイメージしながら私たちが出来ることを提案していって下さい。
医師の場合
医師は病状やADLからどういった治療が必要か、それに対してどれくらい訪問看護が必要かを評価しています。
しかし、医師の診察時間は訪問看護やケアマネジャー以上に多くとる事が出来ず、症状や問題点以外の生活面や環境面をじっくり見ることができません。
そのため、実際に訪問でご利用者様へ介入が開始したタイミングで、病状を含めご利用者様を取り巻く生活状況や環境面での懸念事項などをお伝えすることが大切です。また私達から生活課題の改善に必要と思われる”必要性のある”訪問回数の説明ができれば、医師から訪問頻度を増やす許可をもらえる可能性が高くなります。
「医師から言われたからこの回数で、かつこの内容しか提供できない」と思い込むのではなく、そのご利用者様の生活全体を見渡して、何が必要なのかどういった介入をすべきなのか、それはなぜなのか、それを踏まえて何回訪問が必要なのかをしっかりと医師に伝えていきましょう。
4.意識してとるべき行動とは
意識して行動に起こせば、訪問頻度は必ず変わってきます(※あくまでもご利用者様にとって”必要性のある”ケアの提案が前提です)。
そのためにどういった行動を実際に行っていけばいいのかをお伝えします。
(1)依頼された通りの頻度で訪問看護を引き受けるのではなく、ご利用者様の状況やケアマネジャーの依頼の意図を十分汲み取り、能動的に訪問頻度を提案する
(2)訪問回数を増やした方が良いと感じたときはその理由とともに適切な訪問頻度を提案する
(3)ご利用者様やケアマネジャー、医師に対して言われたこと以外にも自分たちが出来ることはないか探し、提案する
(4)ご利用者様の状況が変わった時はすぐに新たなケア内容を提案する
(5)訪問回数の多寡に応じて自分たちが何を提供できるかをイメージし、説明できるようにしておく
(6)「3.訪問頻度は他人任せにしない」でお伝えした相手ごとへの対応を意識して行動に起こす。
(7)目的や意味のある看護を提案すること。またその提案には、ご利用者様・ケアマネジャー・医師の想いや考えが組み込まれていること。
最後に
「訪問看護ステーションにおける売上を上げる戦略思考」についてシリーズでお伝えしてきました。
売上を上げる方法として「ビラ配りや新規開拓だ!」といった手段が目的になってしまわないように、自身の事業所の資源や環境を把握した上で、どういう考え方をした方が良いのか優先的に何を取り組んでいった方が良いのかを考え決断していく事が大切です。
是非この機会に自事業所の売上の上げ方を見直してみませんか?