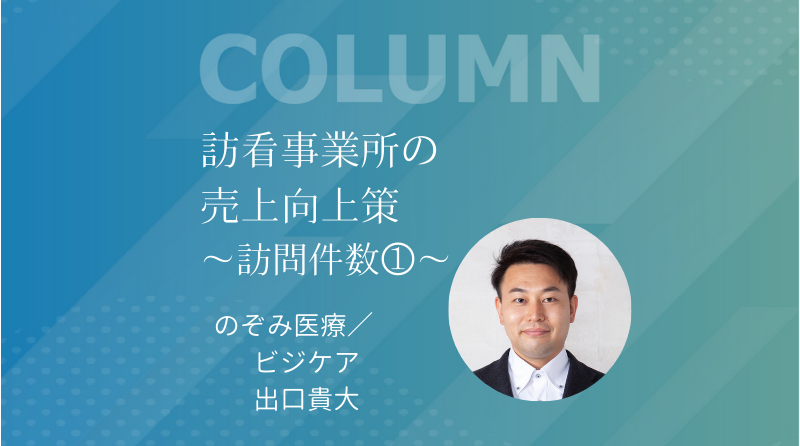これまで複数回にわたって「売上を上げていくための考え方」についてお伝えしています。
今回はその中でも、『訪問件数の向上(新規顧客、既存顧客)』にフォーカスします。
前回の記事をまだ読んでいない方は合わせて読んでいただけたらと思います。
■これまでの記事まとめ
訪問看護ステーションにおける売上を上げる戦略思考
・訪問単価を上げよう(1)(単位、診療点数)
・訪問単価を上げよう(2)加算を取る意識の醸成
訪問看護における訪問件数を増やすためには新規と既存、両方にアプローチする
皆さまは訪問件数を増やすためにどういった活動をされていますか?
営業のチラシを配ったり、挨拶回りをしたりと色んな取り組みをされている事かと思います。
多くの現場を見る中で、
・新規の依頼は来ているけどキャンセルが多く、訪問件数の合計が変わらない、あるいは減っている
・事業所の認知度は上がっているのに新規が来ず、新規が来ない分析をせずにひたすらチラシを持って行っている
という現場が多い事に驚きを隠せません。
このようなケースへの対策を踏まえつつ、訪問件数を増やしていくアプローチについて説明していきたいと思います。
マーケティングモデル「AIDMA」を活用した訪問看護の新規依頼獲得の戦略
新規の依頼を獲得していくには、なぜそれが来ないのかを把握して対策を練る必要があります。
こういった時に役に立つのがAIDMA(アイドマ)モデルです!
AIDMAとはマーケティング用語で、消費者の購買行動プロセスを説明する代表的なモデルの1つです。
Attention(注意)→ Interest(関心)→ Desire(欲求)→ Memory(記憶)→ Action(行動)の頭文字を取ったもので、標準的な購買プロセスを分析するために広く使われており、訪問看護事業の戦略立案にも活用することができます。
以下の図1をもとにご説明します。

(1)事業所立ち上げ前、直後に効果的な営業手法-「注目・興味」を惹くアプローチ-
この時期はそもそも事業所があること自体を認知されていないので、
まずは「依頼を受ける事が出来ますよ」「こういったケースも対応できますよ」「こういう事業所ですよ」といった認知度を高めていく必要があります。
図1で言うと注目・興味にアプローチをしていく段階です。
この段階では、
・事業所がオープンしたことを知らせるチラシを配る
・オープンの挨拶回りをする
・事業所の説明やスタッフの構成や特徴を伝えに行く
などの手法が効果的です。
まずは地域の皆様に事業所を知って頂き、かつ同時に自分たちも地域のケアマネジャーや医療機関を知っていくための情報収集が重要になってきます。
一通り挨拶回りが終わったタイミングで、次はケアマネジャーや医療機関の>欲求・記憶・行動にアプローチをしていきます。
一回挨拶をしただけではすぐに忘れられてしまいますし、チラシもすぐに捨てられてしまうでしょう。
そのため、記憶に残してもらうために
最初の半年間は1ヵ月に2回ほど定期的に挨拶をしたり勉強会の企画をするなど
・いかに信頼を得るか
・「お願いしてみてもいいかな」、と行動に移してもらえるか
といったところを意識してアプローチすることが大切です。
私が実際にやっていてかなり効果を感じたのは勉強会の提案です。
2021年度の介護報酬改定により、訪看だけでなく居宅介護支援事業所やデイサービスなどの介護事業所関連も認知症、虐待防止、感染症対策などの研修が義務化されました。
また、居宅介護支援事業所は特定事業所加算の算定のために計画的な研修を行わなければいけません。
担当者が多く、忙しいケアマネジャーには、研修の内容を考えて開催するのはかなりの負担かと思います。その研修を誰かが代わりに計画・実施してやってくれたらかなり助かると思いませんか?
この研修要件は、必ず居宅内のスタッフが企画しなくてはいけないものではなく、外部の方がに講師をしてもらっても満たせるのです。
そのため、こちらから『もしよければ一緒に研修をしませんか?』『事業所の皆さま向けに研修をしましょうか?』と提案して頂くと、かなりの確率でお願いしたいと依頼が来て、その関わりが新規の依頼につながる可能性は高いんです。
今であれば、ZOOMなどで合同勉強会するのも一つの手です。ぜひ研修会という切り口も検討してみてはいかがでしょうか。
(2)事業所立ち上げから半年から2年ごろ有効な営業手法-2件目の依頼を獲得する「欲求・記憶・行動」へのアプローチ
この時期は事業所の認知度が高まり、新規の依頼が増えてくる時です。
気を付けなくてはいけないのは、同じケアマネジャーから2件目の依頼が来るかどうかということです。
「試しに」と依頼をもらっても、利用してみて
・連携が取りにくい
・意図したように訪問してもらえない
・報連相がない
などというが印象が残れば、再び依頼を受けることはありません。
この時期には、
欲求・記憶・行動にアプローチしてまたお願いしたいなと思ってもらえるように関わっていく事が大切です。
この時期でお勧めの行動は
・ケアマネジャー、 医師の相談にフレキシブルに対応する
・1件新規をもらったケアマネジャー、 医師から2件目がもらえているか意識してチェック、行動に起こす
・ケアマネジャーのモニタリング前、医療機関への受診前やドクターの訪問診療前にFaxなどで情報共有をする
を行う事です。
特に、最後の情報共有はかなり効果があります。
ケアマネジャーや医師からすると、月末月初に報告書や、計画書を送ったり、緊急時に連絡してくれたりするのは当たり前です。その当たり前の連絡だけでは、2件目の新規依頼をもらえるの可能性はかなり低いです。
かといって、業務量が増えていく中でこまめな連絡を継続する事が難しいかと思います。
同じケアマネジャーや医師から再度依頼してもらうための取り組み
ではどうやって情報共有をすれば一番効果的かというと、
「ケアマネジャー、医師がご利用者様のご自宅に訪問する2、3日前」に情報共有する事です。
病院に受診する時は、受診する2日前に地域連携室か外来看護師に連絡しFAXを送ります。
ケアマネジャーは、基本的には月に1回しかモニタリングで訪問しませんし、医師も医療機関受診時や訪問診療時の月に1-2回(ご利用者様の状態によって回数増減あり)しか会いません。
そこから得た少ない情報でご利用者様のアセスメントをする必要がありますが、ご自宅の生活をすべて把握するのは難しいのです。
そこへ、直近のご利用者様のまとまった情報が訪問看護から共有されるとどう思うでしょうか?
モニタリングや訪問診療で関わるポイントが整理されて、かなりの助けになります。また、それは、ご利用者様への質の高いケアにもつながります。
こうした情報共有の方法を継続していくと、「あそこの訪看に関わると、情報が網羅されて仕事がはかどる、助かる」という印象を与えることができ、次に新規の依頼がもらえる可能性が高くなります。
今一度、ケアマネジャー、医師への情報共有の仕方を見直してみませんか?
(3)事業所立ちあげから2年以降の活動-ABC分析で営業活動の効率化を図る
ここからは少し時間を進め、訪問看護事業所を開設して2年以上が経った頃の営業戦略について考えてみましょう。
先ほどのAIDMAモデルでいうとこの時期は、地域でのシェア率を踏まえながら新規開拓を検討しつつ、既存のお付き合い先に対しては欲求・記憶・行動へのアプローチを続けます。
ただ2年以降となると、ご利用者様の数も増え、それまでのこまめな連絡を全員に継続するのは難しくなってきます。
そのため、この時期はお得意先とそうでない先とを優先順位付けして関わっていく事が大切です。
優先順位は、お付き合いのある居宅介護支援事業所や医療機関ごとに依頼数を集計し、その数の多さによって、お得意先をA、普通をB、頻度が少ない先をCと3分類します。
連携先にもよりますが、目安として5~10カ所ごとで分類します。
そして、分類別にコンタクトを取る頻度を分け、
それぞれ最低、Aは月3回、Bは月2回、Cは月1回コンタクトを取ります。
コンタクトをとる方法としては、
・報告書、計画書を直接渡しに行く
・モニタリングの報告をする
・実績を持って行く
などがあります。ケアマネジャーや医師のキャラクター・好みなどを把握して踏まえつつ、どの方法をとるか選んで検討するのがお勧めです。
既存のご利用者様のキャンセルを防ぐことに目を向ける
ここまで、新規の依頼を獲得する手法を例ですがにしてきましたが、実は新規の利用者獲得以上に大切な事があります。
それは既存ご利用者様のキャンセルを防ぐという事です。
必死で新規依頼を1件獲得したが、気が付くと新規2件分のキャンセルが出ていたという話は良くあります。
そのためキャンセルが月々どれくらい出ているのか、その理由はどういったものか、どうやったら無くすことができるのかを検討する必要があります。
キャンセルの理由を知り、対策する
キャンセルの理由は、職員が理由に起因するのものとご利用者様に起因するものと主に2種類あります。
まず職員に起因するの理由としては
・職員スタッフに欠員が出て振替ができない
・キャンセルが売上に与える影響について、職員の認識が足らない
などがあります。
上記のようなことが起こっている場合は、職員の意識付けと休むときは振替を徹底して行うよう指導します。
次にご利用者様側の理由としては
・訪問看護に来てもらう理由付けが弱く、私用を優先してしまう
・体調が悪くてキャンセルする
・入院やショートステイのため
などがあります。
入院やショートステイなどは仕方ないですが、ほかの2つは事業所側の体制で対策する事が出来ます。
「訪問看護に来てもらう理由付けが弱く私用を優先してしまう」という理由に関しては、
再度訪問看護の必要性をお伝えし直したり、ご利用者様と一緒に目標設定しながら1カ月ごとに目標を振り返りモチベーションコントロールをしたりするようにします。
数値やグラフなどをまとめ、努力の成果や取り組みを評価してお渡しするのも効果的です。
「体調が悪くてキャンセルする」という理由に関しては
体調が悪いからこそ訪問看護を利用しているので、悪い時こそ体調を確認しに行くべきです。
そのため、体調が悪い時向けの訪問看護の内容やリハビリのプログラムがある事業所であれば、体調がすぐれない時に提供するサービス内容を事前にご利用者様と決めておきます。
事前に手を打つことで、キャンセルはかなり減ってきます。
キャンセルに隠されたご利用者様の本当のメッセージに目を向けて取り組めるように努めて下さい。
自事業所の課題を整理し、効果的なアプローチを
今回の記事を読んでいただき、新規獲得や既存のキャンセル数を防ぐ取り組みで
・事業所として何が出来ているか
・現状としての課題は何か
・それに向けて何から取り組んだ方が良いか
しっかり見極めながら訪問件数を戦略的に増やしていって下さい!