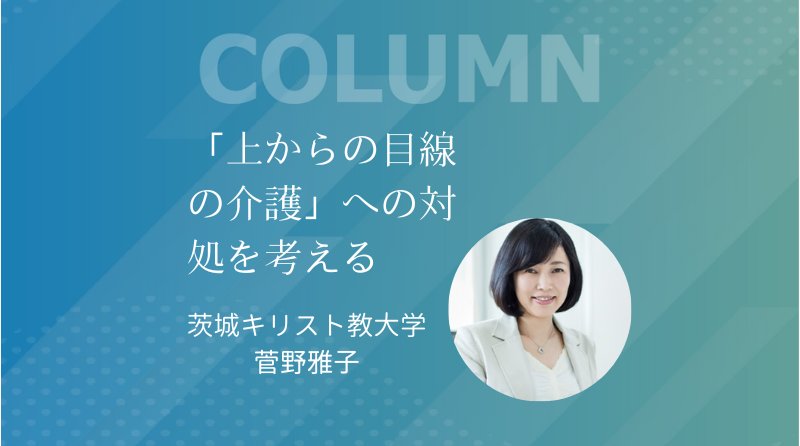引き続きこのシリーズでは、現場のリーダーや管理者からよく聞かれる悩みを題材に、介護現場で起こりやすい人材問題とその対処法について検討したいと思います。
第2回は、「上から目線の介護」が横行してしまうという、訪問介護の若手サービス提供責任者の悩みについて一緒に考えてみましょう。
(事例は、筆者が見聞きした実話を題材にしたフィクションです)
サ責Bさんの悩み:ヘルパーさんの“上から目線の介護”
Bさん:「中高年のヘルパーさんは、人生経験も豊富で、利用者さんとのコミュニケーションも上手なので、本当に貴重な存在です。もういま、とにかくヘルパー不足なので、仕事受けていただけるだけでも本当に感謝なのです。でも、人生経験豊富なだけに、ちょっと厄介なところもありまして・・・」
そう語り始めたBさんは新卒で在宅介護の会社に採用され、入社5年目若手のサービス提供責任者です。
Bさん:「例えばですが、利用者と濃密な関係を築いてしまって、代わりのヘルパーじゃダメだというケースがあったりしますね。他の目が入りにくくなるといいますか、そういう閉鎖的な関係の中ではやはり問題が起きやすくなります」
Bさんは続けます。
Bさん:「当人同士は気にしていないかもしれないですが、赤ん坊に言うように、“〇〇しないとダメだよ”とか“〇〇って言ったでしょ”といった“上から目線”の言動があったりします。
それと、ヘルパーが自分の経験と感覚で思うとおりにやりたいと、“利用者本位”ではなく、“自分本位”の介護になってしまうことも多いのです。それもある意味“上から”ですよね。同行訪問とか定期訪問の時なんかに、そういう話が出てきますね」
Bさん:「良かれと思ってやってくださっているのは分かるのですが、こういう方に限って、注意すると逆切れするので、なかなか対応が難しいですね」
このようなBさんの悩みに、どう対応したらよいでしょう。
ヘルパーの言い分から状況を把握する
これはやはり目をつぶったままにしてはいけないケースです。
前回のケースと同様、状況把握と改善に向けて、まずはヘルパーの言い分を十分に聴くところがスタートと言えるでしょう。
人生経験に基づく信念があったりプライドが高かったりする場合、自分のやっていることを認めてもらえなかったり、ましてや咎められたりすると、自尊感情が傷つけられ、怒り心頭“逆切れ”してしまうのも不思議ではありません。
まずは、どんな思いでその利用者に向き合っているのか、十分に本人の話を聴くことです。相手の話を聴き、共感できるところはそれを伝え、認めるところは認め、労うところは労うというステップは、念入りすぎるほどやった方が良いかもしれません。
そのような方は、一旦納得してもらえると、実はものすごく力強い味方になってくれることも多かったりするのです。
「上から目線」は、介護という仕事が陥りやすい本質的特性
とはいえ、上記はある意味、対症療法に過ぎないかも知れません。介護労働の本質的な特性について、管理者と職員が十分に理解してサービスを提供することが必要です。
そもそも医療や介護などのヒューマンサービスの顧客は、病で治療を必要とする人や、生活するのに他者の助けを必要とする人、言い換えると“社会的に弱い立場に置かれた人”です。
一方のサービス提供者は、社会サービスという公共性を背景に社会的資源や正当性を有すると同時に、顧客にはない専門性を有しています。そのため、「サービス提供者=強者」、「サービス利用者=弱者」というサービス関係が構造的にセットされていると言われています。つまり、労働特性によって、放っておけばそのような関係に陥りがちだということです。高齢者虐待などは、その延長線上にあると言っても良いでしょう。
管理者も職員も、こうした特性を十分に理解し、自分たちがサービスを提供するときの姿勢を意識的にコントロールすることが求められます。介護事業所では、プロとしての意識と行動を定着させる教育が必要になるのです。
「ありがとう」という魔法の言葉が作り出す不均衡な関係
強者と弱者の関係が存在するからこそ、利用者は「ありがとう」と言うでしょう。「あなたがいてくれて良かった」、「あなたのお陰で私は生きていられる」と繰り返し伝えてくるかも知れません。
そのような感謝の言葉は、介護職にとって大きなやりがいや支えとなるかも知れません。しかし、その一方で、「介護する側=強者」、「介護される側=弱者」という不均衡な関係をより強固なものにしていくという副作用も有しています。
専門職によって提供されるサービスの質は、素人には評価できない面もあります。「利用者に喜んでもらえる」、「感謝してもらえる」からといって、専門職としての知見や先見性に基づく判断は他律的に行われるものではないはずです。
専門職としての仕事の価値を考えるならば、仕事のやりがいや評価軸が「利用者からの感謝がやりがい」に偏っていて良いのか、考えてみる必要があるかも知れません。
そのようなことを職場で問題提起し、議論しあえる機会を作ることも重要ではないでしょうか。
「利用者本位」とは「顧客が上」ということなのか
では、「サービス提供者=強者」、「利用者=弱者」という関係を逆転させれば問題は解決するのでしょうか。営利サービスでは、サービス提供者が顧客のニーズを満たし、利用者に「ありがとうございました」と感謝するという、ある意味「顧客が上の立場」であることが一般的です。
しかし、介護のようなヒューマンサービスにおいて、これをそのまま当てはめて良いのかどうかも議論が必要でしょう。顧客が圧倒的な強者になってしまうと、利用者や家族による理不尽な「カスタマーハラスメント」にもつながりかねません。
パートナーシップで築く「利用者本位」の介護
生身の人間の身体や生活を扱う介護サービスにおいては、「これが絶対」という方法があるわけではありません。当の利用者でさえ、自分にとってより良いサービスはどのようなものなのか、わかっているわけではないはずです。
それならば、サービス提供者側と利用者側が双方向のコミュニケーションをとりながら、「本当に必要なサービスは何か」、「どうしたら望む暮らしに近づけるのか」をともに考えていくプロセスが重要になるのではないでしょうか。
どちらかが上でも下でもない、対等なパートナーシップを築いてこそ、真の「利用者本位」の介護の実現につながるのではないか、そんなふうにも考えられます。
介護労働の特性を理解した上で、専門職として求められる価値観や姿勢について、職場で議論を重ねながらメンバーに内在化していくことが求められます。