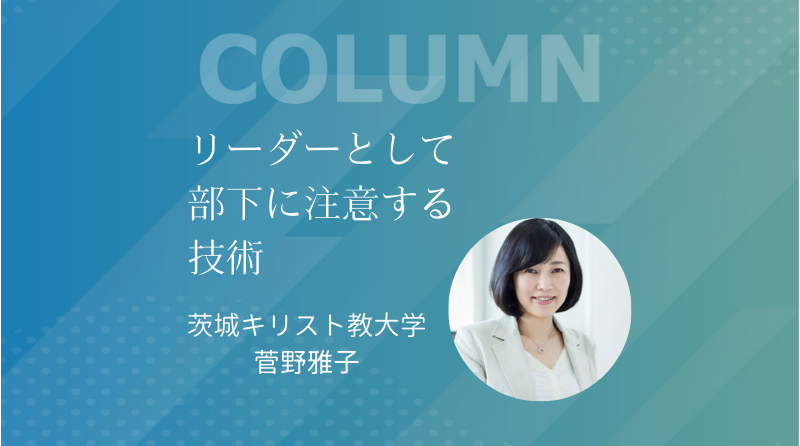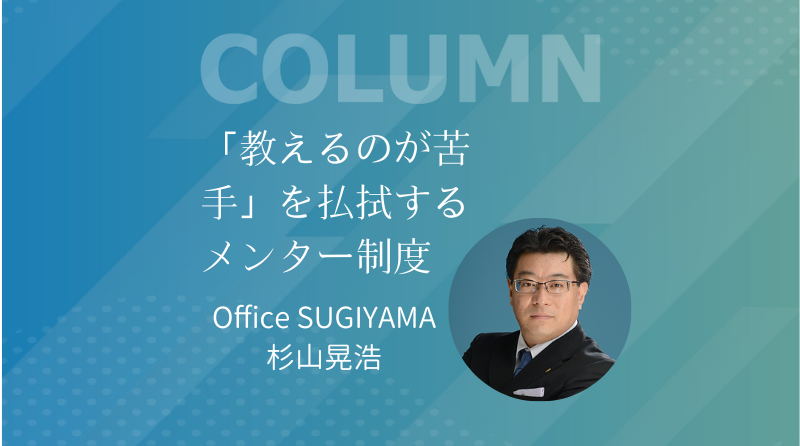前回までは介護労働実態調査(介護労働安定センター2021年公表)のデータをもとに、介護事業所の人材問題について業界の全体的な傾向と対策を検討してきました。
このシリーズでは、レンズを虫の目に切り替えて、現場のリーダーや管理者からよく聞かれる悩みを題材に、介護現場に起こりやすい人材問題とその対処法について検討したいと思います。
第1回のテーマは、「辞められてしまうのが怖くてダメなことをダメと言えない」という、リーダーの悩みについて一緒に考えてみましょう。
せっかく採用した人材を何とか引き留めたい…3年未満の離職は約6割
以前の回でも触れましたように、介護職員の離職率は、長期的な推移としては低下傾向にあります。しかしながら、離職者のうち1年未満に辞めてしまう人が35.6%、1年以上3年未満に辞めてしまう人は24.8%、合わせると約6割が3年未満に離職しており、早期離職は引き続きの課題と言えます。
やはりせっかく採用した人材が早期に辞めてしまう損失は大きいと言わざるを得ません。介護職は「引く手あまた」なので辞めても他で就職先を探しやすいという労働需給の問題は大きいと言えるでしょう。
以下の事例は、特養フロアリーダーAさんの悩みです。あなたがAさんの上司、またはスーパーバイザーという立場だとすると、どのようにAさんにアドバイスしますか?
(事例は、筆者が見聞きした実話を題材にしたフィクションです)
フロアリーダーAさんの悩み「辞められてしまうのが怖くて注意できない」
Aさん: 「介護の求人は多数あるので、職員が“いつ辞めてもいいんだよ”と、そう思いながら働いているんじゃないかなと、つい思ってしまいます。厳しいことを言って、“だったら辞めます”と言われてしまうのが一番怖いですね。ダメなこともダメと言いにくくて、指導の仕方もなかなか難しいなと感じています」
Aさんが上記のように考えるようになったのは、過去に自分の言動が職員の離職につながったことがあったからのようでした。
Aさん:「以前、入職2年目くらいの職員が、私が注意したことがきっかけで辞めてしまったことがありました。立とうとした利用者さんに対して、その職員が“ちょっと座ってて!”ときつい言い方をしていたことがあったんです。それで、“ちょっとさっきの言い方は違うでしょう”というように軽く注意したのですが、その後、“もう私辞めます!”ということになってしまったのです。そのことがあって以来、部下になかなか注意ができなくなってしまいました」
このようなAさんの悩みに、どう対応したらよいでしょう。
まずは、部下の言い分を聴く…ネガティブフィードバックのステップ
人間は、やはり自分の言動が批判されることには、大なり小なりストレスを感じるものです。若い世代は叱られることに慣れていないし、年配の方は人生経験に基づく信念やプライドが強かったりするので、どの世代も特有の「承認欲求」を持っていて、それに対して「気遣い」や「配慮」が必要な時代と言って良いでしょう。
「ちょっと座ってて!」ときつく言ってしまった職員にも、その職員なりの言い分や事情があるはずです。忙しくて、ついイライラした口調で言ってしまったとか、以前転倒させてしまった経験から転倒を恐れてついキツイ口調になってしまったとか、その時、その人なりの事情です。
2年目くらいだと、業務に慣れてきた頃ではあるけれど、逆にその“慣れ”が怖い時期でもあります。専門職としての意識や行動もまだ十分に備わっているといえる段階ではないとも言えます。
今回のようなネガティブフィードバックをするときは、まずは十分に本人の話を聴くような場面設定をすると良いでしょう。相手の話を聴き、共感できるところはそれを伝え、認めるところは認め、労うところは労い、相手が「聞く耳」を持ったところで、注意すべき点は注意するというようなステップをとれば、本人も注意されたことを受け止められるのではないでしょうか。
「時にはガツンと言ってほしい」という心理
逆の立場になってちょっと考えてみてください。不適切なことであっても注意もせず、ただ優しいだけのリーダーに、みんなついていきたいと思うでしょうか。
ダメなことをダメと言えないリーダーや管理者は、その場は丸く収まっても、中長期的には信頼を得ることはできないでしょう。
経験の浅い介護職員は、まだまだ技能もプロ意識も十分に備わっておらず、「これでいいのだろうか」という不安や迷いの中、手探りで介護の仕事をしている状況であることも少なくありません。
そのような中、ダメなことはダメと言ってくれる、時にはガツンと言ってくれるようなリーダーが実は求められていたりするのです。「成長したい」、「良い介護をしたい」と思っている人ほど、優しさだけではなく厳しさを備えたリーダーを望んでいるのです。
もちろんそこには、以下に示すように信頼関係のベースが必要です。
ネガティブフィードバックが受け入れられる信頼関係の構築
昨今は業界を問わず、「パワハラと言われるのが怖くて、部下に厳しく指導できなくなってしまった」という管理職の悩みがよく聞かれますが、Aさんの事例はそれと共通するところもありそうです。
「ちょっとそれ違うでしょう」
この一言が、部下に受け入れられるかどうか。それは、日頃からの信頼関係によるとも言えるでしょう。
先述のように、本人の言い分を十分に聴くような場面設定ができず、上司が咄嗟に注意したとしても、日頃から部下とコミュニケーションをとり、話を聴き、頑張っていることを労い、褒め、期待を示すということができていたら、部下は「愛あるアドバイス」として受け入れることができるはずです。
改めて、日頃のコミュニケーションの上に築かれる信頼関係を大切にする重要性を考えさせられます。
相互にフィードバックできるプロ集団を目指して
そして、もう1つ考えたいのは、「注意するのは上司だけなのか」ということです。
自律性が高いプロフェッショナル集団であるならば、プロフェッショナル同士の相互フィードバックによる質の維持・向上が期待されます。
法人の理念やケア方針をしっかり共有して、随時、相互にフィードバックし合えるような職場風土作りができていれば、Aさんのように一人思い悩むことも少なくなることでしょう。そんな職場作りが実現するような組織的支援が期待されるところです。