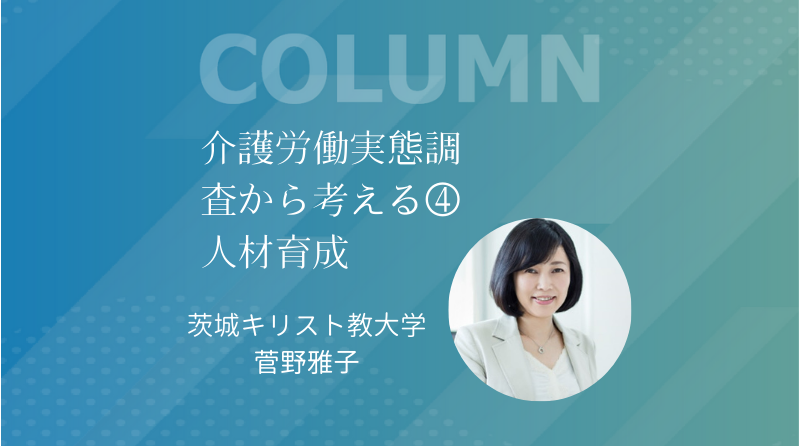1. 事業所の人材育成の充実度は人材定着に関連する
このシリーズでは、「令和2年度介護労働実態調査」(公益財団法人介護労働安定センター2021年8月23日公表)の結果を参照しながら、介護の人材問題について考えてきました。今回は最終回として、人材育成施策について検討します。
*参考:介護労働安定センターウェブサイト
【表1】は、介護事業所の人材育成の充実度(同業他社と比べた充実度を尋ねた質問)を定着率(事業所管理者の実感としての定着率)別にクロス集計したものです。

これを見ると、「定着率は低くない」とする事業所では人材育成の充実度が高く、「定着率が低く困っている」、「定着率は低いが困っていない」とする事業所は充実度が低いという結果となっています。つまり、人材育成施策が充実している事業所ほど、人材の定着率は良いと言えそうです。
2. 定着率が良い事業所では、外部研修への参加促進の割合が高い
次に介護事業所が取り組む具体的な人材育成施策について確認します。【表2】は、定着率別にみたクロス集計結果です。

定着率の良し悪しと施策の関連をわかりやすくするために、「定着率が低くない」とする事業所に対して、「全体」との差異(差異①)、「定着率が低く困っている」事業所との差異(差異②)、「定着率は低いが困っていない」事業所との差異(差異③)を算出してみました。
全体の傾向と比べてもあまり差異がありませんが、定着率の低いグループと高いグループ間の比較でみると、「自治体や業界団体が主催する教育・研修に参加させている」や「地域の同業他社と協力、ノウハウを共有して育成に取り組んでいる」に若干の差異が確認できます。
外部研修への積極的な参加促進や、地域連携による人材育成への取組みが定着率の差異化につながっているということは、法人・事業所という枠を超えた「越境」や「連携」、「共同化」などが、人材の定着・育成において重要な意味を持つ可能性が考えられます。
3. 越境的学習の可能性と意義を考える
組織の境界を越えて学ぶ「越境的学習」は近年注目されており、その効果は、普段とは異なる他者との交流による刺激、発想の転換、視野の広がり、リフレッシュ効果など、さまざまに指摘されています(石山,2018; 松本,2019など)。
以前、筆者が介護現場のリーダーシップ研究のために、リーダー・マネジャー層にインタビュー調査をした際も、外部研修への参加経験、外部の各種連絡会・協議会等への参加経験、他事業所との交流経験などが、自らの視野の広がりや業務改善などにつながっているというお話が多く聞かれました。
現場で日常業務のルーティンに追われ多忙な中、どうしても物の見方・考え方が固定的・閉鎖的になりがちです。一歩外に出て異なる考え方ややり方に触れるような機会は、自らを一段高い視座で振り返り、新たな気づきを得ることにつながると言えるのではないでしょうか。
4. オンライン化は学習の制約を乗り越えるチャンス?!
そうは言っても、ただでさえ多忙な中、現場から人を送り出すことはそう簡単ではないでしょう。
長引くコロナ禍の影響で、人が集まることが難しくなっている昨今、研修やセミナーの開催、あるいは学びや仲間づくりのためのネットワークの形成が、オンラインを通じて行われることが多くなってきました。
これは、現場を離れることが難しい介護事業所の職員にとって、「学びの機会」という点でみれば、時間的・地理的制約が小さくなり、参加の可能性が広がっていると考えることもできます。
これまでは時間的・地理的に考えて参加が難しかった研修やセミナー、オンラインコミュニティへの参加なども含めて、積極的に活用する意義は大きいと言えるのではないでしょうか。
内発的モチベーション理論によれば、人間は生来、有能感を感じたい、自律的でありたい、他者と良い関係性を築きたいという欲求を持っており、それが満たされることによって、より高いパフォーマンスを発揮することができるとされています。
人材育成により、有能感を高め自律的に行動できるようになれば、内発的に動機づけられ、介護の仕事の「やりがい」を感じられるようになります。そんな状態が実現できれば、ケアの量・質ともに高まっていくのではないでしょうか。筆者は、「魅力ある職場環境作りの中核は人材育成にある」と言っても過言ではないと考えます。
<参考文献>
・介護労働安定センター(2021)『令和2年度介護労働実態調査』(事業所調査)
・厚生労働省(2021)『令和2年度能力開発基本調』」
・ 石山恒貴(2018)『越境的学習のメカニズム: 実践共同体を往還しキャリア構築するナレッジ・ブローカーの実像』福村出版
・松本雄一(2019)『実践共同体の学習』白桃書房