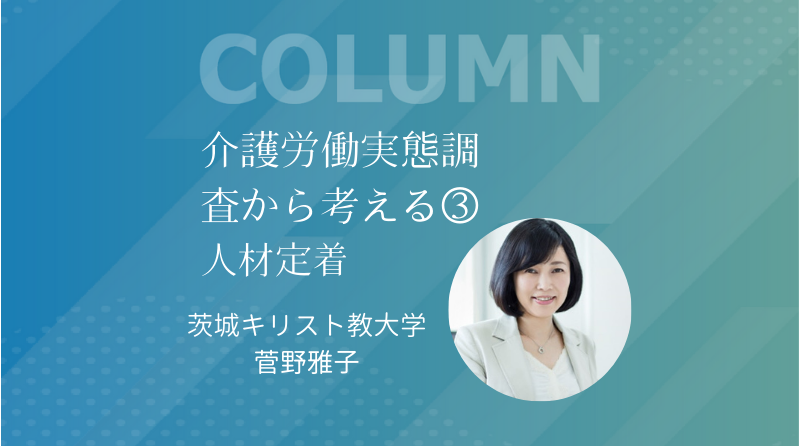1. 介護は人が辞めない職場になってきた
このシリーズでは、引き続き「令和2年度介護労働実態調査」(公益財団法人介護労働安定センター2021年8月23日公表)の結果を参照しながら、介護の人材問題について考えます。今回は、効果的な人材の定着促進策について検討していきましょう。
*参考:介護労働安定センターウェブサイト
第1回のコラムでもお伝えしましたとおり、介護事業所の離職率は年々改善傾向にあり、介護職員(訪問介護員とそのほかの介護職員の2職種計)の平均は14.9%で、全産業平均(14.2%)(厚生労働省,2021『令和2年雇用動向調査』)と同程度の水準になっています。
介護労働実態調査開始以来、離職率が最も高かった平成19年度の21.6%と比べても、介護業界は人が辞めない職場になってきたと言えるでしょう。
一方で、離職率の高い事業所と低い事業所の二極化傾向がかねてから指摘されていますが、その傾向は変わっていません。離職率が高い事業所と低い事業所では、取り組みにどのような違いがあるのでしょうか。
2. 全体の傾向としては、働きやすい職場作りに取り組む事業所が多い
まず介護事業所が取り組む定着促進策について確認します。表1 は、サービス系列別にみた調査結果です。実施している定着促進策の割合を示しています。

サービス系列によって、順位や割合の違いは若干ありますが、「残業を少なくする、有給休暇を取りやすくする等の労働条件の改善に取り組んでいる」や「本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に取り組んでいる」など、時間外労働削減や柔軟な働き方を可能にする体制など、働きやすさに力を入れていることがわかります。
また、「賃金水準を向上させている」、「能力や仕事ぶりを評価し、賃金などの処遇に反映している」、「キャリアに応じた給与体系を整備している」、「有期雇用から無期雇用への転換の機会を設けている」、「能力開発を充実させている」など、キャリアパス関連施策にも取り組む割合が高いようです。
さらに「職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている」もサービス系列共通に割合が高くなっており、仕事面での円滑な情報共有や良好な関係性構築に配慮した職場づくりを行っていることがうかがわれます。
3. 定着率が良い事業所では、仕事上のコミュニケーションの円滑化に力を入れている
それでは、人材の定着率が良い事業所とそうではない事業所の違いはどこにあるのでしょうか。その点について、検討していきましょう。
図1は、事業所の定着率(回答した事業所管理者の実感としての定着率)別に見て、「定着率は低くない」という事業所と、それ以外の事業所の取り組みを比較したものです。取り組み割合に差異のある項目のみピックアップしています。差異が大きいということは、その違いが定着率の良し悪しに関連している可能性が高いということになります。

差異が最も大きいのは、「仕事上のコミュニケーションの円滑化」でした。その他、「業務改善や効率化」、「健康対策や健康管理」、「経営方針やケア方針の共有」、「福利厚生の充実」なども、若干ではありますが、「定着率は低くない」事業所の取り組み割合が高くなっています。これらも定着率の良さに関連している可能性があります。
その一方で、表1で取り組み割合が高かった、時間外労働削減や柔軟な働き方、キャリアパスに関連する項目は、ほとんど差異がありませんでした。
この結果より、人材定着に対して、労働条件の改善やキャリアパス関連施策は多くの事業所が取り組んでいるため違いはあまりなく、仕事上のコミュニケーションの円滑化が定着率の違いを生む最も重要なカギになることが考えられます。
4. キャリアパス導入は定着促進に効果があるとは言い切れない?!
ここでもう1つ、筆者が昨年度(2020年8月公表「令和元年度介護労働実態調査(事業所調査)」)のデータを用いて行った分析をご紹介します。
二項ロジスティック回帰分析という手法を用いて、サービス系列別に定着促進策(令和2年度と同じ内容)と定着率の関係の分析を試みました。その結果が表2です。
表中の「β(ベータ)」列のマイナスの符合の有無は、正の影響か負の影響かを示しており、*(アスタリスク)の数が影響の強さを示しています。
これを見ますと、人材定着に正の影響を及ぼしているのは、サービス系列によって多少違いはありますが、「仕事上のコミュニケーションの円滑化」、「福利厚生を充実させ、職場内の交流を深めている」などであることが確認できます。

マイナスの符合がついている項目に網掛けがしてあります。訪問・通所の在宅系では「能力や仕事ぶりを評価し、賃金などの処遇に反映している」、入所系では「職員の仕事内容と必要な能力等を明示している」、居住系では「賃金水準を向上させている」といった、キャリアパス関連の施策が負の影響を及ぼしていることが見てとれます。
この結果の解釈として、キャリアパス関連施策の制度や運用プロセスに何らかの齟齬が生じている可能性や、能力や役割に基づく新たな人事方針・制度についていけない人が去っていくなど、さまざま考えられます。いずれにしても、この結果だけで結論づけることはできません。引き続き介護業界のキャリアパスの制度設計や運用等を注視していく必要があると考えています。
人材定着のカギは賃金以外の魅力づくり
今回は介護労働実態調査のデータから、介護事業所が行う定着促進策の中で、とりわけ「仕事に関するコミュニケーションの円滑化」が、人材定着の良し悪しを分けている取り組みである可能性を確認しました。
介護事業所は人と人の良好な関係性から成り立っているといっても過言ではありません。仕事上の良好なコミュニケーションや関係性作りを積極的に進めている事業所に、働く人々は魅力を感じていると言えるのではないでしょうか。
賃金等の処遇改善はもちろん重要テーマですが、賃金以外の魅力づくり施策の重要性がうかがわれます。
参考文献
・ 介護労働安定センター(2021)『令和2年度介護労働実態調査』(事業所調査)
・ 厚生労働省(2021)『令和2年雇用動向調査』
・ 菅野雅子(2021)「介護事業所の定着促進策に関する一考察-キャリアパス制度導入の影響に着目して-」『ビジネスブレークスルーレビュー』