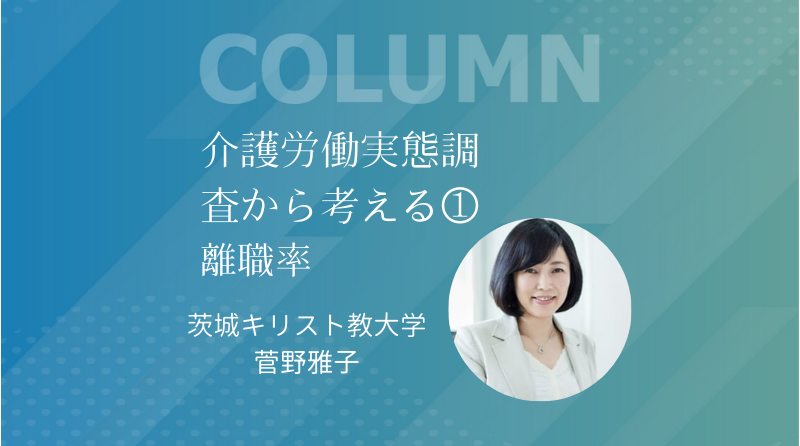介護業界の人材マネジメントに関する研究をしている菅野雅子と申します。本コラムでは、介護労働実態調査のデータ等を参照しながら、介護人材の確保・定着・育成等のテーマについて検討していきたいと思います。
離職率は改善傾向で平均は14.9%。産業全体平均よりも低い結果に
2021年8月23日に介護労働安定センターから「令和2年度介護労働実態調査」の結果が公表されました(有効回答数9,244事業所・回収率52.7%)。
*参考:介護労働安定センターウェブサイト(「介護労働実態調査」について)
この調査で毎年話題に上るのが「離職率」です。令和2年度調査では、2職種計(訪問介護員、介護職員)の離職率は14.9%でした。離職率は低下傾向にあり、今回は平成14年度の調査開始以来、最も低い離職率となりました。
他産業に目を向けてみますと、厚生労働省「令和元年雇用動向調査」によれば、全産業平均の離職率は15.6%(前年度14.6%)と少し上がっています。
また非正規労働の割合が多い生活関連サービス業・娯楽業は20.5%(前年度23.9%)、宿泊業・飲食サービス業は33.6%(前年度26.9%)と高い数値となっており、介護サービスの離職率の低さがよくわかります【図1】。

介護業界全体として、労働環境の整備が進み人材が定着していることが推察されます。とはいえ、全体の平均値だけ見て「上がった・下がった」と言ってもあまり意味がありません。次に、もう少し細分化してデータを見ていきたいと思います。
離職率の数値と現場の実感の間には乖離も
先に示した2職種計の離職率を、主な事業所属性と職種・雇用形態別に見ていきましょう【表1】

これを見ると、サービス系列では居住系(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護など)の有期雇用、介護事業開始後経過年数別では年数が浅い事業所の離職率が相対的に高いことが見てとれます。また、事業所規模別の状況では、規模が小さい事業所ほど離職率が高い傾向が読み取れます。
しかし、これを見て「事業所規模が小さいほど人は辞めていく」と考えるのは早計かもしれません。規模が小さいほど分母が小さいわけですから、1人辞めた時のインパクトが強くなり、振り幅が大きくなるからです。
同調査のうち、「事業所における人材の定着実感」を聞いた質問では、事業所規模が大きいほど「定着率が低く困っている」割合が高く、事業所規模が小さいほど「定着率は低くない」の割合が高くなっています【表2】。

離職率の数値と定着実感、どちらのデータがより現場の感覚に近いのでしょうか。筆者がある介護事業所の管理者の方にお聞きしたところ、「離職率の数値よりも、辞めてほしくない人が辞めてしまうかどうかの方が大事。辞めても仕方ない人が辞めても、定着率が悪いとは感じない」というご意見をいただきました。
皆様の事業所ではいかがでしょうか。
事業開始3年未満で高い離職率、新規開設事業所の重点支援が重要
さて、もう一度【表1】に戻り、今度は介護事業所開始後経過年数に着目してみます。すると、開始後3年未満の事業所は軒なみ離職率が20%を超えて高い水準にあることがわかります。
同じ法人であっても、新規に開設した事業所は、オペレーションが安定稼働するまではある程度時間がかかります。多くのスタッフは新規採用され「はじめまして」の人々が集まります。理念やケア方針を共有し、お互いの得手・不得手を理解し、ケアチームがうまく回るようになるまで、一定の時間がかかるでしょう。そのような「バタバタした状態」の中で、辞めていく職員も多くなるのは、納得できます。
この点を踏まえると、新規開設の事業所支援は、離職率改善の1つの重要な施策になると言えるのではないでしょうか。具体的には、法人本部や安定稼働している他事業所からのマンパワー支援、スキルアップ支援、情報支援、相談対応などを厚くすることが考えられます。要するに、放っておかないということです。
「辞めるべくして辞めていく人」を採用の入り口で減らすアプローチ
離職率を巡る切り口として、「早期離職」の問題にも触れておきましょう。今回の調査では例年の結果と傾向は変わらず、2職種計の離職者のうち実に6割強が3年未満に離職しています【表3】。

介護事業の場合、新人といっても新規学卒者から高齢者まであらゆる年齢階層の方が多数入職します。この特徴に着目して、早期離職について、「辞めるべくして辞めていく人の問題」と、「辞めてほしくない人が早期に辞めてしまう問題」の2つのパターンについて考えます。
前者は、他産業でリストラされた人など、どう考えても適性のない人材が入ってきて、結局介護の仕事が合わずに辞めていくというケースです。現在の労働需給状況を考えると、一定数こうしたケースがあるのは仕方ないとも言えるでしょう。
しかしながら、採用・教育コストや、現場の士気の低下といった悪影響を考えると、できれば入口の段階で抑制したいものです。このようなミスマッチを回避するために、採用段階で「やりがい」とか「感謝・感動」などポジティブな面ばかりを強調するのではなく、仕事の厳しい側面も誠実に知らせておくという方法も一計です。これはアメリカの産業心理学者ジョン・ワナウスにより提唱された理論で、RJP(Realistic job preview:現実的な仕事情報の事前開示)と言います(Wanous,1973)。
RJPにより入職を断念するようであれば、その人は適性がなかったと考えることができるのではないでしょうか。また入職に至ったとしても、入職後のギャップが小さくなり、ミスマッチの緩和と人材定着に効果があることがこれまでの研究で確認されています。
辞めてほしくない人が早期に辞めてしまう問題と改善へのアプローチ
もう一方の「辞めてほしくない人が早期に辞めてしまう問題」とは、適性がありそうな人なのに、介護の仕事の醍醐味や面白さがわかる前に辞めていってしまうというケースです。
介護の仕事は、机上の知識だけでは現場で通用せず、多様な利用者に向き合う経験の量・質から得られる知が何より重要であると、研究の世界でも以前から指摘されています(西川,2004a,b: 佐藤・大木・堀田,2006など)。
そのため、とりわけ介護の仕事に就いた最初の段階では、経験が乏しいので状況対応力や問題解決力などが伴わず、一生懸命やっているのに利用者・家族に怒られたり、認知症の方に拒否されたりといったことも多々あるのではないでしょうか。
そんな時に、心折れて辞めてしまうというケースは何とか未然に防ぎたいものです。仕事の手応えを得ることができるよう、できないことをできないままで終わらせず、粘り強く技術指導をしたり、落ち込んだ気持ちを前向きに切り替えられるよう、ソーシャルサポート(声かけや精神的サポートなど)を厚くしたりするなど、満足や安心感を与えることが、より重要になると言えるでしょう。
<参考文献>
・介護労働安定センター(2021)『令和2年介護労働実態調査』(事業所調査).
・厚生労働省(2020)『令和元年雇用動向調査』.
・ 佐藤博樹・大木栄一・堀田聰子(2006)『ヘルパーの能力開発と雇用管理-職場定着と能力発揮に向けて-』頸草書房
・ 西川真規子(2004a)「ヘルパーの技能の内実と向上: アンケート調査に基づく実証分析 その1」、『経営志林』41(1), 35-53.
・西川真規子(2004b)「ヘルパーの技能の内実と向上: アンケート調査に基づく実証分析 その 2」、『経営志林』41(2), 53-70
・Wanous, J. P. (1973). Effects of a realistic job preview on job acceptance, job attitudes, and job survival. Journal of applied psychology, 58(3), 327-332.