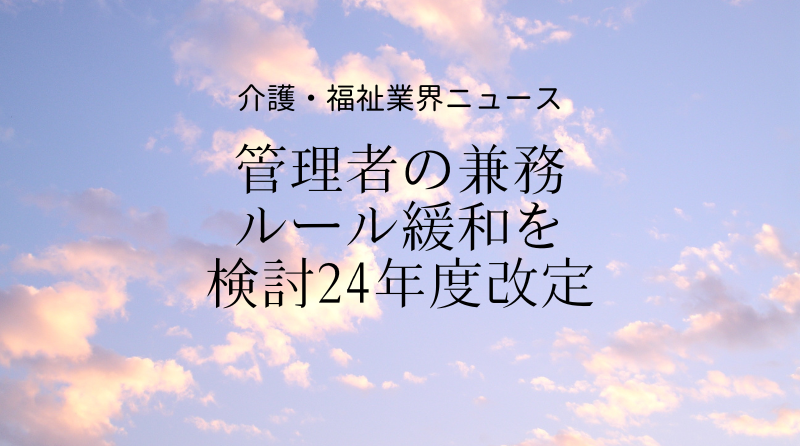社会保障審議会・介護給付費分科会では、2024年度の介護報酬と診療報酬の同時改定に向け、論点の洗い出しを進めてきました。
このうち、限られた人員でもサービス提供を継続するために、業務効率化の促進と並行して検討されているのが、管理者の兼務など柔軟な働き方をどこまで認めるかです。
規制緩和の議論と並行して自治体によって異なるルールの是正も進められることになりそうです。
人員配置基準に関わる見直しとしてはこのほかに、職員のテレワークを認めるかどうかの方針が3月末までに示されることも、注目ポイントです。
人員配置等基準の緩和は2024年度改定でも対応される見通し
サービス種別の枠を越え、24年度改定での対応が必要とされているテーマに「介護人材の確保と生産性向上」があります。このテーマを掘り下げるため、社保審・介護給付費分科会では、以下の切り口で課題の整理や検討が進められているところです。
【”介護人材の確保と介護現場の生産性の向上”(第223回の議論のテーマ)】
1.介護人材の処遇改善等
2.人員配置基準等
3.介護現場の生産性向上の推進/経営の協働化・大規模化
4.外国人介護人材に係る人員配置基準上の取り扱いについて
このうち、人員基準配置基準等については、2021年度改定でも若干の対応が行われました。介護を理由に時短勤務する職員を「常勤」として換算する基準が緩和されるなどの変更がなされています(全サービス対象、通知改正事項)。
24年度改定に向けては、管理者に関する事項が俎上に上っており、その切り口としては
- 常勤専従要件の緩和
- ローカルルールの実態把握の促進
が示されました。
また、管理者以外の職員について
- テレワークを認めるかどうか
も議題にあがっています。
管理者についてどの程度まで兼務を認めるか
管理者に関する要件を見直す上で、初めに挙げられているのが、”原則常勤”とされている運営基準上の規定についてです。
すでに一部のサービスではすでに、①同一事業所での兼務②ほかの事業所の管理者/現場職員等の兼務―が認められており、例えば、訪問介護事業所の管理者はサービス提供責任者や、訪問介護員として働くほか、併設事業所の管理者業務などの兼務が、”指定訪問介護の提供に支障がない場合”に認められています。


(【画像】管理者の兼務に関する規定(下は第223回社会保障審議会介護給付費分科会資料2より引用))
こうした省令上の規定において、現状では兼務可能な事業所等の明確な種別や数は定められていません。
そこで可能な範囲の明確化や緩和などが今後の検討事項として示されています。
また、小規模多機能型居宅介護事業所などの管理者は、兼業可能な範囲が、併設されている地域密着型介護老人福祉施設や認知症GH等に限定されているため、これを通所介護事業所等にも広げて欲しいという要望があり、これも検討の範囲に含まれています。
管理者の兼務に関するローカルルールの実態把握
次に、管理者を初めとした人員配置基準における規定のうち、兼務可能な範囲のローカルルールについてです。
先述の通り、人員配置基準は厚生労働省令で定められていますが、この省令上、「管理上支障がない」「利用者の処遇に支障がない」などの表現で示されている部分について、その解釈は自治体に定められています。
管理者の兼務を可能とする規定の「同一敷地内」の範囲がその一例で、この範囲を隣接あるいは近接した事業所まで含める自治体と、文字通り同一敷地内にある事業所のみ認めている自治体に分かれています。
また、管理者の兼務について上限数を課している自治体もあります。



(【画像】人員配置基準等の自治体ごとの解釈・運用の実態(第223回社会保障審議会介護給付費分科会資料2より))
このローカルルールについては、厚労省でも全容が把握できているわけではありません。
そこで、今回同省は、人員配置基準に関する運用の実態把握と公表を進め、ローカルルールの是正を推進しようとしています。
テレワーク等の扱い:管理者以外の職種は2024年3月までに結論
最後に、職員のテレワークについてです。
既に、管理者については「管理者は、当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である」などと厚労省が考え方を示しています(9月5日事務連絡)。
今回焦点になっているのは、現場でサービス提供に従事する職員や有資格者らの扱いです。
検討材料として厚労省は、職員らを対象としたテレワークに対する意識調査の結果などを示しています。
介護給付費分科会委員の意見:テレワークの推進については疑問符も
厚労省の提案に対し、ローカルルールの把握・公表について特に反対意見は出ていません。
ただし、全国知事会から大石賢吾長崎県知事の代理で出席した参考人は、「極端なローカルルールは改善しつつも、自治体の裁量は一定担保される必要がある」と主張しています。
管理者の兼務の範囲を拡大することについては、事業者や保険者を代表する委員らが賛同の意を示した一方、労連の小林司委員は「兼務が常態化すれば、休憩時間や有給休暇の取得がしづらくなり、離職の理由にもなりかねない。介護人材の処遇改善にも反することになる」と慎重な検討を求めています。
また、稲葉雅之委員(民間介護事業推進委員会・代表委員)は、緩和に向けた検討を進めることについては賛同したものの、「今日的な管理者の役割と業務内容を改めて整理する必要がある」と指摘しました。
テレワークに関してはこの日、対象職員の多くが業務の性質上導入を難しいと考えていることがわかるデータが示されています。


江澤和彦委員(日本医師会常任理事)がこれを「現場の率直な声」とした上で「管理者業務のみに従事している職員は少ないということも留意するべき」と指摘しています。