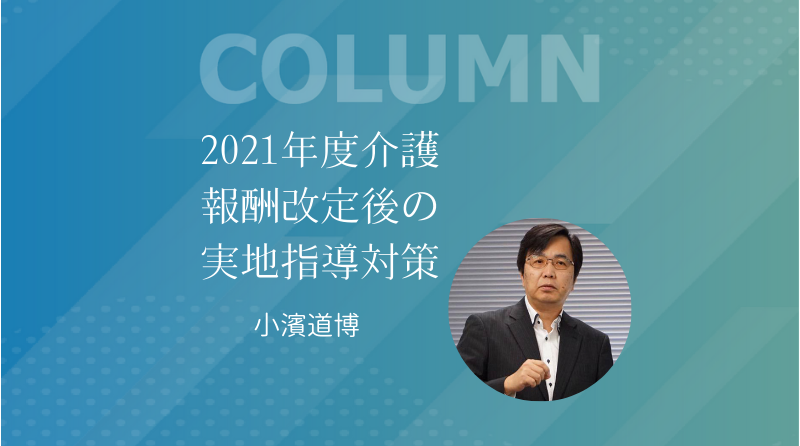※「実地指導」は2022年4月から「運営指導」に名称変更されました。
今年度の実地指導がコロナ禍の中、全国で本格的に再開されている。関連通知や介護報酬改定の対応を踏まえつつ、対策にポイントを紹介するので、各事業所における対応の参考にしてほしい。
1.処遇改善加算関連の算定要件が大きく変更
2020年度以降は、コロナ禍特例措置が採られたことなどもあって、法令の解釈について複雑さが更に増している。コロナ禍特例措置を使っている場合は、その根拠となる記録が特に重要となるために、再チェックをしておくべきだ。
特に、職員が発熱や学校の休校などのコロナ禍の影響で休んだために職員の配置基準を満たせない日がある場合でも、人員基準減算を適用しない旨の特例があるが、その理由や状況を日々の業務日誌などで確認出来ないと特例は適用されない。
また、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の算定要件が毎年のように変わっている。
特に2020年度は比較対象年度が、「最初に加算を算定した前の年度」から、「算定の前年度」となり、さらに「前年の1月から12月」と「当年の4月から翌年3月」を比較するという変則的な算定要件となった。
さらには、最初に加算を算定した前年以降の独自の改善額を、別枠で計算して基準年度から差し引く処理を行うのであるが、この辺りの明細の作成で多くの時間を費やす。いずれにしても、従来とは算定要件が大きく異なるため、今一度の再確認が必要だ。
(※編集部注:介護職員等特定処遇改善計画書の書き方と様式無料DL【21年度改正対応】(関連記事) )
2.半日型の実地指導が中心となっている
厚生労働省からの通知「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針」が2019年5月に発出されている。
これは、実地指導を効率化して年間の指導件数を増やすことが主たる目的である。
従来から厚労省は、介護事業所を所轄する自治体に対して、少なくても指定有効期間である6年以内に一度は実地指導を行い、その事業所に問題ないことを確認してから指定の更新手続を進めるように通知を出していた。しかし、介護事業者の急増によって物理的に困難な状況が続いているのが現実だ。
19年5月の通知では、実地指導を効率的に実施することで、従来は一日作業であった現地指導を半日に短縮して、一日に複数件の実地指導を行うように求めた。それによって、指定有効期間である6年の内に一度は実地指導を行うことを実現することを目的としている。
今後は、自治体の職員が標準確認項目での効率的な指導に慣れていくと共に、確実に半日型の実地指導が増加していくであろう。
19年に出された通知をその年度内に実施する自治体は少ない。多くの自治体は、翌年2020年度からの実施を予定していた。しかし、この年にコロナ禍が発生した。その影響で、同年の2月以降の実地指導の大部分は延期もしくは中止となった。非常事態宣言が解除された6月以降、コロナ禍で出来なかった件数分を含めて、実地指導の実績件数を増やすため、全国的に一気に半日型の指導は拡大したと言える。
ただし、一日型の実地指導が無くなったわけでは無い。事業規模の大きい介護施設、前回の実地指導で問題が多かった介護事業所、トラブル、クレームの多い事業所などは、従来通りに一日型の実地指導が行われる。
3.「標準確認項目」及び「標準確認文書」の確認が必須
先に触れた「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針」の通知内容を確認しよう。
現在の実地指導は、通知の中で示された別紙「標準確認項目」及び「標準確認文書」に基づいて実施されている。
その対象は、訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所、認知症対応型共同生活介護、介護老人保健施設、訪問看護の7種類のサービスであるが、その他のサービスについても、この7種類のサービスを参考にして実地指導に活かすとされた。ここに記載された確認項目と文書以外は、特段の事情が無い限り実地指導では見なくても良いとされている。
この指針に沿って実地指導を行うことで、一件当たりの所要時間を短縮し、一日に複数件の実施指導を行うことが想定される。
実地指導の頻度は、事業所の指定有効期間である6年間に最低でも 1 回以上実施することが基本となる。それでも実現できない場合は、過去の実地指導で特に問題がない事業所は集団指導のみとするなどを検討するとされた。同一所在地や近隣に所在する事業所への実地指導は、同日または連続した日程で行う。
現地での提供記録等の確認は原則として利用者 3 名以内とし、居宅介護支援については原則として介護支援専門員1人あたり利用者 1 名〜2 名の記録等を確認する。
実地指導において確認する書類は、原則として実地指導の前年度から直近の一年間とするとされた。
このプロセスを実施することで、ある程度、事業所に存在する問題は把握できるという事だ。問題が発覚した場合は一日指導となり、悪質である可能性がある場合は監査に切り替わる。

*【表】「標準確認項目」及び「標準確認文書」の抜粋(「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針」より)
4.10月から一定基準を超えたケアプランの届け出等が義務化
10月より居宅介護支援居宅介護支援について、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みが導入された。
(※編集部注:新たなケアプラン検証、対象は支給限度額7割以上・訪問介護6割以上の事業所に、vol.1006「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)(関連記事))
厚生労働大臣が定める基準に該当する場合で、市町村からの求めがあった場合には、ケアプランの届出等を義務付けられる。厚生労働大臣が定める基準は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合を100 分の70とし、かつ、訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合を100 分の 60とした。 要は、区分支給限度基準額の7割以上を使い、かつ、サービス全体に占める訪問介護の割合が6割を超えた場合、そのケアプランを役所に提出を義務づけて、地域ケア会議などで検証すると言うことだ。
これは、ケアプランの一つでも該当したら対象になるわけでは無い。ひとつの居宅介護支援事業所が契約している利用者全員の区分支給限度基準額を合計し、合計額の7割以上の給付単位のケアプランを組み、かつその6割以上が訪問介護の場合、地域ケア会議などでの「ケアプラン点検」(介護給付等費用適正化事業)の対象として抽出されるということで、平均が7割を超えた場合である。
5.高齢者住宅併設の居宅介護支援事業所への指導の強化
同じく10月から、同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する利用者のケアプランについても、区分支給限度基準額の利用割合が高い利用者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、居宅介護支援事業者を事業所単位で、ケアプランを役所に提出を義務づけて、地域ケア会議などでのケアプラン点検の対象として抽出される。
そのとき、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行って、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図るとされた。
高齢者住宅に関しては、依然として囲い込み批判が強く、今後も実地指導においての強化の方向が明確だ。日頃からの充分な事前対策が求められる。