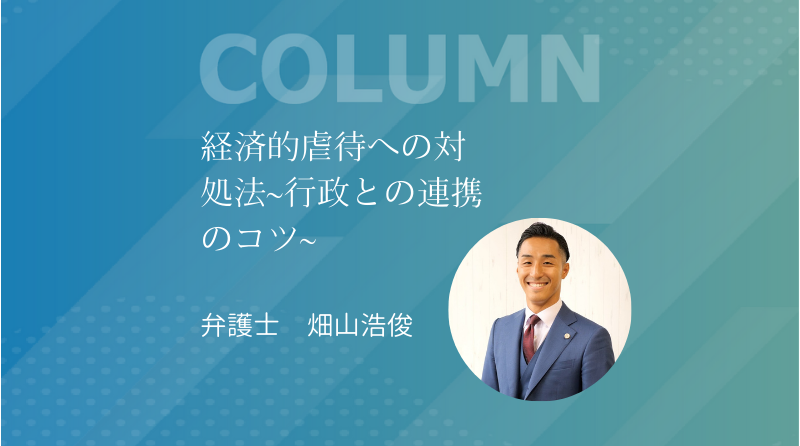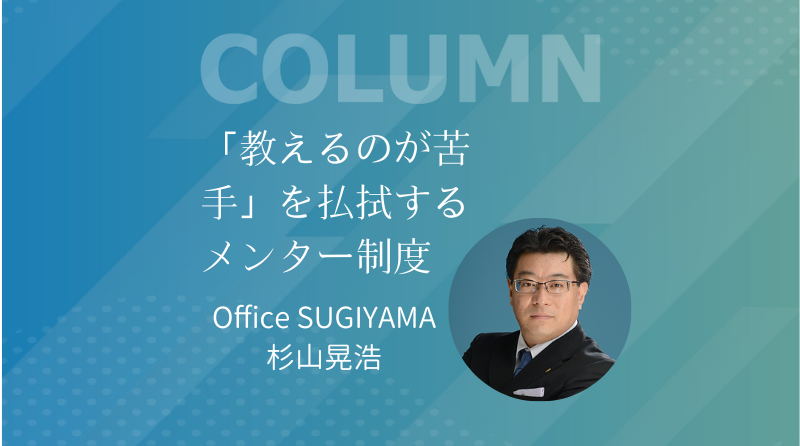※本稿では、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を「高齢者虐待防止法」と略称します。
1.考察する経済的虐待の具体例…家族が年金を使い込み介護施設の利用料を滞納したケース
以前の記事で紹介したとおり、本稿でも、次に示す利用者が経済的虐待を受けていたときのケースを元に解説します。
経済的虐待の解説、成年後見制度の市町村長申立の概説については、前回の記事を参考にして下さい。本稿では、経済的虐待の事案において、本人や親族が成年後見申立てをすることが期待できない場合、いかに速やかに成年後見制度の市町村長申立の手続を進めるのか、その際の行政連携の「コツ」について解説します。
<ケース>
ここはとある特別養護老人ホーム。
施設長は、利用料の滞納が続く利用者サトシさん(仮名)の件で頭を悩ませていた。
サトシさんは要介護5で、重度の認知症を患っており、意思疎通は困難な利用者だ。既に配偶者も亡くなっており、サトシさんの娘であるAがキーパーソンである。
Aはサトシさんの年金が入ってくる通帳を管理しており、どうやら自分たちの家族の生活費に年金を遣っているようだ。年金に余りが出た分だけを利用料の支払いに充てるため、利用料の滞納が徐々に増えている状況だ。
「このままでは、滞納が増える一方だ。何とかしないと。」と思った施設長は、Aを施設に呼び、どのようにして滞納を解消していくのかを話し合うことにした。
施設長:本日はお忙しいところお越し頂き、ありがとうございます。今日は、サトシさんの利用料の滞納額の件でお話があります。現時点でサトシさんの滞納額は、約35万円になっています。この滞納分はどのようにして支払って頂けますでしょうか。
A:そんなことを言われても、私たちも生活が大変なのよ。コロナの影響で仕事も減らされちゃって収入も少なくなったんだから。
施設長:大変な状況の中、このようなお話で恐れ入ります。ただ、サトシさんは、利用料を支払うのに十分足りる額の年金を受給しておられると思うのですが・・・。その年金から利用料をきちんとお支払頂きたいのです。
A:年金は入ってくるけど、私たちの生活費に充てると足りないのよ。あと、私の息子の塾代も高くて年金がいくらあっても足りない状況なの。福祉施設さんなんだから、ちょっとは融通を効いてくれてもいいじゃない。
施設長:年金を生活費や塾代に回すのはちょっと・・・。サトシさん本人が受給すべき年金ですから、施設の利用料に遣っていただかないと。
A:私たちだって大変なんだからちょっとは融通をきかせてよ。福祉施設なんだから弱者の味方でしょう?
施設長:・・・・・
2.「経済的虐待」の判断に役立つ情報提供を積極的に
本件においては、サトシさんの年金の管理主体をご家族から成年後見人に速やかに移行することが大切です。したがって、なるべく速やかに行政への市町村長申立てに駒を進めてもらうことが最重要課題となります。
その際に重要なことは、介護事業所として、「経済的虐待」の判断に役立つ情報を積極的に行政へ提供することです。
意外と見落とされがちなのですが、行政は通報を受けた内容を全て「虐待」と認定する訳ではありません。「虐待」と認定するまでに利用者本人からの聴き取り調査や、ご家族への訪問調査など、慎重に調査を重ねた上で証拠をなるべく多く収集し、虐待か否かを判断するのです。
その観点から、筆者が特に積極的に提供して頂きたいと考える情報・資料は以下の3つです(他にもたくさんありますが、スペースの関係上敢えて3つに絞ります)。
一つ目は、滞納状況が一目でわかる事実経過表です。
具体的には、時系列で事実関係を整理したメモを作成し、添付資料として末尾に利用料の請求書を編綴するイメージです。
この事実経過一覧表を行政担当者に交付することで、「介護事業所がこのような形できちんと毎月請求しているにもかかわらず、滞納が続いているのだな。」ということが行政担当者も一目瞭然になります。
「何を当たり前のことを」と思われた読者もいるかもしれません。
ただ、筆者が関わった事案の中には、介護事業所側の資料整理が杜撰で、どの月の利用料が滞納になっているのか、本当に請求書を出したのか、といった具体的な事実関係がよく分からない介護事業所も存在しました。
このような杜撰な状況では、行政担当者も「事実関係がよく分かりません。きちんと資料を整理の上、再度お越し下さい。」と対応せざるを得なくなります。
基本的なことですが、行政との連携の場面では、整理整頓された資料を持参することが鉄則です。
二つ目は、利用契約書です。
特に利用契約書に記載の契約の解除事由が大切です。
介護事業所によって内容は微妙に異なりますが、おおむね以下の解除事由が規定されているはずです。
利用者が、正当な理由なく事業所に支払うべき利用料の自己負担分を3ヶ月分以上滞納した場合には、事業所は利用者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、期間内に滞納額の全額の支払いがないときは、この契約を解除する旨の催告をすることができます。その上で、事業所が定めた期間内に利用者が滞納額の支払いをしなかったときは、文書をもってこの契約を解除することができます。
おそらく行政へ虐待通報をする段階では、滞納が数か月続いていることが多いと思います。一つ目の事実経過表を示すとともに利用契約書も合わせて情報提供することで、契約の解除事由に該当する状況になっていることを行政担当者へ伝えて下さい。
契約の解除とはすなわち利用者へのサービス提供の停止を意味します。
介護サービスが必要な利用者に対するサービス提供が停止すると、利用者本人は生きていけません。利用者へのサービス提供の停止は、すなわち、利用者本人の権利侵害に直結します。一つ目の事実経過表と共に利用契約書を提供することで、利用者本人の権利利益が害される蓋然性が高まっていることを行政担当者に伝えていきましょう。
三つ目は、金銭管理を行っているご家族との面談時の録音データです。
虐待通報を受けると、行政担当者は金銭管理をしているご家族のもとを訪問し、聴き取り調査を実施します。その際、ご家族が種々の言い逃れをすることがあります。
例えば、ケースのサトシさんの事例で、ご家族は施設長に対し、年金を家族の生活費や息子の塾代に遣っていると発言していました。
しかしながら、行政担当者の聴き取りの際には、「利用者本人の色々な支払いのために充てていて、利用料が滞納になっている。今後必ず支払う。」などと、発言内容を異にすることがあります。
これでは、行政担当者も速やかに経済的虐待だと認定できなくなります。
筆者が実際に担当したケースでも、ご家族がのらりくらりと発言を変え、行政担当者も「ご家族が明確に使い込みを認めていない以上はしばらく経過観察が必要かと・・・」と事案が停滞してしまうこともありました。
そこで、滞納事案において、利用者本人の金銭管理を行っているご家族と面談する際は、必ず録音し、その録音データを行政に提出して下さい。その録音内容と、行政担当者のヒアリング内容がずれている場合、録音内容の方が信用できると判断され、経済的虐待の認定が速やかに行われることがあります。
なお、面談時の録音はご家族の許可を得ない秘密録音の方法で問題ありません。むしろ、ご家族の「生の声」を記録する上では、秘密録音の方が望ましいでしょう。
秘密録音は違法か否か、という論点については、以前寄稿した 社会問題化しているカスタマーハラスメント3にて詳しく説明していますので、そちらをご覧下さい。
3.市町村長申立における親族調査の在り方…行政側のメカニズム
経済的虐待の場面における成年後見制度の市町村長申立のルールを再度確認します。
老人福祉法第32条
市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条・・・(中略)・・に規定する審判の請求をすることができる。
高齢者虐待防止法第28条
国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。
老人福祉法第32条の「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」という文言は一体どのような意味なのでしょうか。
具体的には、「本人に2親等内の親族がない又はこれらの親族があっても音信不通の状況にある場合であって審判の請求を行おうとする3親等又は4親等の親族も明らかでないなどの事情により、親族等による法定後見の開始の審判等の請求を行うことが期待できず、市町村長が本人の保護を図るために審判の請求を行うことが必要な状況にある場合」をいうとされています。
こうした状況にある者について、介護保険サービスその他の高齢者福祉サービスの利用や、それに付随する財産の管理など日常生活上の支援が必要と判断される場合について、審判の請求を行うか否かを検討することになると考えられています(平成17年7月29日付厚生労働省老健局計画課長事務連絡を参照のこと)。
今回のサトシさんのケースで考えてみると、サトシさんの4親等内の親族から積極的に成年後見制度の申立手続きを行うとの申し出がなければ、2親等内の親族にサトシさんの成年後見申立てをするかどうか文書で意思を確認し、返事が無ければ市町村長申立に踏み切ることになると考えます。
仮に、金銭管理をしていない親族が成年後見制度の申立に協力的である場合は、行政としてはわざわざ市町村長申立に踏み切る必要はありません。また、意向確認する過程で他のキーパーソンが浮上し、ケースが良い方向に働くことも稀にあります。その意味で、行政は、上記の親族への意思確認を慎重に行う傾向があります。
もっとも、本人の生命・財産を安全に確保するためには迅速な対応が必要不可欠ですし、経済的略奪等が背景にある場合は、虐待者である親族から同意を得ることは現実的に困難です。
したがって、ケースバイケースですが、行政の親族に対する成年後見申立てへの意向確認という上記手続が省略されたり、簡略化されたりする場合もあると筆者は考えています。
個別具体的なケースに柔軟に対応することで、虐待下にある利用者本人がいち早く権利回復することが可能になります。
本稿を読んで頂いた皆様は介護事業所の方々が大半だと思います。
行政側のメカニズムを正しく知って頂いたことで、必要な情報を適時適切に行政側へ共有することの重要性を理解して頂けたのではないかと思います。是非、実務に役立てて下さい。