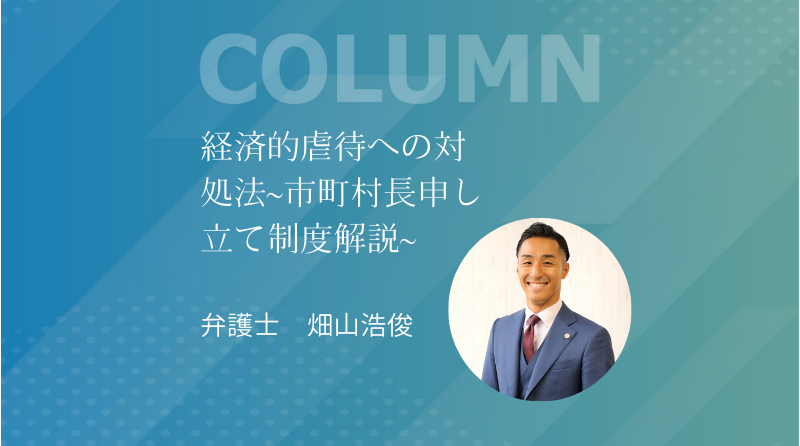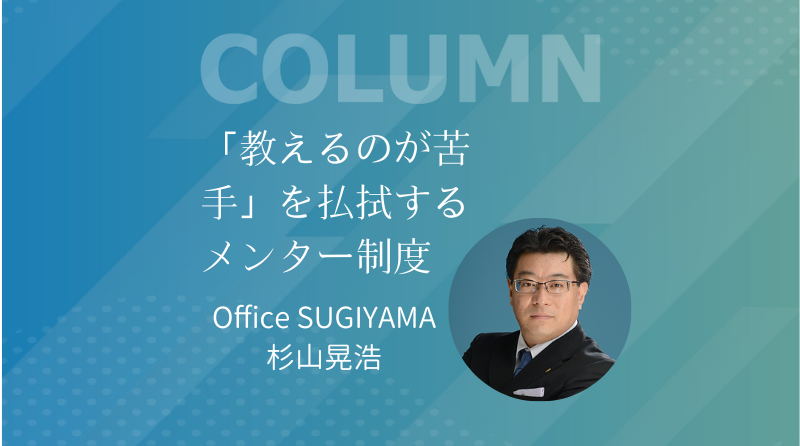※本稿では、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を「高齢者虐待防止法」と略称します。
1.介護事業者における滞納問題の具体例
以前の記事で紹介したとおり、弁護士法人かなめで2021年9月22日から同年11月末までの約一週間、滞納問題実態調査アンケートを実施しました。最終的には合計111法人から回答を頂きました。その中で、「過去に滞納問題が発生したことがある」と回答した割合は、実に87.4%であり、滞納問題の深刻な実態が垣間見えます。「福祉事業者として、催促することが憚られる。」「明らかに家族が本人の年金を遣い込んでいるのに、行政に通報してもすぐに動いてくれず、たらい回しにされる。」といった具体的な声が多数寄せられました。
本稿では、これらのアンケートの内容に加えて、筆者が実際に対応した案件を元に以下のケースを作成しました。いわゆる経済的虐待の事例です。本稿では、このケースを元に、経済的虐待と成年後見の市町村長申立てについて解説します。
<ケース>
ここはとある特別養護老人ホーム。
施設長は、利用料の滞納が続く利用者サトシさん(仮名)の件で頭を悩ませていた。
サトシさんは要介護5で、重度の認知症を患っており、意思疎通は困難な利用者だ。既に配偶者も亡くなっており、サトシさんの娘であるAがキーパーソンであり、A以外の親族は、現在サトシさんとは音信不通である。
Aは、サトシさんの年金が入金される通帳を管理し、どうやら自分たちの家族の生活費に年金を遣っているようだ。年金に余りが出た分だけを利用料の支払いに充てるため、利用料の滞納が徐々に増えている状況だ。
「このままでは、滞納が増える一方だ。何とかしないと。」と思った施設長は、Aを施設に呼び、どのようにして滞納を解消していくのかを話し合うことにした。
施設長:本日はお忙しいところお越し頂き、ありがとうございます。今日は、サトシさんの利用料の滞納額の件でお話があります。現時点でサトシさんの滞納額は、約35万円になっています。この滞納分はどのようにして支払って頂けますでしょうか。
A:そんなことを言われても、私たちも生活が大変なのよ。コロナの影響で仕事も減らされちゃって収入も少なくなったんだから。
施設長:大変な状況の中、このようなお話で恐れ入ります。ただ、サトシさんは、利用料を支払うのに十分足りる額の年金を受給しておられると思うのですが・・・。その年金から利用料をきちんとお支払頂きたいのです。
A:年金は入ってくるけど、私たちの生活費に充てると足りないのよ。あと、私の息子の塾代も高くて年金がいくらあっても足りない状況なの。福祉施設さんなんだから、ちょっとは融通を効いてくれてもいいじゃない。
施設長:年金を生活費や塾代に回すのはちょっと・・・。サトシさん本人が受給すべき年金ですから、施設の利用料に遣っていただかないと。
A:私たちだって大変なんだからちょっとは融通をきかせてよ。福祉施設なんだから弱者の味方でしょう?
施設長:・・・・・
2.経済的虐待と市町村などへの通報
まず、ご家族等の高齢者を現に養護する立場にある養護者における経済的虐待の定義から確認していきましょう。
高齢者虐待防止法第2条4項第2号
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
具体的には、
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・本人の自宅等を本人に無断で売却する。
・年金や預貯金を無断で使用する。
・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない。など
これらの行為が経済的虐待に該当します(詳しくは、厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(平成30年3月改訂)を参照のこと)。
上記のケースでも、利用者であるサトシさんの年金をご家族が遣い込んでおり、介護保険サービスの料金の滞納が発生していますので、ご家族の行為は経済的虐待に該当します。
では、経済的虐待と思われるケースに遭遇した介護事業者はどのように動けば良いのでしょうか。
結論は、「市町村に通報」です(高齢者虐待防止法第7条1項ないし2項)。
高齢者虐待防止法は、「高齢者の権利利益の擁護」を目的として定められた法律であり、その目的を達成するために、国や地方公共団体が積極的に連携し、種々の手段を講じて問題解決を図ることが求められています(同法第3条、第9条、第19条等参照)。
つまり、高齢者虐待防止法は、「高齢者が虐待されていると思われる状況を発見したら、行政自らが積極的に様々なサポ-トをしていきますよ。そのためには、虐待と思われる事例に遭遇したら通報して下さいね。」ということを求めている訳です。
介護従事者の皆様は、「虐待かもしれない」と感じたら、市町村に通報しましょう。
今回のケースでは、サトシさんの件を施設長が次のように通報することになります。
【通報の具体例】
うちの特別養護老人ホームに入居しているサトシさんという方の件で相談があります。サトシさんの年金をご家族が管理しているのですが、ご家族が生活費や子どもの塾代に年金を遣っており、サトシさんの利用料の滞納が続いています。経済的虐待だと思うので通報しました。今後どのようにしていけば良いでしょうか。
このように、まずは市町村に電話して相談することからスタートして下さい。
市町村はこれを受けて「経済的虐待の通報有り」と受け付け、必要な調査(利用者への聴き取り調査、ご家族への訪問調査など)を経た上で虐待の有無の判断をしていくことになります。
高齢者虐待に関する窓口業務は、市町村が行う場合、その委託を受けて地域包括支援センター、虐待防止センター、人権擁護センターなどが行う場合など、地域の実情によって異なります。通常は、集団指導の際に、高齢者虐待に関する通報窓口が広く周知されますので、各自治体のホームページをご確認下さい。分からない場合は、取り急ぎ、各自治体の介護保険課に電話して確認すると良いでしょう。
3.成年後見制度の市町村長申立て
ケースのサトシさんは、重度の認知症を患っており、意思疎通が困難な利用者です。自身では、介護サービスの契約の締結などの法律行為や、金銭の管理すらも難しい状況です。だからこそ、ご家族がサトシさんの年金を管理している訳です。
しかしながら、ご家族がその年金を使い込んでいるので、もはやご家族にサトシさんの金銭管理を任せることは危険です。
このような事態に備えて、成年後見人・保佐人・補助人が本人の判断能力を補うことによってその人の生命、身体、自由、財産などの権利を擁護することを目的とする成年後見制度が準備されています。つまり、成年後見人などが本人に代わって財産を管理したり、必要な契約行為を行ったりしますよ、という制度です。
成年後見制度は、原則として本人、配偶者、四親等内の親族等の家庭裁判所への申立てに基づき利用されます(民法第7条)。
しかしながら、今回のケースで、サトシさんは意思疎通が困難なのですから「本人」による申立はできません。また、配偶者も既に他界していますし、娘であるAが年金を遣い込んでおり、他の親族とは音信不通の状態であることから、「四親等内の親族」の協力を得ることが非常に難しい状況です。
そうすると、本人保護のための成年後見制度が使用できないという事態に陥ってしまいます。
そこで、このような場合に備えて、市町村長が、本来の申立人に代わって成年後見制度の申立手続きを行うことができるという例外的ルールが設けられています。
その内の一つが老人福祉法第32条です。高齢者虐待防止法も第28条において成年後見制度の利用促進を規定しています。
老人福祉法第32条
市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条・・・(中略)・・に規定する審判の請求をすることができる。
高齢者虐待防止法第28条
国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない
近年、成年後見制度に関する関心が高まり、市町村長申立ての件数も年々増加しています。直近の令和2年度の市町村長申立ての件数は8,822件であり、全体の約23.9%を占め、申立人の中で最も多い比率を占めています(次いで、本人の子が約21.3%、本人が約20.2%、最高裁判所事務総局家庭局『成年後見関係事件の概況―令和2年1月~12月~』参照)。
次回は、成年後見制度の市町村長申立の際における行政との連携の「コツ」について解説します。