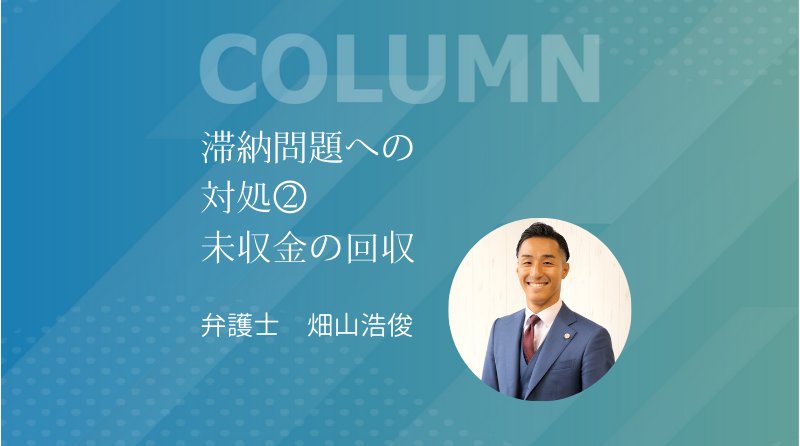1.介護事業所における滞納問題の実態
前回の記事では、滞納問題の実態とその対処法の第一弾として、連帯保証契約の解説をしました。
さて、前回の記事でも紹介したように、弁護士法人かなめでは、独自に滞納問題実態調査アンケートを実施しました。前回の記事公表時では、アンケートの回収は105法人でしたが、その後さらに増え、最終的には111法人のご協力を得ることができました。
その結果、「過去に滞納問題が発生したことのある」と回答した割合は、前回より多い87.4%になりました。推測ですが、アンケートの母数が増えれば増えるほど、滞納問題の経験のある法人の割合は増加する傾向にあると言えそうです。
今回は、未納金の回収について解説します。
2.いきなり弁護士が窓口になることはNG
弁護士法人かなめでは、現在、多数の介護事業者より滞納問題について相談を受け、その解決のためのサポートをしています。
その中で、一番重視していることは、「如何に弁護士が窓口にならずに債権回収を実施するのか」という点です。
たしかに、債権回収を速やかに実施する上では弁護士が介護事業者の代理人に就任し、介護事業者に代わって債権回収業務を実施する方が実効性は高いです。
未納者の立場からすると、介護事業者から支払いの催促が来ることよりも弁護士から催促される方が衝撃は大きく、「早く払おう」という気持ちになりやすいですよね。
しかし、介護事業は、地域密着の事業であり、一回で取引が終了する売買契約などとは異なり、継続的な契約です。
債権回収の際にいきなり弁護士が窓口になると、契約を継続する上で最も大切な信頼関係が壊れる可能性があります。
また、「あの介護事業者は、何かあったらすぐに弁護士を出してくるぞ。」という悪い噂が立つ恐れもあります。
したがって、いきなり弁護士に未納金の回収業務の代理行為を依頼することはお勧めしません。
3.顧問弁護士の活用法
お勧めする方法は顧問弁護士を活用することです。
具体的には、未納者へのお手紙を顧問弁護士に作成してもらうことをお勧めします。
差出人は介護事業者ですが、お手紙の内容を顧問弁護士に依頼することで、より法的なニュアンスが伝わりやすい文章になります。
実際に、弁護士法人かなめでも、顧問先である介護事業所に代わって未納者へのお手紙を作成し、顧問先から直接未納者へ送付してもらうことで、未納金の回収を実現しています。
ここでは、文例を細かく解説することは避けますが、これまでの経験上インパクトのある表現は以下のとおりです。
・・・なお、このお手紙は当社の顧問弁護士に相談の上、作成しております。 当社と致しましては、法的措置をとることまでは望んでおりませんが、未納金をお支払頂けない場合は、やむなく法的措置を顧問弁護士に依頼せざるを得ませんので、ご承知おきのほど、宜しくお願いします。
顧問弁護士の存在をきちんとお手紙の中で示すことで、介護事業者の覚悟が伝わるので、支払いに応じる人が増えます。顧問弁護士がいる介護事業者は、一度、顧問弁護士に相談の上、上記の方法をトライして下さい。
なお、上記の方法が使えるのは、次の2つの条件を充たす場合のみです。
(1)顧問弁護士がいること
(2)顧問弁護士に相談した上でお手紙を作成してもらう、ないしは作成したものを顧問弁護士にチェックしてもらうこと
つまり、仮に顧問弁護士がいたとしても、顧問弁護士に事前の相談を経ていなければ、「当社の顧問弁護士に相談の上」という表現は嘘になってしまいます。
したがって、「顧問弁護士に相談していること」をお手紙に記載する場合には、必ず(2)の手順を踏むようにして下さい。
4.顧問弁護士がいない場合はどうすれば良いのか
では、顧問弁護士が不在の場合はどうすれば良いのでしょうか。
ここでお勧めの方法は、弁護士の無料法律相談を活用することです。
今の時代は、インターネットで検索すれば、無料法律相談に対応してくれる弁護士を簡単に探すことができます。
特に、「債権回収 弁護士」と検索すると、債権回収業務を得意にしている弁護士が見つかります。そこで無料法律相談を申し込んで下さい。
「弁護士に相談している」ということを未納者に伝えることで、前述した「顧問弁護士に相談している」と同等のインパクトを与えることができます。
「弁護士に相談している」というアクションを取っていないにも関わらずこの表現を用いると嘘になってしまいますが、無料法律相談であったとしても「弁護士に相談している」ということは事実ですから嘘にはなりません。
顧問弁護士が不在の場合は、この方法を実践してみて下さい。