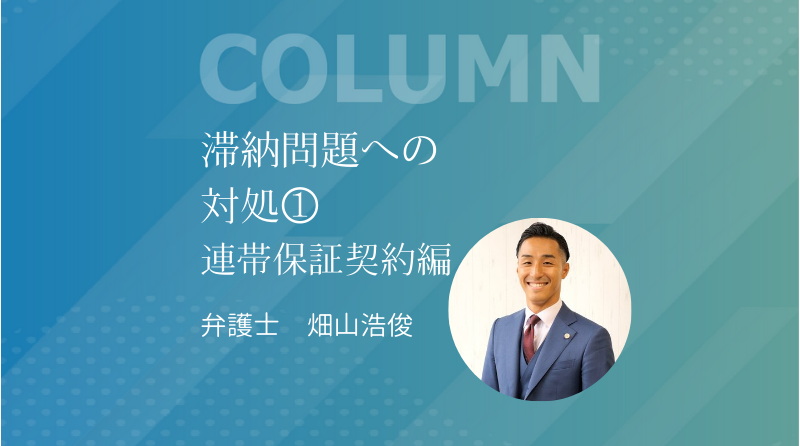1.87%が過去に経験。介護事業者における滞納問題の実態
我々弁護士法人かなめは、日本全国の介護事業者を法的にサポートしておりますが、中でも多い法律相談は「利用者が利用料金を支払ってくれない」という相談です。
あまりに相談件数が多いので、「実態調査をしよう」と思い立ち、介護事業所を運営する法人に対して、滞納問題実態調査アンケートを実施しました。調査期間は、2021年9月22日から同年9月末までの約一週間という短期間ですが、合計105法人から回答を得ることができました。
さて、アンケート結果で衝撃を受けたのは、「過去に滞納問題が発生したことのある」と回答した割合の高さです。
何と、実に87%の介護事業者が過去に滞納問題で悩んだことがあるという結果が出たのです。
さらには、現在進行形で、滞納問題に悩んでいる介護事業者の数も多数に上ります。
アンケート結果の中には、「福祉事業者として苛烈な取立てはできない」と思い悩んだ結果、滞納額が約300万円にも達してしまったことがあると内情を吐露して下さった介護事業者もあり、滞納問題に深く悩んでおられることが窺い知れます。
介護事業は、日本全国に存在し、利用者、その家族、そして地域社会そのものを支えるインフラです。
一生懸命に介護サービスの提供をしたにも関わらず、滞納問題が生じ、その解決ができない状態が続くと、介護現場のモチベーションは低下します。何より、滞納が頻繁に発生してしまうと、介護事業の運営に影響を及ぼしかねません。日本のインフラである介護事業の継続には、滞納問題の解決が不可欠です。
そこで、本稿から複数回に分けて、滞納問題への法的対処法を解説します。
初回は、連帯保証契約における注意点について解説します。
2.家族だからといって滞納額を当然に請求できる訳ではない
さて、利用者が利用料金を滞納している場合、当然のようにそのご家族に滞納分を請求できる訳ではありません。
介護利用契約は、利用者と介護事業者との間で締結します(利用者に意思能力が無い場合は除く)。契約は、契約当事者間のみで有効です。従って、仮に、利用者が利用料金を滞納した場合、あくまでその滞納額を請求できるのは利用者本人ということになります。
重要事項説明書にキーパーソンとしてご家族がサインしていても、これにより利用料金の支払義務まで発生する訳ではありません。また、身元引受人としてご家族がサインしていたとしても、その内容の多くは、利用者の緊急時に医療同意を行ったり、または、利用者が亡くなった際の荷物の引取りを行ったりといったものに留まり、利用料金の支払いを行う内容になっていません。
「滞納額を払ってくれませんか。」とご家族にお願いすることは自由ですが、法的にご家族へ滞納額の請求を行うことはできないのです。
3.連帯保証人を求める際の注意点:将来的に発生する債務と個人根保証契約
滞納が発生した場合、利用者のみならず、ご家族にも法的に滞納額の請求を可能とする手段が連帯保証契約です。
連帯保証契約とは、本来の債務者(今回のケースでは利用者本人)と同じ責任を負うことを約束することを言います。介護利用契約とは別途の契約です。
なお、ここでは、分かりやすくするために、家族に連帯保証人になってもらう前提で執筆していますが、連帯保証人はご家族以外でもなることができます。
連帯保証契約の注意点は、「個人根保証契約の極度額ルール」です。少し難しく聞こえますが、内容は簡単なのでご安心下さい。
例えば、住宅型有料老人ホームで考えます。
介護事業者としては、どのような滞納リスクに備えておきたいでしょうか。
当然のことながら、賃料(利用料)の滞納には備えておきたいですね。
それ以外には、利用者がわざと部屋を汚したり、部屋の壁や備品を壊したりした際に発生する修繕費や原状回復費用もカバーしておきたいと考えるでしょう。他にも退去時に荷物を撤去しなかった場合に発生する撤去費用もカバーする必要があるかもしれません。
このように、介護事業者としては、様々な債務の発生に備えておきたいと思うのが普通です。
介護に関する契約は、一回きりの契約ではなく、継続的な契約であり、その継続的な契約から将来発生する不特定の債務をまとめてご家族個人に連帯保証してもらいたいという場面で結ぶ契約を「個人根保証契約」と呼びます。
4.121年ぶりの民法改正による連帯保証契約のルールが変更に
さて、このニーズを満たすため、従来は以下のような取決めをしている場合が多く見られました。
連帯保証人は、介護事業者に対し、利用者が本契約上負担する一切の債務を連帯して保証する。
この取決めは、現在、無効です。
その理由は、2020年4月1日から改正民法が適用されるようになったためです。
2020年4月1日より前の契約では旧民法が適用されるため、上記の取決めでも問題ありませんでした。
しかしながら、上記の取決めでは、連帯保証人がサインをする段階で、「一体上限はいくらになるのだろうか」という点が明記されていないため、連帯保証人の負うべき将来のリスクが明確になっていない点が問題です。従前、連帯保証人が連帯保証契約にサインする際、将来のリスクの上限が示されていないことで予想外の債務を負うことになり、連帯保証人の生活自体が破綻してしまうという問題が多数発生しました。「たしかに連帯保証契約はしたけど、まさかこんな金額になっているなんて・・・!」というイメージですね。
実に121年ぶりに民法が改正され、個人根保証契約も改正の対象になりました。
2020年4月1日以降に締結する連帯保証契約は、以下のように上限額(極度額)を定めるようにしましょう。
連帯保証人は、介護事業者に対し、利用者が本契約上負担する一切の債務を極度額●●万円の範囲内で連帯して保証する。
極度額をいくらにするのか、という点については、法律では特段の規制はありません。
もっとも、あまり高額に設定しすぎると、公序良俗に反するとして無効になる可能性がありますし、何より、あまりにも高額な金額を記載すると、連帯保証契約にサインする段階で抵抗を覚え、サインしてくれない可能性があります。
例えば、私が過去に担当した事例の中で、住宅型有料老人ホームの滞納額で一番高かった事例は、約80万円の滞納額でした。そこで、施設系サービスについては、極度額100万円が一つの目安ではないかと考えています。
今回の原稿では、介護事業者の多くが悩んでいる滞納問題の実態とその対応策・注意点として連帯保証契約について解説しました。
次回は、滞納の理由がご家族による経済的虐待にある場合の対応策について解説します。