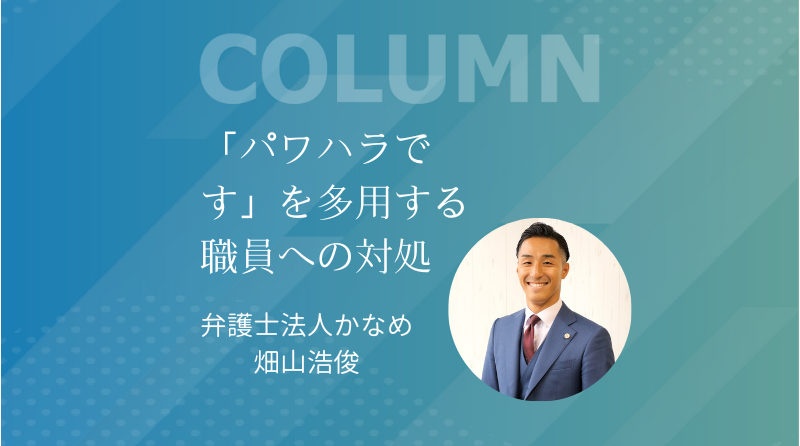1.「パワハラです」を多用する問題職員の存在
皆様の介護事業所に、注意指導や業務に関する指摘を受けると、「それはパワハラです!」「いじめですよ!」などとすぐに反発する職員はいませんか。
令和3年度介護報酬改定で、全ての介護事業者に「ハラスメント対策の実施」が義務付けられたこともあり、ハラスメント対策は日本全国の介護事業所において、目下の課題となっています。
ただ、「ハラスメント」と言う言葉が一人歩きした結果、日本各地の介護事業所で、本来、「パワハラ」に該当しない場面でも「パワハラだ!いじめだ!」と主張する問題社員が出現しています。この問題を放置しておくと、管理職は疲弊し、やる気のある職員が職場からどんどん離脱してしまう重大問題に発展してしまいます。
昨年3月20日にアップした『急増する逆パワハラ!組織崩壊を防げ!』という記事で、「逆パワハラ」への対処法について解説しましたが、今回は、より具体的に裁判例を分析して、この問題への対処法を深掘りしたいと思います。
2.パワーハラスメントの定義
裁判例の分析に入る前に、パワーハラスメントの定義を再度確認しておきましょう。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
- 優越的な関係を背景とした言動であって、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
~事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令和2年6月1日適用】より抜粋~
「逆パワハラ」との兼ね合いで最も重要な視点は②です。
業務上、注意指導を受けたことに対して、「それってパワハラですよ」とすぐに反発する職員は、往々にして受け手の主観に基づいてパワハラかどうかを判断しています。
しかしながら、パワハラかどうかは、受け手の主観では判断されません。
業務上必要かつ相当な範囲内での注意指導であればパワハラには該当しないのです。
そして、業務上必要かつ相当な範囲かどうかは、主観ではなく「客観的に」判断される点が重要です。
3.裁判例の分析と対策
今回、紹介する事例は、大阪府下のとある社会福祉法人が運営する介護事業所内で発生したハラスメントトラブルです(大阪地方裁判所令和3年2月25日判決)。
訴えを起こした原告は、上司の種々の言動を捉えて「パワハラだ!いじめだ!」と主張し、法人を相手取って損害賠償請求訴訟を提起したのですが、結論的に、パワハラに関する原告の主張は全て退けられています。つまり、裁判所は「パワハラではない」と判断したのです。以下、争点の一部を紹介します。
(1)職務上の適正を欠くと判断した業務から担当を外すことは「パワハラ」か?
原告は、デイサービスの利用者を自宅まで送迎する業務を行った際、作業手順に従えば、利用者の居室のエアコンを作動させることになっていました。そこで、原告がエアコンを作動させようとしたところ、設定温度が27度の暖房になっていた(当日は平成29年5月20日)ことから、利用者に確認したところ、利用者はそのまま作動してくれればよいと回答しました。そのため、原告がエアコンをそのまま作動させて利用者の家を後にしたところ、利用者の親族からクレームが入るという問題に発展しました。
原告は、今回の問題だけではなく、内容は違えどミスを繰り返していました。そのため、介護事業所は、利用者に被害が発生してからでは遅いと考え、送迎のように利用者と1対1で対応しなければならない業務ではなく、周りに他の職員がおり、相談等ができる施設内での業務につかせるため、原告を送迎業務から外しました。
原告は、これに対して「必要以上に重いペナルティを課された」と主張しましたが、裁判所は、「原告がエアコンを作動させることに疑問を持ちながらも施設側への相談等を行わず、以前にも相談等を行わずに注意を受けていたことから、被告代表者としては、今回は、利用者に危険が生じなかったとしても、将来のリスクを考えると、1人で介護等の対応を行う送迎業務ではなく、周りがフォローできる施設内での勤務が望ましいと判断したものであって、合理的な判断といえる」と認定し、原告の主張を退けました。
つまり、介護事業所側の対応は、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲の処置であり、何ら問題が無いと判断された訳です。
この事案は、「担当業務を外す」=「パワハラ」と主張する職員がいる場合の対応として、参考になると思います。介護事業所としては、担当業務を外す判断をする前提として、「何故担当業務を外すのか、その理由を明確に言葉で説明できるか」を十分に検討しましょう。そして、職場のメンバーにその理由を説明した際、メンバーの中に違和感を覚える者がいないのであれば、その処置は「業務上必要かつ相当な範囲」に留まると言えるでしょう。これらの点を、顧問弁護士などに確認しながら検討することも良い方法です。
(2)シフトに無い業務を担当させることは「パワハラ」か?
原告は、他にも、シフトに無い業務を命じられたことに対して「嫌がらせだ、いじめだ」と主張していました。
具体的には、原告が「シフトどおりに動きたい」と伝えた際、リーダーが「原告は送迎業務が無いし入浴の介助はしても当たり前ではないか。」と言ったのですが、原告はこれを「嫌がらせだ、いじめだ」と主張したのです。
裁判所は、「そもそも原告の勤務状況や他の従業員の勤務状況を見て、原告のシフトにない業務を命じること自体は業務指導の範囲を超えるものではなく、リーダーが上記発言を行ったとしても、それが嫌がらせ、いじめに該当するものではない。」と認定し、原告の主張を退けています。
皆様の職場においても、シフトに無いことを命じた際に一切協力姿勢を見せない職員はいませんか。
「シフトに無いことはやりたくない!」と主張する職員の気持ちも理解できなくはないのですが、そもそも介護事業所においては、職員同士のチームプレイ、協力が何よりも大切です。職員が法人に対して負う「労務提供義務」の具体的な内容は、「職員同士が連携して、協力しながら介護サービスを提供する義務」です。つまり、協力しながら働く、助け合いながら働く、ということは、職員が負っている義務の本質的な内容なのです。「シフトに無いことはやりたくない!」というのは、職務放棄に他なりません。
ただ、業務上の必要性もないのに、シフトを完全に無視したような業務に従事させたり、殊更に介護業務と関係の無い業務にばかり従事させたりするようなケースでは、「嫌がらせ」と認定される場合があることには注意が必要です。あくまで、通常予定される業務に従事させることを前提に、助け合いが必要な場面があるのであれば、シフトに無くとも業務に従事することが労務提供の具体的な内容になるのです。
シフトに無い業務を担当させる場面は、介護現場では頻繁に生じます。
業務上必要であり、かつ相当と言えるのであれば、たとえシフトに無くともそれを命じることはパワハラには該当しません。この点も介護現場では役立つ知識だと言えるでしょう。
4.一人で悩まず顧問弁護士を頼ろう
原告は、この裁判で、上記に記載した点以外にも、多くの点について「パワハラだ」という主張していましたが、裁判所は原告のパワハラに関する主張を全て退けています。
原告が「パワハラだ」と感じていたとしても、それが業務上必要かつ相当な範囲で行われた処置であればパワハラには該当しない、ということを明らかにした点で、介護現場における労務管理上、有意義な裁判例と評価できます。
ただ、裁判になる前の段階で、いざ、同様の問題が介護現場で生じた場合は、一人で悩まず、必ず、同僚や上司、さらに上部の法人本部などに相談するようにして下さい。そして、法人に顧問弁護士がいる場合には、当該職員に対する注意指導の内容や処置の内容が「パワハラ」に該当するのか否かを随時相談することが大切です。
問題行動を起こす職員と向き合うことには多大な精神的負担を伴いますが、弁護士に随時相談し、「それは業務上必要かつ相当な範囲に留まる処置ですので、問題ありませんよ。」とアドバイスを受けることができれば、対応する管理者や職員の精神的負担は大幅に軽減されるはずです。
決して一人で悩まないで下さい。