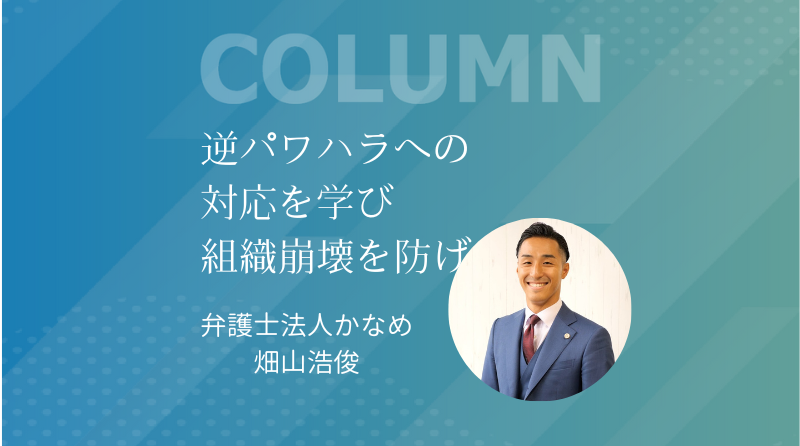1.急増する「逆パワハラ」への対応の必要性
介護現場で、利用者に対し、とても危ないケアをしている職員がいたとします。
当然、それを見た上司は厳しく注意指導します。
「もし怪我させたらどうするの!危ないじゃない!〇〇しないといけないよ!」と咄嗟に厳しい言い方になってしまうこともあるでしょう。そうすると、その注意指導を受けた部下が「そんなキツい言い方はパワハラじゃないですか?傷ついたので謝罪して下さい。許せません。」「労基署に相談に行きますよ!」「私は知合いに弁護士がいるので、はやく謝罪しないと弁護士をつけて裁判しますよ!」などと上司を責めて立ててくることがあります。
このような、部下から上司に対するパワーハラスメントが、今回取り上げたい「逆パワハラ」です。
最近、介護現場では「逆パワハラ」が増えています。
今回、「逆パワハラ」を取り上げたのは、「逆パワハラ」への対処方法がわからず、上司が自分の指導に自信を無くしてしまい、さらには注意指導をした部下に追い込まれ、精神疾患を発症し、休業を余儀なくされるケースが増えているからです。こうなると、組織の指揮命令系統が機能しなくなり、組織崩壊が起きてしまいます。
今や、「逆パワハラ」への対応は介護現場にとって急務なのです。
2.「逆パワハラ」が増えている原因
冒頭のような逆パワハラ事例が増えている原因の一つに、「パワハラ」という言葉が正しく理解されず独り歩きしてしまっている点が挙げられます。
皆様は「パワハラかどうかは、受け手がどう感じたかで決まる。被害者がパワハラと感じたらパワハラなのだ」というような言説を聞いたことはありませんか。
このような主観説が巷で横行していますが、これは誤りです。この誤解が「逆パワハラ」が起こる一つの原因です。
そもそも、「パワーハラスメント」という言葉自体、法律では使用されていません。
2020年6月1日から「パワハラ防止法」が施行された、という報道を耳にされた方も多いと思いますが(中小企業では2022年4月1日から施行)、この法律の正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下、「労働施策総合推進法」)であり、いわゆる「パワハラ防止義務」について定めた条文は、以下の通りです。ご覧の通り、「パワーハラスメント」という言葉が文言には出てきません。
(雇用管理上の措置等)
第30条の2
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
これだけでは、企業は何をすれば良いか分からないため、労働施策総合推進法30条の2の第3項では厚生労働大臣が必要な指針を定めると規定されています。以下、指針のURLを貼っておきますので、興味のある方は一読してみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf
この指針の中で初めて「パワーハラスメント」という言葉が出てきます。
さて、この指針では、「パワーハラスメント」をどのように規定しているか、ここが大切なポイントです。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。(下線は筆者による)
これを見て頂ければ、「パワーハラスメント」の定義の中に、職員の「主観」を考慮するような文言が入っていないことがわかると思います。「私がパワハラと感じたからパワハラだ」という言説は明確に誤りです。
客観的にみて、業務上必要かつ相当は範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワハラではないのです。
介護現場において、危険なケアを行う職員がいたら、厳しく注意指導することは当然必要です。介護事業所は、利用者と利用契約を締結しており、利用者の生命・身体等の安全に配慮してサービス提供する義務を負っています。この義務に抵触した部下を、上司が厳しく注意指導することは、業務上必要かつ相当な範囲内の注意指導であり、パワハラには該当しません。
3.「逆パワハラ」への対処法
(1)注意指導の方法
逆パワハラを受けた上司は、往々にして自身の注意指導が「パワハラ」と言われたことに戸惑います。パワハラの意味合いを労働裁判例等の実務の観点から自信を持って理解している管理者は少なく、「果たして自分の注意指導はパワハラには該当しないのだろうか」と不安を抱き、徐々に、指導に対して後ろ向きになる傾向があります。
仮に、自身の注意指導が業務上必要かつ相当な範囲を超えた指導なのかどうかが不安になった場合は、労働問題の裁判実務に精通している弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。そのような環境の無い方は、一人で抱え込まずに必ず誰かに相談するようにして下さい。
私は、管理者から「業務上必要な指導をしたのだが、部下からパワハラと言われて悩んでいる」という相談を頻繁に受けています。その多くは「パワハラ」には該当しない適正な業務指導です。適正な指導を受けたにも関わらず、自己反省せず反発する部下に対しては、逃げずにきちんと指導する必要があります。その理由は、上司から部下に対する業務指導は、組織が有している指揮命令権限に基づく行為であり、部下がこれに背くことは服務規律に違反するからです。私が相談を受けた場合には、部下の行動のどの点に問題があるかについて書面で指摘し、改善を促すよう指導しています。場合によっては、就業規則の懲戒規定に基づき、懲戒処分を下すこともあります。
反発してくる部下に書面を交付して改善を促す、ということ自体を嫌う管理者もいます。指導には膨大なエネルギーが必要ですから、反発する部下に対して真正面から向き合う辛さは理解できます。しかし、見て見ぬふりをしてしまうと、組織の指揮命令系統が機能しなくなるため、確実に組織は崩壊への一途をたどります。組織崩壊は一瞬には起こりませんが、やる気に溢れ、組織をよくしようとする積極的な職員が、組織に幻滅して離職していき、さらには新しく入ってきた職員も職場の空気の悪さからすぐに退職していく、というように、目に見ない形で徐々に進行していきます。組織を守る覚悟をもって「逆パワハラ」の問題に対処しましょう。
(2)労働基準監督署対応
「逆パワハラ」の問題に覚悟をもって対処する、とは言うものの、昨今はさらに問題が複雑になっています。それは、上司が部下に対して業務上必要な注意指導をしたことに対し、「パワハラを受けたから精神疾患になった。労災ではないか。労働基準監督署に相談に行く」といったように労働基準監督署が関与するケースが増加しているという点です。
普段聞きなれない「労災」「労働基準監督署」という言葉を聞くと、余計に不安が増大すると思いますが、このような事態にも冷静に対処しましょう。
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。労災の申告に対し、労働基準監督署が必要な調査を実施し、労災に該当するか否かを認定する、というプロセスを経ます。
私は、指導を受けた部下が労災を主張するのであれば、それに応じて労災の手続きを進めれば良いとアドバイスしています。簡単に言うと「真正面から受けて立ちましょう」ということです。間違っても、労災申請を阻止しようとするなど、「労災隠し」との誹りを受けるような対応をしてはいけません。
精神疾患の場合、労働基準監督署は「精神疾患の労災認定」というマニュアルに基づいて調査を実施します。
私は労働基準監督署の調査に立会うことがありますが、調査では、労災申請をした職員以外の複数の職員から、「パワハラ」に関する具体的なエピソードの有無について聴取りが実施されます。
しかし、「逆パワハラ」のケースでは、聴取りを受けた職員のほとんどは、「上司の指導は適切だった。なぜパワハラと主張しているのか分からない」と回答し、パワハラに関する具体的なエピソードが出ないことが多いです。実際、労働基準監督署の担当者からもヒアリングの最中に「何故これをパワハラと主張しているのか良く分からない」という本音が漏れることもあります。
労災請求に対して過度に恐れる必要は無く、淡々と応じるようにしましょう。
4.研修の重要性
令和3年度介護報酬改定では、全ての介護事業所において「ハラスメント対策の強化」が義務付けられました。ハラスメント対策の強化は絶対的に必要です。
しかし、「ハラスメント根絶」を叫ぶ前に、ハラスメントの意味をしっかりと理解しておく必要があります。その重要性を伝えるために、本稿で「逆パワハラ」に関する問題を論じました。
ハラスメント対策の強化には、労働法や労働裁判例に関する理解が不可欠です。この分野に詳しい弁護士等の専門家による研修を受ける環境を整えることが急務です。
今やオンラインを活用することで、それぞれの道の専門家に簡単にアクセスできるようになりました。自分たちの介護事業所にとって必要な情報を積極的に獲得することを習慣化し、強い組織作りを実践して下さい。
本稿を読んで「逆パワハラ」に苦しむ管理者が一人でも救われることを願っています。