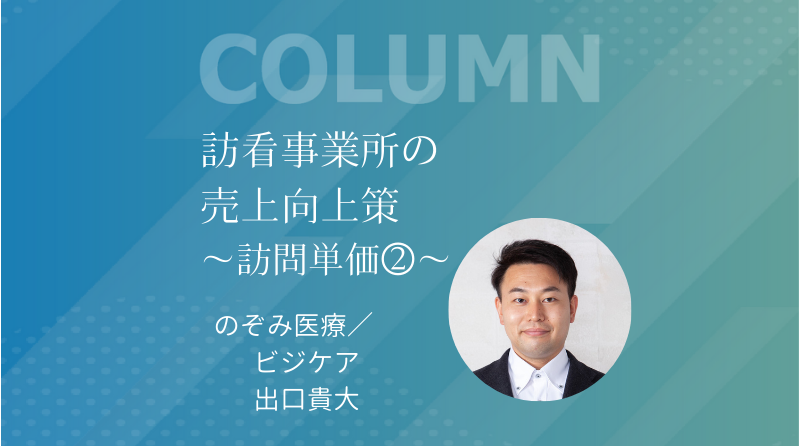前回より、「売上を上げていくための考え方」についてお伝えしております。
今回はこれを掘り下げ、「加算を取る意識を育てる」ことをテーマに取り上げます。
前回の記事をまだ読んでいない方は、ぜひ合わせてお読みください。
*前回記事:訪問看護ステーションにおける売上を上げる戦略思考~訪問単価を上げよう(1)(単位、診療点数)~
加算を意識して取っていますか?
現在、訪問看護の経営者、管理者の方と200名近く毎月関わっています。その中ですぐに売上を上げる方法を尋ねられることが多いのですが、私が最初に着手するのは取得できる加算の見直しです。
ここで皆さんに質問です。
本当にあなたの事業所が算定できる加算を”全部”算定できているでしょうか?
加算を算定できていなくても、それを教えてくれる親切な方はいません。毎月どの加算を取っているのかチェックし、かつ、加算の算定に向けて運営体制を整えようと意識する必要があります。
今回は加算を取るうえで大切な考え方を3点お伝えします。
1. 加算が与える利益への影響
まずは加算が算定できずに単価(訪問1件数当たりの売り上げ)が1%下がった場合の影響をシミュレーションしてみましょう。
以下の条件で収支を見てみます
平均単価8,500円、総訪問件数1,000件、変動費率5%、人件費率60%、その他固定比率20%
上記を管理会計で表すと以下のようになります。

ここからもし単価が1%(85円)下がり、8,500円から8,415円になったとします。 その場合が以下のような図になります。

単価は1%(85円)減ですが、 利益は161万5,000円→153万4,250円と5%(8万750円)も下がってしまっています。
逆に単価が1%上がった場合はどうなるかを見てみましょう。

今回は単価1%(85円)上がっただけですが、利益は161万5,000円→169万5,750円と5%(8万750円)増えています。
*変動費率、粗利率によって変化する倍数は異なりますのでご注意下さい
ここでお伝えしたい事は、わずかな単価の変化でも、事業所全体の利益は大きく増減するということです。
そのため、「利益を必死に獲得していく、そのために加算を軽視せずにしっかりと取りに行く」といった小さな意識が今後の大きな事業や企画、事業の成長につながると信じ、私自身事業所運営を行っており、運営先の事業所の経営者様、管理者様にもお伝えしています。
2.取り忘れやすい加算を見直す
管理者へのアドバイスを行う中で、せっかく算定できる条件がそろっているのに、算定できていないと感じることが多い加算をご紹介します。
気になるものがあれば、今一度詳細要件などを確かめてみてください。
また、算定をし忘れないためのお勧めの取り組みもご紹介いたします。
・初回加算(介護保険)
最もよく知られている加算かと思います。
そのため、「こういう時でないと取れない」という思い込みがちな加算でもあります。
初回加算が取れるタイミングは3つありますが、皆さまはすぐに答えることができるでしょうか?
・1つ目は訪問開始時の算定です。
こちらは皆さん算定し忘れることがほとんどないと思います。
・2つ目は「要支援から要介護」、あるいは「要介護から要支援」と予防と介護の間で変更がある時です。
ケアマネジャーも忘れて、提供表の加算で挙がってこない時があるので注意してみて下さい。
・3つ目は2カ月間訪問看護が提供できずに3カ月以降から再開になったケースです。
こちらも良く忘れがちで入退院を繰り返しているケースではよくあるのでしっかりと押さえておいてください。
・情報提供療養費(医療保険)
この加算については、理解不足で算定されていないケースが多いと感じます。
利用者の同意を得たうえで、市町村・都道府県や保育所など、または保険医療機関等に対して、訪問看護に関する情報を提供した場合に算定できる加算です。
1〜3の3種類あり、それぞれの情報提出先は以下の表をご参考ください。

参考:【表】中央社会保険医療協議会 総会(第493回) 資料より
情報提供先と同様に、情報提供で出きる頻度も異なっているのでご注意ください。
・1は保健師に確認して求めに応じて提出します。
地域によっては毎月提出が求められる場合や1年に1回でいい場合、
提出不要の場合があるため算定対象がどのような利用者になるのか管轄の保健師に
ご確認ください。
・2は年度ごとに1回です。
こちらは小児の利用者が多くないと算定する頻度も少ないかと思います。
・3は保険医療機関等に入院、入所する際に看護サマリーと一緒に渡します。
看護サマリーは看護師に、情報提供書は医師に提出するという違いがあります。
比較的算定できる頻度が多い加算ですが、実際にはできていない事業所が多い印象です
・在宅患者緊急時等カンファレンス加算(医療保険)
こちらは在宅で療養している利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際、カンファレンスを行い、適切な診療方針を立てること、診療方針の変更についての情報共有を行うことを評価する加算です。特にターミナルの看取りを行うケースや介護保険で状態悪化して特別訪問看護指示書で医療保険の訪問となり、医療に切り替えても状態が落ち着かない時などに算定できます。
普段行っているサービス担当者介護では算定は取れませんが、上記の要件の場合でカンファレンスを行えば算定できますのでお忘れなく算定してください。
・特別管理指導加算(医療保険)
こちらは退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、特定の状態にある利用者に対して退院時共同指導を行う時に算定できる加算です。こちらも取れると知らなかったと言われる加算なので、今一度退院時のご利用者様の状態を把握し、算定できる方かどうか見極めて算定してください。
●加算を取り忘れないための取り組み
お勧めしたいのは事業所内での加算の勉強会です。
自事業所の重要事項説明書を使いながら実際にあったケースを振り返り、実際に算定したケースをスタッフ全員で確認します。
加算だけの勉強だとスタッフに興味を持ってもらうのは難しいですし、中々頭に入ってきません。
しかし、実際に今関わっている担当の利用者様と関連付けることで学びの効果が高まります。
また、ご利用者様にお渡ししている重要事項説明書の中に加算の詳しい説明や加算の一覧が書かれている事がほとんどかと思います。
新たにテキストを用意するのではなく重要事項説明書を活用することで、スタッフにその中身を知ってもらい理解してもらう機会にもなります。
ご利用者様が増えてくると管理者だけで加算を全部把握しきるのには限界があるため、スタッフも巻き込みチームで加算を取っていける体制を作っていきましょう。
3.事業所の成長のために算定したい「退院時共同指導加算」
上述した加算のほかに、積極的に取って頂きたい加算は退院時共同指導加算です。
実際に病院に出向き、カンファレンスをする時間の割に、点数が低いため、積極的に算定しよう、病院のカンファレンスに参加しようと考える方が少ないように感じます。
確かに点数は低いですが、この加算を算定することには以下の3点のメリットがあると考えています。
・病院との関係性を築け、次の新規案件獲得につなげるチャンスを作れる
・早期に在宅での対応をシミュレーションし、ケアマネジャーと共有することでご利用者様や
ご家族により安心して自宅に帰って頂く環境を提供しやすくなる。
ケアマネジャーと環境づくりに取り組むことでケアマネジャーからの信頼向上にも繋がる。
・病院と連携することで早期退院できる体制づくりを行っていき、地域のインフラを作っていく
事業所として成長していける
上記のように算定としては得られる点数は少ないですが、それ以外の多くのメリットがあるのでぜひ今後算定できる体制や動きを作って頂けたらと思います。
最後に
一つ一つの加算を取って行くための取り組みは、小さな行動の積み重ねかもしれません。
しかし、加算を取ることで思っている以上に利益に影響が出るだけでなく、事業所の体制整備・サービスの質向上に向けた取り組みが訪問看護ステーションのチーム全体、ご利用者様、関わる方々に与える影響力は大きいものです。
まずはご自身の事業所で、今回例示した加算がちゃんと取れているのか、また、取って行くためにはどのような取り組みを始めるべきか考えてみませんか?