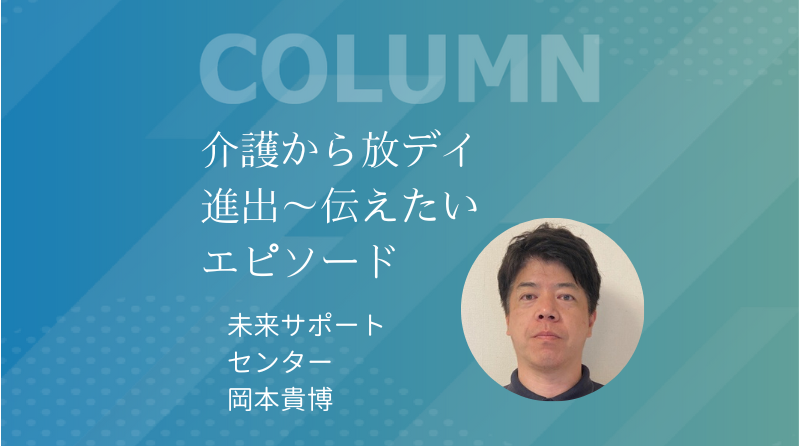前回、「放課後等デイサービスを始めたい」というご相談を代表的な4パターンに分類してお伝えしました。今回はそのうち、介護業界から放課後等デイサービスに進出された事例をご紹介したいと思います。
本サイトは、介護業界の方が数多くご覧になられているかと存じます。昨今、放デイ事業はニーズが拡大しているとして注目を集めている事業ですが、特にこの領域への事業進出を考えていらっしゃる方には、お伝えしておきたいエピソードです。
訪問看護ステーションから障害福祉サービスへ事業拡大
その事業者さん(Aさんとします)と私の関わりが始まったのは、10年以上前のことです。訪問看護ステーションを運営されているAさんから、ケアプランセンターを立ち上げたいというご相談がありました。
開設の動機は、「利用者様・患者様がより安心できるサービスを提供し、地域に貢献したい」というものです。開設直後は利用者の獲得が出来ずに苦戦されていましたが、要支援の方を積極的に受けることで地域包括支援センター等から信頼を得ることに成功し、事業所運営が安定していきました。
その後も「地域の高齢者福祉に貢献したい」という一貫した姿勢を持ち続け、訪問介護ステーションを立ち上げられました。こちらもやはり当初は競合事業所が多く、なかなか利用者を増やせなかったようです。
しかし、地域の相談支援専門員から「障害者のヘルパーはできないか?」という相談を受けたことが転機となりました。
その地域では、障害者の受け入れ先が不足していたのです。
障害者の受け入れを進めることで地域におけるステーションの認知や信頼性が高まり、高齢者の利用者数も増えていきました。Aさんは障害者の支援に関わることで知見が広がり、障害当事者や家族のニーズに対する理解が深まり、地域資源の不足という社会課題も肌で感じられるようになったと言います。
なにより、”子どものときに、どれだけの支援を受けてきたか”が、成人になってからの本人、家族の負担・不安が大きく影響することを目の当たりにした経験が大きかったようです。
「重症心身障害児・医療的ケア児を支援できるのはあなたしかいない」地域からの要望
Aさんはその後、訪問介護事業所の開設後、デイサービスや福祉用具貸与・販売も手掛けるようになりました。その頃には法人としてのブランド力が高まっており、新しい事業であっても利用者がすぐに集まるようになっていました。
多角化によって会社全体の業績も安定してきた頃、「医療的ケア児や重症心身障害児の日中に安心して過ごせる場所がない」という話を耳にすることが多くなりました。
これは当時の全国的な課題であり、国は、2021年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児や重症心身障がい児に対応している児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬を引き上げるなど対応しています。また、重心事業所における看護職員加配加算の要件も緩和されました。
このような社会情勢も手伝い、Aさんは、地域の関係者や専門家達から、「あなたの会社は、医療サービスも介護サービスも提供している。看護職員や理学療法士らも多く在籍している。通所系サービスを行うノウハウもある。あなた以外に、この地域で重症心身障害児・医療的ケア児を支援する人はいません」と言われるように。
ご自身でも会社の資源を最大限生かせる事業だと感じたこと、また、”子どものときにどれだけの支援を受けてきたかによって、成人になってからの本人、家族の負担・不安が大きく変わる”という居宅介護事業での実感を思い起こし、重症心身障害児対象の放課後等デイサービスを始める決断に至ったといいます。
放課後等デイ参入の初めの壁は”児童発達支援管理責任者の確保”
放デイ事業を始める決断はしたものの、初めに当たった壁は児童発達支援管理責任者がいないことでした。
児童発達支援管理責任者は、引く手あまたであり求人を出しても応募が少なく、どうにか資格を持っている人材の面接に至っても、必要な経験や知識が不足していたのです。
資格を持っている方がいれば事業所開設はできるのですが、Aさんが事業を開始する目的は、「放デイ事業所の開設」ではなく重症心身障害児・医療的ケア児への適切な支援と家族への安心の提供です。人材採用を妥協する考えは持っていませんでした。
実際、児童発達支援管理責任者を”とりあえず”採用して放デイ事業所を開設してしまうのはよくある話です。しかし、資格を持っているだけで十分な知見のない児童発達支援管理責任者を雇用したばかりに、適切なサービス提供が出来ず、保護者に不信感を与え、現場スタッフとも摩擦がおき…このような悪循環の結果として、すぐに退職に至ってしまうこともまた、特に新設事業所では”よくある話”です。
このとき、Aさんは「この大切なポジションを任せられる人がいないのであれば、私がなろう」と決意し、実際の事業所に修行にいき、2年をかけて児童発達支援管理責任者の資格を取得しました。そして資格を取得してすぐに物件の選定を行い、事業所を立ち上げたのです。
Aさんの事業所は立ち上げ前から利用したいという声が多く、実際すぐに利用者が集まりました。
これから地域にとってなくてはならない事業所になることを私も確信しています。
”成長市場”という理由だけでは難しい放課後等デイサービスの運営
Aさんが放デイ事業所を開設して1年が経つ現在、開業メンバーの一人であった保育士さんが無事、児童発達支援管理責任者の資格を取得しました。
一見、遠回りに見えた開業までのアプローチですが、信頼できる管理者を得ることができたAさんの事業所は、利用者も常に定員いっぱいです。
放デイ事業の市場は現在拡大しているということ、また、介護の隣接領域として捉えられることなど、様々なきっかけで興味を持たれることもあると思います。
しかし、“なんとなく”事業を始められた場合、スタッフとの関係構築につまづき、子どもへの支援内容に迷い、保護者対応でトラブルが起き…と常に問題を抱えているケースが多いのも事実です。
もちろん、”なんとなく”始めた事業所でも、目の前の課題に一つ一つ丁寧に向き合い、制度をきちんと理解していけば、やりがいや使命感が生まれることもあるでしょう。
どのような事情があるにしろ、地域に受け入れられる事業所に共通していることは、確固たる理念があることと、しっかりと段階を踏んだ準備のプロセスを踏んでいることかと思います。
こどもたちや保護者にとって安心できる場所を一つでも多く。
私自身もそのような気持ちで、事業者をサポートしてまいりたいと思います。