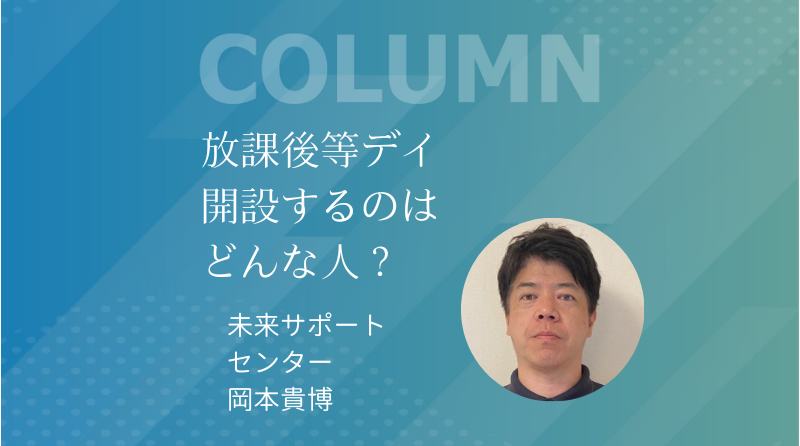2024年4月の報酬の引き下げ等による影響で、「運営が厳しくなった」とおっしゃる放課後等デイサービス事業所は増えていますが、一方で、まだまだ「新規開業をしたい」という相談が弊社に寄せられています。
弊社では、放課後等デイサービスの制度が始まって以来、100を超える事業所の開業支援を行ってきました。今回は、その経験から、開業の経緯や目的別に事業所運営が上手くいくパターンとつまずきやすいポイント・懸念点を紹介します。
※前回、重症心身障害児対象とした事業所の立ち上げ事例を紹介するとご案内しましたが、まず、放デイ事業所を立ち上げている方とはどのような方なのかを知っていただきたいと考え、予定を変更してお届けします。
「放課後等デイサービスを始めたい」代表的なご相談の4分類
それでは早速、ご相談の内容を分類してみましょう。
主観によるものですが、「放課後等デイサービスを開業したい」と考える方は、およそ以下の4つのグループに大別できると考えています。

社会貢献を主要な目的として放課後等デイサービスの開業を目指す層(Aグループ)
まず、社会貢献を目的に放課後等デイサービスの開業を目指すグループです。例えば、以下のような経緯で開業を志す方々です。
「当事者家族であり、子どものための場所をつくりたい」
「地域に障害児を見てくれる事業所がなくて困っているから、自分で事業所を立ち上げたい」
「特定の障害を有する子どもの受入先がない」
「支援学校で働いていたが、より深く子どもたちや家族を支援したい」
「学校の教員をしていたが、定年をきっかけに今までの経験を活かした仕事に挑戦したい」など
習い事や体験系コンテンツを提供したいという意向を持つ層(Bグループ)
次に、障害を持ったお子さんを対象に、習い事や体験系のコンテンツを提供したいという方達です。
「障害児に学習支援をしたい」
「障害児に運動支援をしたい」
「障害児にeスポーツで可能性を広げたい」
「障害児にダンスを教えたい」 など
といった明確なプログラムのイメージをお持ちの方々です。
隣接業種からの参入を目指す層(Cグループ)
3つ目は、すでに放課後等デイサービスと親和性の高い領域で事業所を営んでいる方々です。
「就労支援・生活介護を行っているが、子どもの分野から支援したい」
「整骨院を運営しているが、これから整骨院の業界は厳しくなるからこれを足掛かりに別の事業を始めたい」
「訪問介護や通所介護などを行っているが、新たな経営の柱がほしい」
「フリースクールを営んでいるが、放課後等デイサービスに転換したい」
「学童保育を営んでいるが、放課後等デイサービスに転換したい」 などといったご相談でいらっしゃる方々です。
異業種からの参入・営利目的での参入を目指す層(Dグループ)
最後は、放課後等デイサービス事業のマーケットに魅力を感じ、参入を目指している層です。
「フランチャイズの説明会に行って儲かると聞いた」
「知り合いから儲かると聞いた」
「現在の事業とは別に、安定した事業を持っておきたい」
「何か儲かることないか調べていたら放課後等デイサービスに行きついた」
といった方々です。
経営者のタイプ別に考える強みとつまずきがちなポイント
それでは、各グループの傾向や懸念点についてそれぞれ考察してみます。
まず、Aグループについてです。
事業所の強み:Aグループ
- 「子どもたち、家族のために」という真っ直ぐな想いが経営判断の軸となっており、子どもや家族、地域の方々にとって安心出来る場所になりやすい。
- 集客活動を行わなくても、保護者の方に必要とされる。結果として利用者が安定して確保できている事業所が多い。
- 経営者の「想い」が明確であり、従業員の離職率が低い。
つまずきポイント:Aグループ
- 「子どもたち、保護者のために」という想いが強い分、利用者家族や地域の要望を何でも受け入れてしまい、経営者や従業員が余裕をなくしてしまいがち。
- 経営の経験が無いことが多く、法令等の知識を補う必要がある。良い専門家等に出会わなければ、事業所運営が困難になってしまいがち。
事業所の強み:Bグループ
次に、習い事・体験系コンテンツの提供など、事業所コンセプトを明確にしているBグループについてです。
- 障害特性により、塾や習い事にいけない子どもたちにとっては、良い場所となる。
- 事業所の取り組みが明確で保護者に伝わりやすく、集客につながりやすい。
- プログラムによって目に見える成功体験を積みやすく、子どもと保護者が可能性を感じることができる。
- 習い事感覚で通所できるので、通所のハードルが低く、不登校の子どもたちが外に出るきっかけにもなる。
つまずきポイント:Bグループ
- 習い事としての要素が強いため、週1,2回の利用が多くなり、契約者数が通常の放課後等デイサービス事業所比で3,4倍必要となる。管理をすることが大変。
- 多くの場合、放課後等デイサービスで本来求められる療育ではなく、学習支援や運動支援等の取り組みが中心になってしまうため、放課後等デイサービスの制度に合わせるのが難しい。
- インクルーシブ教育を推進する施策から、一般の学習塾や習い事教室でも、障害児を受け入れ始めているため、放課後等デイサービスに通所させる意義が薄らいでいる。
- 2024年度の法改正の内容は、習い事中心の放課後等デイサービスにとって厳しいものであり、運営の見直しに迫られている。
事業所の強み:Cグループ
隣接業種から参入するパターンにうつりましょう。
- 経験・実績を活かし、比較的スムーズに事業所運営ができる。
- 地域での知名度もあるため、他と比べて集客がしやすい。
つまずきポイント:Cグループ
- 成人を対象とした障害福祉サービスや高齢者介護のサービスの制度に慣れてしまっている分、放課後等デイサービス制度の理解に時間を要する場合がある。
- 異なる事業を複数持つことになるため、経営者一人では、それぞれの事業を円滑に進めにくい。経営者とは別にマネジャーとなりうる人材や各事業所で核となる従業員を育成する必要がある。
最後に営利を最大の目的として異業種等からの参入を目指すDグループについてです。
事業所の強み:Dグループ
- 業界の慣例や枠組みに染まっていない分、新規性が高かったり画期的であったりするサービスを生み出したり、新たな集客方法を生み出す事業所が多い。
- フランチャイズのネームバリューやノウハウを生かせば、成功する確率が上がる。
つまずきポイント:Dグループ
- 最初の2,3年間は上手くいくことが多いが、放課後等デイサービスへの想い入れがないため、法改正に耐えられなかったり、自身が現場に入らない・入れなかったりすることから現場トラブルが多くなりがちになる。
- 想定したほどの利益が出ずに、事業から撤退する割合が他のグループと比べて多い。
- 経営者に子どもや障害に対する理解、療育の知識や経験がないため、現場と大きな溝が生まれやすい。
- 経営者の力が強すぎると職員は離職し、現場の力が強いと経営者によるコントロールが効かなくなり運営が困難になる。
- フランチャイズのノウハウはすべての事業所、地域で通用するわけではない。通用しない場合は、立て直しが難しい。
10年以上存続する事業経営者には共通する信念がある
いかがでしょうか。ここまで、経営者のタイプを別にコメントをさせていただきました。
もちろん、一つ一つの事例を深堀していけば、活かすべき強みも、乗り越えなくてはならない課題も違った内容になるでしょう。
本稿の内容は、あくまで傾向として参考にしていただければと思います。一つ一つの事例や課題の深堀については、次回以降にお伝えできればと思います。
また、今回はわかりやすい表現を優先してグループ分けしましたが、そこに優劣があるわけではありません。それぞれに事業所運営を軌道に乗せて成功した事業所、上手くいかずに失敗してしまった事業所があります。
「想い」の強さだけでも、「儲け」に意識が傾きすぎても、安定した事業所運営を継続することはできません。
10年以上事業所を運営している経営者や複数の事業所を安定して運営している経営者には共通した考えがあります。
それは「放課後等デイサービスを運営することは、自分にとっての社会的使命である」と考えていることです。
この使命感は、思いもよらない法改正があっても、従業員とのトラブルがあっても、それを乗り越える大きな力になっているようです。
弊社のクライアントにも、「儲けるため」に放課後等デイサービスを始めた方は多くいらっしゃいますが、事業所を運営していくなかで使命感が生まれ、子どもたち、保護者、地域にとって必要不可欠な事業所となっているところも存在しています。
それはきっと、ご自身の「社会的使命」を感じているからではないでしょうか。
次回は、介護事業から重症心身障がい児対象の放課後等デイサービス事業に進出した事例について、その社会的使命に触れつつご紹介したいと思います。