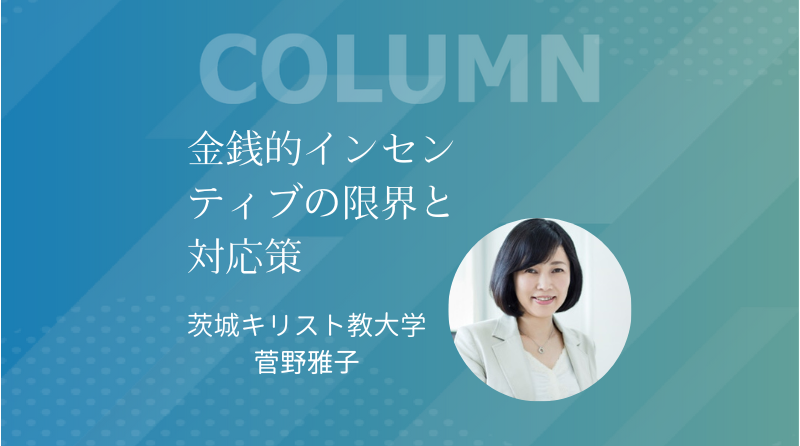この連載では、介護事業所におけるキャリアパスの諸制度について、その実態や効果について検討してきました。今回が最終回です。
最終回の今回は、金銭的インセンティブの限界とその対応策について考えてみたいと思います。他者への貢献や良好な人間関係などが働く動機付けになっているような場合、成果型報酬や昇給・昇格のようなインセンティブをちらつかせることが有効でないこともあります。どのような施策が介護職員の定着やキャリアアップにつながるのでしょうか。
*これまでの記事(キャリアアップ制度とその効用、人材マネジメント)はこちら
賃金はどんな仕事においても中核的な動機付け要因に
賃金という金銭的インセンティブが、働く人の中核的な動機付け要因であることは言うまでもありません。例えば筆者は大学卒業以来ずっと何らかの仕事をしていますが、なぜ働くのかと言えば、「生活するのに必要なお金を得るため」というのが最も大きな要因です。
もちろん、働く動機はお金のためだけではありません。例えば、今の大学教員の仕事で言えば、学生の成長が感じられると仕事へのやりがいを感じますし、授業評価で前向きなコメントが書かれているとやはり嬉しくなりもっと頑張ろうという気持ちになります。研究で新たな発見があると、心躍るようなワクワク感がみなぎってくるのを感じます。
しかし、やりがいがあるからと言って、賃金は上がらなくてもいいとは思いません。やはり昇給や賞与があると、改めて「仕事を頑張ろう、頑張り続けよう」という気持ちになります。
どんな仕事でも妥当な賃金水準の確保は労働への動機付けとして中核的なものであるということを、前提としてまず確認しておきたいと思います。
介護職のようなヒューマンサービス職では多くの人が非金銭的インセンティブを重視
一方で、非金銭的インセンティブが仕事への動機付けに大きな影響を与えることもまた事実です。とりわけ医療や介護等のヒューマンサービス専門職は、仕事のやりがい、他者への貢献、良好な人間関係、自己成長などの非金銭的インセンティブを重視する人が多いことが指摘されています。賃金の動機付け効果についての研究結果は一貫性がないものとなっていますが、上述したような非金銭的インセンティブは多くの研究でその重要性が指摘されています。
それを踏まえると、賃金をいくら改善しても、働きやすさや働きがいにつながる非金銭的インセンティブを改善しなければ、生産性向上や離職防止につながらない可能性があることにも留意する必要があります。
金銭的インセンティブの限界に留意―成果型報酬がモチベーションを低下させることも
もう一つ、私たちは金銭的インセンティブの限界も理解しておく必要があります。前回のコラムでも紹介しましたように、経済学や心理学の分野では、金銭的インセンティブが逆に動機付けを阻害する要因になることが、クラウディング・アウト効果(またはアンダーマイニング効果)として指摘されています。
例えば、仕事に喜びを感じ満足して仕事をしているのに、そこに成果型報酬や昇給・昇格をちらつかせるなど金銭的インセンティブが絡められると、まるで自分がお金のために働いているかのように感じてしまい、返ってモチベーションが下がってしまうというようなケースです。とくに内発的動機付けに強く支えられている職業の場合、こうした現象は強く表れる可能性があります。
また別の問題として、賃金が介護報酬(社会保険料と税金)という公的資金に制約を受けている現状に鑑みると、どこまで賃金を上げ続けることができるのかという点も、広く議論が必要になってきます。
非金銭的インセンティブとして「健康への配慮」
非営利組織の研究では、こうした金銭的インセンティブの限界に対して、非金銭的インセンティブの重要性が強調されています1)。その中でもとくに大きな効果が期待されるものとして、「健康への配慮」があります。組織が従業員の健康に配慮していることを示すことによって、従業員の潜在的な離職リスクを軽減することができるとされています。
介護労働実態調査(労働者調査)(介護労働安定センター)2)によれば、働く人の労働条件等の悩みとして「人手が足りない」(52.1%)、「仕事内容のわりに賃金が低い」(41.4%)のほかに、「身体的負担が大きい」(29.8%)、「健康面の不安がある」(29.0%)、「精神的にきつい」(26.8%)、「有給休暇が取りにくい」(26.2%)、「休憩が取りにくい」(22.6%)など、多忙で心身への負荷が高い状況がうかがわれます。
リソースが十分とはいえず多忙であるというのは、ヒューマンサービス専門職の特徴とされています3)。多忙が続くとイライラすることも多くなり、職場の人間関係もピリピリしたものになってしまいます。
一日の中での休憩時間の確保、悩みなどに対する相談援助、十分な休息が取れるような休みの確保や残業時間の削減、有給休暇が取りやすい職場環境づくりなど、心と身体を休めてリフレッシュできるような環境整備は、重要なインセンティブ施策になると考えられます。
労働時間に着目した労働条件改善は人材確保効果を高める
介護労働の特性からも、上述したような労働時間に着目した施策は有効だと考えられます。筆者が介護労働実態調査(労働者調査)のデータより介護職員と訪問介護員のサンプルのみを抽出して再集計したところ4)、前職を結婚・妊娠・出産・育児や介護等のライフイベントの理由で離職した人が2割弱となっていました。とりわけ訪問介護員ではその傾向が強いようです。また、再就職の際に、賃金よりも通勤の利便性や労働時間が自分に合っているかを重視する人が多いのも特徴的です。女性比率が多い業界なので、そのような傾向になるものと考えられます。
こうしたデータを踏まえると、仕事と育児介護との両立支援、時間外労働削減、柔軟な働き方を可能とする仕組み作り等を含むワーク・ライフ・バランス(WLB)支援に力を入れることが、有力なインセンティブ施策になりうると考えられます。
こうした働き方改革に関する取り組みは政府も積極的に後押ししているため、くるみん、えるぼし、健康経営優良法人、WLBや生産性向上関連の賞・アワードなどにチャレンジすることも一考です。「賞をもらって以来、応募者が格段に増えた」という話を複数見聞きしたことがあり、高い宣伝効果が期待できるかもしれません。
仕事への肯定感ややりがいの土壌づくりへ
以上をまとめると、働く人の心身の健康配慮の面からも、就業ニーズへの対応の面からも、WLB支援を充実させることが人材確保に奏功する可能性が高いと考えられます。WLB支援の中身は、育児介護等との両立支援、時間外労働削減、休日休暇取得促進、労働時間の柔軟化など、働き方改革そのものとも言えます。
働き方改革を推進するためには、労働生産性を高める必要があります。今回の報酬改定においても、生産性向上に取り組むことが最重要かつ急務なテーマとして位置づけられています。生産性向上の成果を、休みの確保や時間削減として還元するという目標を掲げて取り組むことも、検討の余地があるのではないかと考えます。
日々の仕事に追われ疲れがたまり、日頃の業務を振り返ることもできないという状況が続けば、仕事の意義ややりがいの喪失にもつながりかねません。十分に休息しリフレッシュするとともに、日頃の仕事を客観的にリフレクションし、新たな活力がわいてくるような環境が整えられれば、自らの仕事への肯定感が高まり、やりがいや成長を感じことができる土壌が育まれるのではないでしょうか。
<参考文献>
1)Akingbola, K. (2015) Managing Human Resources for Nonprofits. Routledge.
2)介護労働安定センター(2023a)『令和4年度介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書』.
3)田尾雅夫(2001)『ヒューマン・サービスの経営: 超高齢社会を生き抜くために』白桃書房.
4)介護労働安定センター(2023b)『令和4年度介護労働実態調査特別編』
https://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/r4_tokubetsukikou.pdf