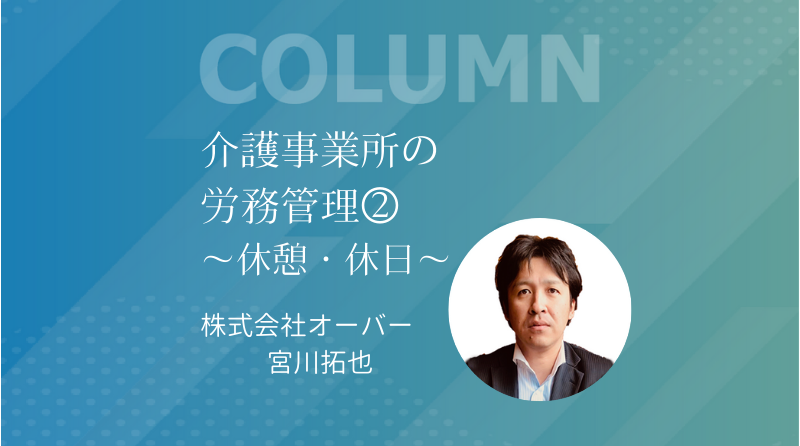前回の記事に続き、介護事業所における「働き方改革を戦略的に実践するポイント」について、お伝えします。第2回目は「働き方改革における労働時間のポイント②と休憩・休日のポイント」です。
なぜ、「労働時間」が重要なのか
私は社会保険労務士として、人事労務コンサルティングの場面で「労働時間」「賃金」「貢献」についてかなりの時間を要して検証します。
具体的には、「事業所としての経営的数値(売り上げ、利益)」と「賃金」の関係についての検証です。
それは、労働者にとって「賃金とは労働の対価」であり、経営者にとって「賃金とは貢献の対価」であるが故に、この部分のバランスがとても重要だからです。
介護事業所における人件費率(売り上げに占める人件費の割合)は60〜70%、中には80%近くの事業所もあり全産業の中では高くなっています。
例えば、訪問介護で、平均の報酬単価約5,000円/時間(身体介護や家事援助の単価を勘案した参考単価)を1日5件、1ヶ月22日とすると、1ヶ月の報酬が約55万円、この60〜70%ですから、33〜38万円が人件費であり、これには、会社の法定福利費等も含まれますので実質の支給額は25万円〜38万円となります。
介護事業所においては、定員や職員状況に応じて、報酬(売り上げ)について、上限(天井)があります。
その限られた条件の中で、責任、評価、実績、役職に応じた手当を振り分け賃金を構成していく必要があります。
それゆえ、報酬を生まない時間をスリム化する事、また工夫で削減できる割増賃金等をスリムにする事が原則となります。
また、「労働時間」の扱いは、人事労務トラブルにつながる可能性もあります。「サービス残業代」「未払い残業代」に関するご相談は依然多いのが現状です。ご相談の中には、意図的に払わなかったわけではなく、「知識として知らなかった」「そのような認識がなかった」という実態も見られます。
それゆえ、残業代に関する運用は理解し、誠実に行う必要がありますし、分かりやすい運用をおすすめしています。
「働き方改革」における労働時間のポイント②
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを法定労働時間と言います。これを超える労働については割増賃金を支払う必要があります。
例えば、時給1,200円の場合、割増分(0.25)は300円となり、法定労働時間を超過した時間は、時給1,500円となります。
割増賃金の支払いは、法律や自社の就業規則に準じて支払う必要がありますが、私は実務において、この超過労働時間について検証させていただきます。それは、仕事の内容がどうとか、態度がどうとかといったことではなく(この部分は事業所の方しか分かりませんから)、日々の労働時間の割り振りに改善できる部分はないかという事です。
例えば、次の事例をご覧ください。
例:
月 8:30 〜 17:30 休憩1時間 実労働 8時間
火 8:30 〜 17:30 休憩1時間 実労働 8時間
水 8:30 〜 18:30 休憩1時間 実労働 9時間 超過1時間
木 8:30 〜 17:30 休憩1時間 実労働 8時間
金 8:30 〜 17:30 休憩1時間 実労働 8時間
土 8:30 〜 12:30 休憩なし 実労働 4時間 超過4時間
日 休日
原則の労働時間運用の場合、水曜日の1時間、休日の土曜日に出勤した4時間について、割増賃金を支給する必要があります(法定労働時間 1週間40時間の事業場の場合)。
上記の例では、時給を1,200円とした場合、超過時間分の割増分が1,500円となっております。
割増分が月単位では、約6,000円、年間では、約7万2,000円(6,000円12カ月)となります。
このような状況において、私はその労働時間について検証します。
例えば、火曜日は、他の従業員の働き方の工夫により、午後は休んでもらえないだろうか等です。
※火曜日の労働時間を3時間にする。
その分を、他の労働時間に分配、つまりは、水曜日の労働時間を、そもそも9時間に、土曜日の労働時間を4時間分配することで、割増分の支払いを削減する労働時間運用です。
さらに、子育て中の従業員について、朝と夕方の勤務それぞれ30時間短縮し、その分を土曜日に分配する労働時間運用です。
私が支援させて頂く中で、「正職員、常勤は、1日8時間労働」が前提とされている事業所様が見られます。
後ほど、記述させていただきます「変形労働時間制」においては、1日の労働時間を8時間に固着する必要はありません。制度を活用する事で、フレキシブルなシフトを組むことができます。
パートタイマーは、限れられた時間で勤務するため、フレキシブルな勤務シフトが難しい部分があるかもしれませんが、正社員はフレキシブルな勤務シフトでの勤務を前提とする労働条件とすることも考えられます。
また、削減できる割増分を、手当や評価として分配する事や、他の人材の雇用に活用も可能です。
「変形労働時間制」の取り組み
変形労働時間制とは、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができます。導入には、就業規則への記載、行政機関への届出等が必要となります。
今回、介護事業所における「変形労働時間制」の活用で考えられる「1カ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」についてご紹介します。
(1)1カ月単位の変形労働時間制
1カ月単位の変形労働時間制は、1カ月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場(※1)は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えた労働、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えた労働が可能になる制度です。
※1 常時使⽤する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、 接客娯楽業
→例えば、月末月初の数日間は、月末締め業務、月初の請求業務があり、残業が発生する時期のため、その日の所定労働時間数を、1日10時間にし、月の中旬等を、1日7時間勤務等にするなどにより、1カ月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるようにする方法です。
(2)1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1カ月を超え、1年以内の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない事を条件として、業務に繁忙等に応じ労働時間を分配が可能になる制度です。
→例えば、夏期休暇時期等により、1日の稼働人員が手薄になる際に、あらかじめその時期の所定労働時間数を多くし、それ以外の時期の所定労働時間数を抑える事で、その期間の1週間の労働時間が40時間を超えないようにする方法です。
変形労働時間制は、「あらかじめ計画」する事で、原則の労働時間制より柔軟にシフト運営ができ、割増賃金を抑えることが可能となる制度です。この「あらかじめ計画」が重要となります。
従業員にとって、「この日は、何時から何時まで勤務すれば良いの?何時間勤務すれば良いの?」この部分について事前に計画し通知する必要があります。変形労働時間制という、不規則制を勘案しても当然と言えます。
多様な働き方の時代だからこそ労働時間マネジメント者の評価を
現在、働き方改革も相まり、多様な働き方が広がりを見せています。雇用の場合においても、多様な働き方に対応できる事業所と対応できない事業所では差が生じてきます。
だからこそ、多様な働き方を管理し運用する人材への評価も重要となります。
上記の変形労働時間制は、規定を盛り込めば良いもの、効果が出るものではありません。実務において、この労働時間制意図する事を理解しつつマネジメントする必要があります。
変形労働時制を導入しても、従業員にその思いが伝わらないまま、今まで変わらない労働(例えば、1日の所定労働時間数が6時間の場合で、今までと変わらず8時間勤務している等)が行われていなければ意味をなしません。
介護事業所において、労働時間をはじめとしたマネジメントの重要性が高まっています。
それゆえ、マネジメントを行う者への評価(何を根拠に、どの配分で評価する方が良いのか)についてもご相談が多くなっているのが現状です。
介護事業所における「休憩・休日」の取り組み
介護事業所における「休憩・休日」において、注意すべき事をご案内させていただきます。
労働基準法では、使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の途中に与え、自由に利用させなければなりません。
また、休憩は全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより一斉付与は適用除外となります。
また、休日は労働基準法において、労働基準法では、使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。
私が休憩、休日において、ご相談を多くいただく内容をご紹介いたします。
①「アルバイトやパートタイマーでも休憩時間を与えなければならないのか?」
→休憩には、正社員やアルバイト、パートタイマーという雇用形態を問いません。1日の労働時間が4時間、5時間という場合は、法令上休憩を付与する必要がないので、特に休憩を与えなくても問題ありません。しかし、アルバイトやパートタイマーの勤務時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩を与える必要があります。
②「1日5時間勤務のパートタイマーより、お昼の一斉休憩時間は給与が出ないから要らない。この従業員の希望を受け入れる必要はあるのか?」
→その時間に労働してもらえる事があるのであれば労働への対価ですから受けいれても良いですが、労働がないのに与える必要ありません。このような職場である事は雇用時に伝えておく必要があります。
職場で1つの例外を認めると、それが波及し事業所運営に支障が生じますので注意が必要です。
③「デイサービスで、自身の休憩時間は、利用者と一緒にご飯を食べ、見守りもしている。休憩時間には当たらないのでは?と言われた」
→休憩時間とみなされない可能性が高いので、休憩時間の運用(分散付与等)を再考する。
または、10時から13時の時間限定のアルバイト雇用する方法も考えられます。その時間の貢献価値を考慮し、他の時間帯より時給を上げ雇用することも考えられます。
④「事業所の営業日以外に働いた場合、休日労働になりますか?」
→休日労働になりません。事業所の営業時間と、労働者の労働時間は別です。ただし、就業規則等で、「事業所の営業日以外の労働については休日労働とし、手当を支給する」等のような規定がされていればそれに準ずる必要があります。また、その労働が結果として割増賃金支給対象となる労働の場合は、割増賃金の支払いが必要となります。
⑤「休日に研修に参加した場合、労働時間になりますか?」
→その研修が事業所からの強制、運営上必要不可欠な研修の場合労働時間になります。
また、仮に労働者の自主的な学びで研修に参加しており、それが事業所運営に貢献する要素が見られる場合、何らか評価することも重要です。前向きな姿勢に気づき、それを共有し、承認し、応援する姿勢はこれからの経営において効果的であると考えます。
事業所としてのありたい姿と、それに向けた取り組みがこれらの実践における会社の思いとして繋がり、“形式的ではない働き方改革”の実践において「労働時間」はその中軸を担うといっても過言ではありません。
働き方の多様化は、今後ますます進み、それに応じた運用ができる事業所づくりが求められます。
夢や目標に向かいがむしゃらに働く事で自己実現する者、家庭や自身の生活とのバランスを取り働く事で自己実現する者など、それぞれの思いを勘案した職場づくりです。
良い悪いではなく、そのような時代であることを理解しながら、重要な事は自社の思いに逆らった運用は、いずれ歪みが生じ、経営者の思いや目的を埋没させることです。
それゆえ、個別の誠実な対応は、経営という大きな舵取りの中での俯瞰的な視点でバランス感を持って対応する必要があります。
第3回目は、「働き方改革における労働時間のポイント③両立支援の取り組みと令和3年度助成金」をお届けします。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。