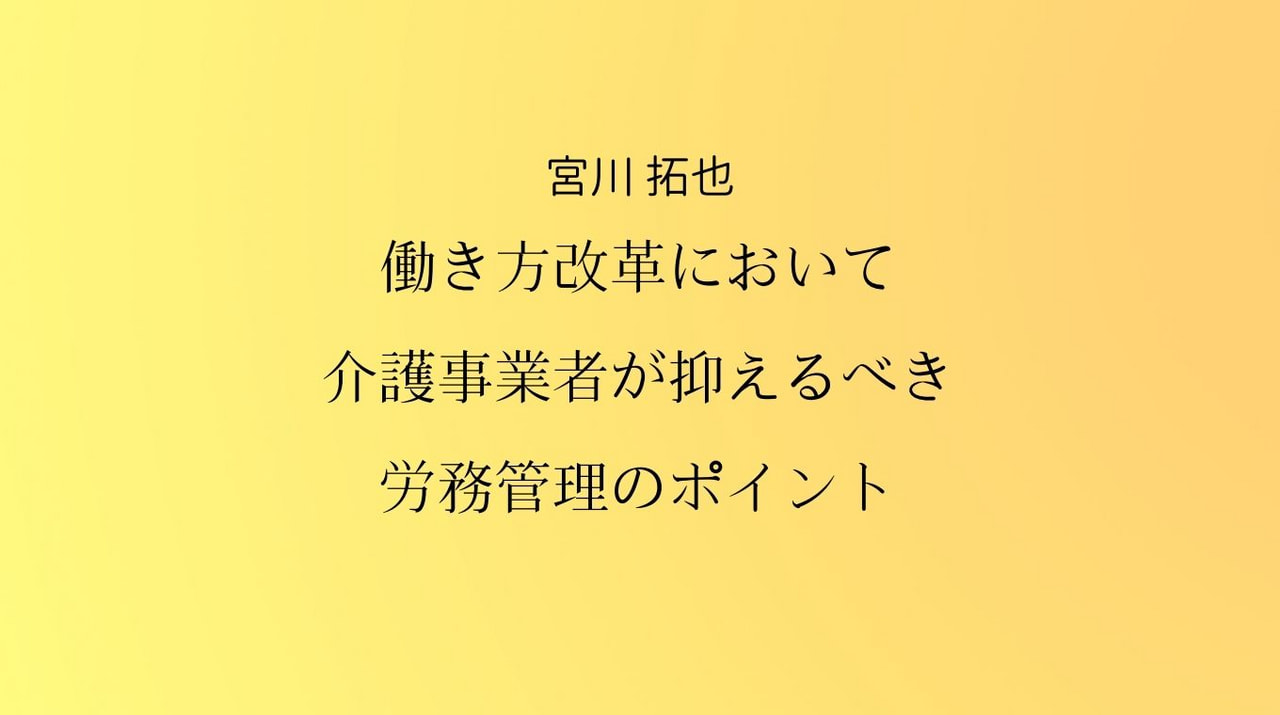現在、介護事業所における人事労務は、ターニングポイントを迎えています。
介護事業所の経営者であり社会保険労務士として仕事をしている筆者に、相談頂く事業所においても、ここ1年で飛躍した事業所と先行きが不透明になった事業所と分かれています。
コロナ という外的要因により数値的な部分での経営が難しくなられた事業所もありますが、労務側面では今までの人事労務課題が解決され、総じて発展された事業所があられます。
なぜ、コロナ禍で発展できたのか?
それは、戦略的に「働き方改革」を実行していることが理由にあげられます。
戦略なくして「働き方改革」の成功はない
「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革であり「同一労働同一賃金」や「兼業」「テレワーク」「長時間労働の抑制」「年次有給休暇の取得」等の関連法も施行されています。
筆者も多くの介護事業所様に「働き方改革」の支援をさせて頂いておりますが、介護事業所の「働き方改革」への最初の印象は、ネガティブです。
例えば、「分かっていますが・・」「先生、私たちの現場分かっておられるでしょ、弊社では難しいです。」慢性的な人材不足の業界であり、場合によっては、利用者の安全配慮義務を遵守できない状況に陥る事を想定しながら、事業運営を行っている事業所も見られます。
一方で、働き方改革への“意識”は高い傾向があります。それは、慢性的な人材不足の中、「働き方改革」が目指す職場の実現は、人材不足解消に向けた取り組むべき課題であると認識されているからです。
ただし、「働き方改革」は戦略なく、やみくもに取り組むことは危険です。
それは、管理者の負担が増大し、現場が疲弊する恐れを含んでいるからです。
安全に配慮できた事業運営を行うために、人的リソースを把握し、小さな事でも、実行可能なことから、計画的に一つひとつの積み重ねて前進させることが重要となります。
生き残る事業所における「働き方改革」の取り組み
今後、生き残る事業所なるためは、自他共に厳しく、そして柔軟に「働くことができる環境づくり」 に取り組む必要性があります。
そして、事業所が達成すべき目的に近づく為には、「働き方改革」という戦略が重要になります。
戦略とは、事業所が「進むべき方向」を示します。進むべき方向を実現するため具体的な手段が戦術です。
本シリーズでは、介護事業所における「働き方改革を戦略的に実践するポイント」について、お伝えしていきます。第1回目は「働き方改革における労働時間のポイント」です。
「働き方改革」における労働時間のポイント
著者は 必ずお聞きします。
「貴社にとって、働くとは何ですか?従業員に求める貢献とは何ですか?」
もちろん、企業によって回答は異なりますし、(社会的に逸脱したものでない限り)それぞれを私は受け取ります。
特に介護事業所において、この回答が重要となるからです。
そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間を示します。
ここでのポイントは、「使用者の指揮命令下」「使用者の明示又は黙示の指示」です。
労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などで定められた時間だけで判断されるものではなく、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと客観的に判断できるかどうかにより定まるものであると解されています。
例えば、翌日に開催されるサービス担当者会議の資料について、通常の業務時間内に作成できず、持ち帰り自宅で作成した場合は、労働時間となります。
その根拠は、労働時間か否かを判断する際、業務との関連性、そしてこの業務をせざる得ない状況かどうかを考慮する為です。
つまりは、事業所内での仕事のみが労働時間ではない事、使用者から明確な指示がない場合でも労働時間となる事はあります。
その上で重要なことがあります。このサービス担当者会議の資料の作成に要した労働時間ですが、「単なる残務としての労働時間」と扱うのか「自社が提供しているサービス、それにおける気づきを整理し、自社の質のアピールに繋げるため労働時間」と捉えるかによって価値は異なります。
それに応じた従業員への報酬を思考する、つまりは経営者の思いが伝わる人事労務と報酬のあり方です。
このような目的、目標、成果等の観点を盛り込んだ仕組み作りが、私が大切にしている、働き方改革における戦略的ポイントの1つです。
労働時間のルール
労働時間のルールについて簡単にまとめさせて頂きます。
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを法定労働時間と言います。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。これを法定休日と言います。
この法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結し、事業所を管轄する労働基準監督署長への届出が必要となります。
時間外労働には上限があり、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。また、やむを得ない事情により、この上限を超える場合、特別条項を締結することで、超えることができます。主なポイントは以下の通りです。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
・上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
・特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。
※引用:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
生き残る事業所における「労働時間」の取り組み
今、コロナ渦で飛躍された事業所に見られるのは、「経営者の思いを伝えておられること」、「多様な働き方について積極的に実践されておられる」ことです。
昨今において、従業員の労働への意識は多様化しています。それぞれの価値観、ライフスタイルに合わせた働き方を選択されます。それゆえ、労働時間=会社への貢献度(長く働いている者が会社に価値を提供している)、パートタイマー=補助業務者等の意識は埋没する必要があります。
例えば、○時から○時の時間帯に、従業員があと1名いてくれたら、従業員の負担の軽減、サービスの向上、売り上げの向上に繋がるのに・・・であれば、その時間帯に勤務いただく従業員への報酬を評価し、時間帯によって時給を変えることも有効です。
数年前に作成した就業規則、賃金規定に固着するがゆえに、人事労務運営において行き詰っておられる事業所もおられます。中には、就業規則の労働時間について、どこかの雛形をそのまま引用し、それに固着されている場合もあります。
結果として、無意識に残業時間が累積し、残業代が多くなられているケースも散見されます。これらを改善させて頂くと新規雇用できる資金に繋がるケースもあります。
事業運営には、ルールが重要です。しかし、そのルールは、現状と目指すべき目標に沿ったものである必要があります。人材で事業運営が大きく変わる業界だからこそ、「柔軟であれ 」が筆者 の思うところです。
「労働時間」の考え方が、他の制度に波及する
労働時間の考え方が、「同一労働同一賃金」や「兼業」「テレワーク」「長時間労働の抑制」「年次有給休暇の取得」等の働き方改革への実践に繋がります。「労働時間」について、ありたい姿と、それに向けた取り組みがこれらの実践における会社の思いとして繋がり、“形式的ではない働き方改革”に繋がります。
また本稿の最後に、長時間労働=悪ではありません。私自身も施設で勤務している時、感染症により多くの従業員が就業禁止になり、少数の職員で事態を乗り越えました。介護事業所において、このような事態は想定されることです。実際に残業や休日労働も多くなり疲弊しましたが、その際、経営者より、従業員1人1人に、「ありがとう、あなたのおかげで助かったわ」と言っていただいたことで、その後の働き方が変わりました。介護事業所を運営する者において、このような気遣いが人事労務においては非常に大切で、何よりもの報酬に繋がること大切にして頂きたく思います。
第2回目は、「働き方改革における労働時間のポイント②と休憩・休日のポイント」をお届けします。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。