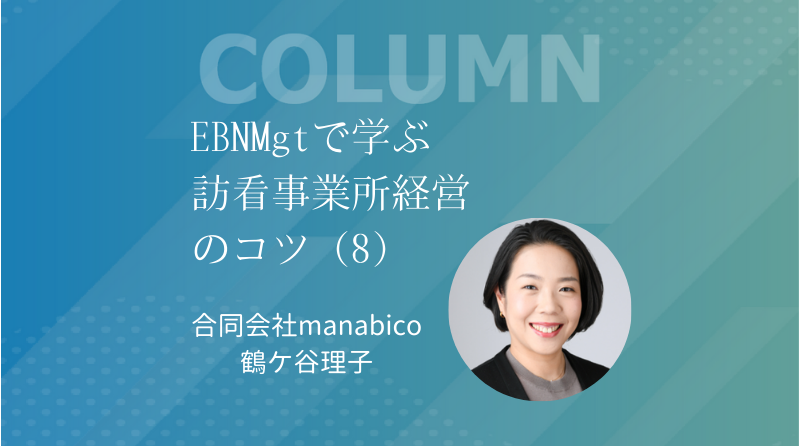前回は訪問看護ステーションにおけるスタッフの育成手法としての「1on1」とはどういうものなのか、そして1on1で効果的にスタッフを育成するために管理者が気をつけるべきポイントをご紹介しました。
今回は具体的な事例をもとに、より効果的にスタッフ育成に活かす1on1を管理者が実施するための3つのステップについて解説していきます。
<ケース>どうやって新入職の訪問看護師を育てていけばいいの⁈―訪問看護管理者の悩み
主人公は連載の4回目と6回目にも登場している新任の訪問看護管理者・山代さんです。彼女は、忙しさのあまり情報共有がまったく行われていない訪問看護ステーションに着任したばかりです。今回は、山代さんが管理者を務めるステーションに待望の新入職看護師が配属され、1カ月が経過した時点のお話です。このステーションでは、入職後1カ月を教育期間として同行訪問を組んでいます。
1カ月が終了した今、山代さんはスタッフの育成を今後どのように進めていけばよいか悩みを抱えています。
待望の看護師の配属。そして
ステーションの忙しさは相変わらず。で、スタッフ全員で行うミーティングも月に1回取れるかどうかという状況がは継続していた。しかし、山代はスタッフの訪問の合間に一人一人と面談の時間をできるだけ持つようにしていた。
新入職の看護師である川上は3年の病棟勤務の経験後、山代が管理者を務めるステーションに配属になった。会社規定で決まっている1カ月の同行訪問期間がおわり、川上が新規利用者への訪問を除いて一人で訪問に行くようになったのは先週からのことであった。同行訪問期間中のはすぐにアドバイスやフォローすることが可能であったが、もうそういったことはできない。そこで、川上とは週1での面談を設定している。山代はまだまだ川上に訪問において注意して欲しいことがあったが、この面談を利用して川上への注意をこの面談でどのように伝えていくかに悩んでいた。
新入職看護師との1on1
山代「川上さん、お疲れさま。来月からオンコールも始まるけど、ひとり立ちしてみてどうかしら?」
川上「オンコールは、まだちょっと怖いです。ターミナルの方や今まで経験のない疾患の方も徐々に増えてきてますし、私一人では対応できるか不安です」
山代「そんなこと言っていたらいつまで経っても一人前の訪問看護師になれないじゃない。他のスタッフからも山上さんは以前に比べて成長してるって聞いてるし、私たちもセカンドコールでフォローするから大丈夫よ。あと、今日の訪問はどうだった?阿部さん(*川上が担当している利用者)、前回はご機嫌が悪くて入浴介助拒否されたみたいだけど、今日は入れた?」
川上「今日もダメでした。もう1カ月くらいお風呂も入ってないですし、入って欲しかったのですが・・・。ご本人は『一人で入ってる』って言って」
山代「え、今日も入れなかったの!?足浴とか清拭はしたの?」
川上「してません」
山代「阿部さんは認知症の症状でケアの拒否があるのは分かるけど・・・。糖尿病もあるし皮膚とかの状態確認はしないとダメでしょ。ちゃんとアセスメントはできてる?寄り添う看護がしたいって言っていたけど、寄り添うって仲良しこよしをすることじゃないし、訪問看護師としてお金をもらって入っている意味を分かってる?」
川上「・・・自分では分かっているつもりです・・・」
山代「次回からは看護師としてちゃんとアセスメントして介入しなきゃだめよ」
川上「分かりました。次の訪問があるので行きます。ありがとうございました。」
面談の最後は重苦しい雰囲気になってしまった。
川上は次の訪問が組んであったため急いで事務所を出発した。
果たして、面談はこのやり方でよいのだろうか。もっとよい働きかけを川上に対してできたのではないだろうか。山代は不安を感じながらも事務作業に取り掛かった。
育成を目的とした1on1で管理者が踏むべき3つのステップ
川上さんとの面談を週一で設定したことは、スタッフ育成の第一歩として素晴らしいことです。しかし、効果的に行われたかどうかについては疑問が生じています。山代さんが川上さんと行った1on1は形式上「定期的に管理者とスタッフの間で行われる一対一の対話」となっていますが、山代さんが一方的に話すばかりで信頼関係は構築されず、スタッフの育成という目的を達成していません。
山代さんの対応を振り返りながら、「1on1で管理者がすべき3つのステップ」をご紹介します。

(1)信頼関係を構築する
信頼関係を構築するには相手の話に耳を傾ける”傾聴”と話してくれた内容を”肯定的に受け止める配慮”が必要です。山代さんは川上さんの話を遮ってしまい、自分の意見を述べてしまいました。たとえその意見が正しいものであったとしても、これでは川上さんはなかなか受け入れられません。日頃からステーションで「心理的安全性」を構築しておくことも大切です。
(2)学びを深化させる
オンコールに川上さんが不安を感じていることは事実なので、山代さんには「まだちょっと怖い」という考えの理由を、もっと確認する必要がありました。1on1はスタッフの抱える問題の解決とスタッフの成長のための時間です。何が不安なのか問いかけることで、川上さん自身にその不安を乗り越えるには何かを考えてもらえるようにできると良いでしょう(コーチング)。その上で、具体的にこうすれば良い、という指導をしてもいいでしょうし(ティーチング)、直す必要のあることをしっかりと伝えることもいいでしょう(フィードバック)。
(3)次の行動の決定をうながす
面談の最後が重苦しい雰囲気になってしまい、山代さんは川上さんの次の行動の決定をうながすことができませんでした。
阿部さんへの次回訪問では、どういうコミュニケーションをして、こんな対応をします、といった具体的な行動決定を川上さんにうながすことができれば、川上さんの抱える問題解決と成長を支援することができたでしょう。
まとめ:管理者自身がスタッフとの1on1を振り返るための4つの問いかけ
川上さんとの1on1後に山代さんは「これでよかったのだろうか」と悩んでいます。自分自身の1on1を振り返るというのは難しいことです。連載の1回目と2回目では経験や勘に頼らない問題解決の手法としてGRPIモデルをご紹介しました。このGRPIモデルを下敷きとして、管理者自身がスタッフとの1on1を振り返るための4つの問いかけが以下になります。ご自身の1on1の振り返りにご活用ください。

次回は、訪問看護管理者としてどのように振る舞えばよいか悩んでいる方に役立つ、リーダーシップ理論をご紹介します。
参考文献
本間浩輔(2017)『ヤフーの1on1−部下を成長させるコミュニケーションの技法』,ダイヤモンド社
松尾睦(2011)『職場が生きる人が育つ「経験学習」入門』,ダイヤモンド社
松尾睦(2015)『「経験学習」ケーススタディ』,ダイヤモンド社
中原淳(2017)『はじめてのリーダーのための実践!フィードバック』,株式会社PHP研究所