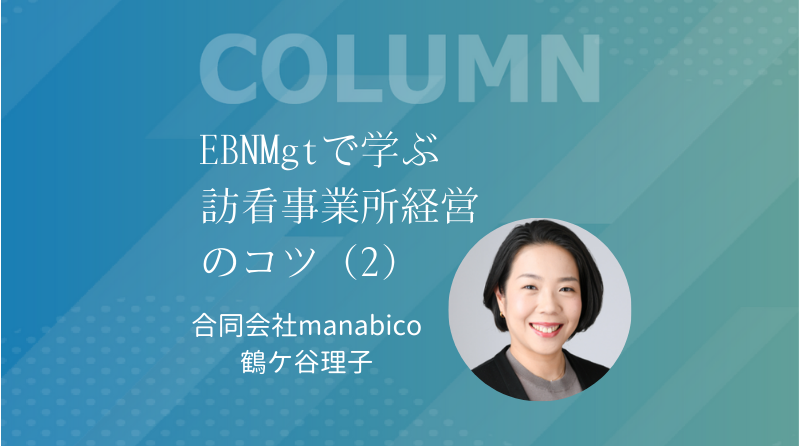前回は、訪問看護ステーションで良く起こるスタッフ間の仲違いや雰囲気の悪さの解決のために役立つステーションの状態を診断するツール『GRPI(グリッピィ)モデル』をご紹介しました。
今回はその具体的な事例を挙げて、これをどのように活用するかについて解説していきます。以下はある訪問看護ステーションの管理者とスタッフの会話例です。ぜひその様子を頭に思い浮かべながらお読みください。訪問看護管理者の西川と看護師の田中の会話が行われています。ベテラン看護師の田中が話題のようです。
<ケース>“訪問看護管理者西川の苦悩”
訪問看護管理者の西川が事務所の扉を開けると、入れ替わりにベテラン看護師の田中が訪問に出かけた。事務所の中では看護師の中村が真っ赤な顔をして仁王立ちしていた。パート看護師は気まずそうな表情でそそくさと退勤していった。

中村「西川さん、田中さんをどうにかしてください。普段は自分の方がベテランだからって威張ってるくせに都合の良い時だけ『自分は歳でパソコンの入力は若い人の方が早いから』って計画書の入力とか押し付けてくるんですよ。西川さんからも田中さんに注意してくださいよ。先月だって報告書が終わらなくて残業続きだって言うからいくつか代わりに入力してあげたら、内容にケチつけて文句まで言うんですよ。じゃあ、自分で最初からやってくださいって思います。私だってまだ訪問看護始めて1年で、どうやって新規の人を受け入れるかとか営業はどうするかとか、病院との連携とか色々まだ分からないことばっかりなのに」
西川「最近は利用者さんが増えてきて売上目標がようやく達成できそうなの。でもそのせいで、私も契約とかサービス担当者会議とかで、ちゃんと中村さんのフォローできてなくてごめんなさいね。田中さんも確かに事務作業は苦手だけど、最近は緊急対応もやってくれてるし訪問が忙しいって言うのはしょうがないのよ。チームなんだから、みんなでフォローしあってやっていきましょうよ」

中村「売上、売上って・・・うちの訪問看護ステーションは何をしたいんですか?それに、自分のことしか考えてないような人とはチームなんかできません」
西川「何がしたいって・・・もちろん利用者の在宅生活の継続のために訪問看護しているんじゃない。売上目標は降ってくるものだもの。私だって大変なのよ」
スタッフ間の仲違いに4つの問いからアプローチ
このケースのようなスタッフ間の仲違い、そこから来る雰囲気の悪さは、残念ながら訪問看護ステーションでは良く見かけられる問題です。では、西川は良いチームを作っていくためにどのようにアプローチしていくべきでしょうか?
GRPIモデルの4つの問いを用いてこのステーションの状態改善に取り組んでいってみましょう。
1.チームの「Goal(目的)」は明確になっているか?
まず何よりもチーム内で自分たちが「何のために訪問看護を行うのか」、「どのような看護がしたいのか」という共通の目的・目標を明確にすることが肝心です。もちろん「専門看護師を取りたい」や「無理ない範囲で家庭と両立したい」等、一人一人の目標や目的は異なると思います。それでも、チームとして「地域で1番のステーションになる」であったり「在宅看取りと言えば名前が浮かんでくるステーションになる」といったり等の目的・目標を全員で共有する機会を持ちましょう。
そして、売上目標についてもスタッフ全員に納得してもらい、その達成に向けて動いてもらえるようにしなくてはなりません。
時折「看護師に売上のことは話しません」という管理者さんに出会います。自分たちが訪問看護を提供し続けるためにはこれだけの売上が必要だということをとことん説明して「一緒に頑張ろう」と思ってもらうことが重要です。
2.チームの「Roles(役割)」は明確になっているか?
ここから説明する「役割」と、次に説明する「段取り」の明確化については、特にステーションが大きくなる段階で必要となることが多いように感じます。
それでは、「役割」の明確化についてアプローチの仕方を確認してみましょう。
西川のステーションでは、現場で信頼の厚いベテラン看護師の田中と、訪問看護師としては駆け出しだがPC入力が得意で周囲のフォローができる中村というそれぞれの特性に合わせた役割分担ができていなかったため、中村は不公平感や不満を感じていました。
訪問看護においては、病棟看護以上に事務作業や多職種との連携等の直接的な看護ケア以外の業務が多数あります。
例えば、訪問ルート作成をする時には、看護師の能力や利用者・家族との相性等の様々な特性を考慮して担当を割り振っているのではないでしょうか。
同様に、日々の業務全体を円滑に進めるために看護だけでなく周辺業務の能力も含めて働く人それぞれの特性を活かせるような役割分担をする必要があります。チームでとことん話し合って役割分担を決めると、お互いにフォローしあってチームとしての業務を進めていけるようになります。
3.チームの「Process(段取り)」が明確になっているか?
続いて、「段取り」を明確にするステップに進みます。看護ケアはエビデンスベースドナーシングという考え方に基づいており、「なぜその看護をするのか」を言語化して共有することに疑問は無いと思います。
しかし、例えば営業や新規受け入れの手順といった周辺業務になるとどうでしょうか?手順が明確になっていない事業所も多いようですが、業務の段取りについて手順書を作成しておくと良いでしょう。 簡単でも構いません。
手順書の作成は、新人看護師の教育の役に立つだけではなく、作成時にスタッフ間での段取りや認識の違いが明確になるという点でも有用です。
明らかになった違いについてチームで話し合い、ステーションとして統一の手順書を作成する過程を通じて、業務の進め方の違いが元で起こる衝突を減らすことができます。
4.チームの「Interpersonal Relationship(人間関係)」は良好か?
以上に挙げた3つの問いについて全て確認した上で、人間関係についても手立てをとっていくと良いでしょう。 人間関係の悪さが問題になっている場合でも、よくよく原因を考えていくと、実はそのステーションの目的が不明確で、役割分担がなされておらず、業務の段取りも曖昧である、ということが非常に多いのです 。
皆さんもGRPI(グリッピィ)モデルの視点を活用し、組織のマネジメントに役立てていただけましたら幸いです。
次回は、スタッフの動機付けをどのように行えばよいのかについて、動機付け理論の古典であるハーズバーグの『二要因理論』をご紹介いたします。