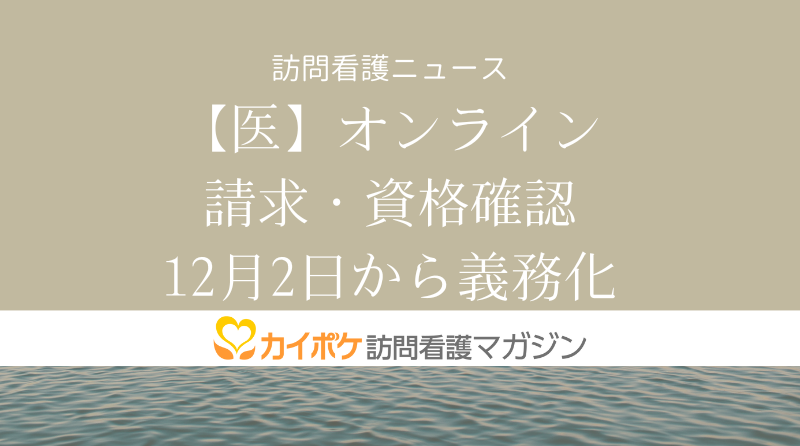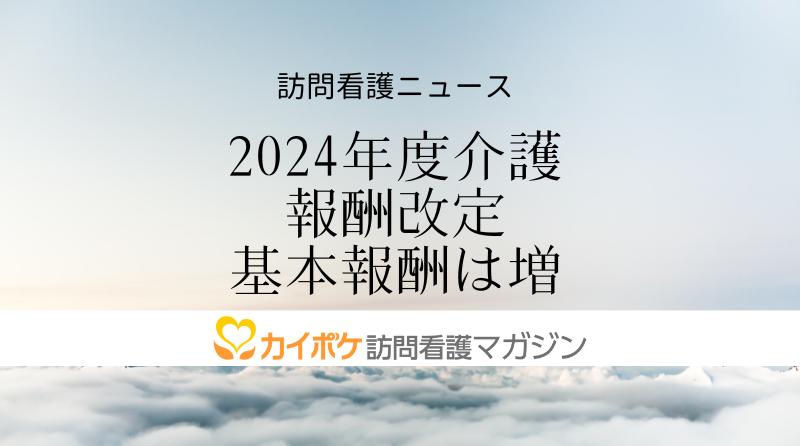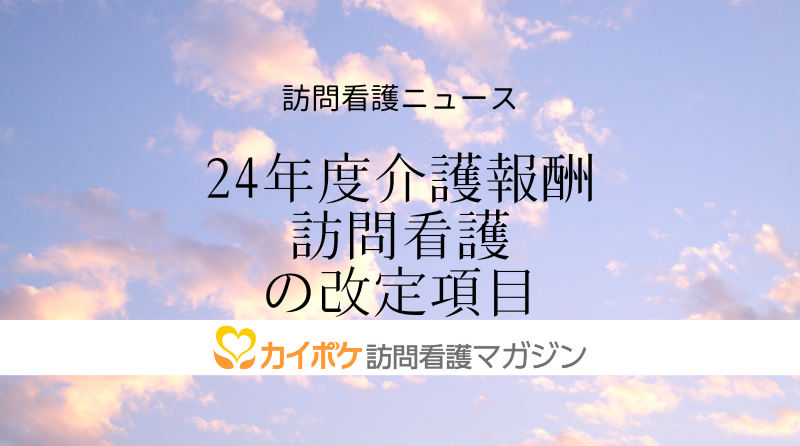前回は「風通しの良い」職場の鍵となる心理的安全性とはどういうものか、そして心理的安全性を高めるために管理者が取り組むべき手順についてご紹介しました。今回は具体的な事例を用いて、自ステーションの心理的安全性が低いとどのようなことが起きるのか、そして心理的安全性を高めていくにはどうすればよいかについて解説していきます。
スタッフから医療事故の報告がない!…管理者としてどうする?
今回取り上げるのは、ある訪問看護ステーションの新任管理者として着任した山代さんが、自分の着任前に起きていた医療事故についてケアマネからの問い合わせで気がついた事例です。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、山代さんは前々回で取り上げたケースの主人公でもあり、今回はその続編にもなります。もしもあなたが山代さんの立場であったなら、どのように対応するかを考えながら読んでみてください。
<ケース> “報告されなかった医療事故―新任訪問看護管理者山代さんの奮闘―”
着任後のステーションの状況
前任の管理者のどんな依頼であっても断らないという方針が地域に浸透していたおかげで、連携しているケアマネジャーや医師からの依頼はひっきりなしだった。依頼内容は、他ステーションから断られた困難ケースや土日を含む急な訪問開始等のケースが多く、スタッフたちが疲労と不満を溜めていたことは着任間もない山代から見ても明らかだった。
また、新型感染症の流行や忙しさを理由にスタッフ全員が揃って行うカンファレンスやミーティングはこの1年間全く行なっていないようだった。そのため、ステーション内での共有事項についてスタッフの誰かが「聞いて無い」と言うのは日常茶飯事であった。
スタッフたちの様子立ち上げ時からの唯一残っているベテランの高見は、必要な時のみ山代に声をかけてくるくらいで、それ以外は挨拶も無く訪問のために事務所を出入りしていた。
昨年入社した常勤の鈴木とパートの石原は愛想も良く、異動してきたばかりの山代に気を遣っている様子が見受けられた。2人は仲が良いようだが、更衣室等でコソコソと話していることが多く、高見とは必要最低限しか話していない様子が見られた。
山代が着任して1週間ほど経ったある日、ケアマネから「先日、訪問看護の際に起こった事故について、どの後の対応がどうなったか聞きたい」と電話があった。山代は前任の管理者からもスタッフの誰からもその事故について聞いていなかった。急いで事故報告書のファイル内の記録を探したが、ファイルに挟まっていたのは事故報告書の書き方フォーマットのみであとは何も無かった。
そこでまず、一番に帰ってきた高見に事故のことを聞いたが知らないとのことだった。
次に帰ってきた鈴木と石原に聞いたが、モゴモゴとして明確な返答は得られなかった。よくよく聞き出してみると、石原が訪問時に些細なヒヤリハットを起こしてしまったが利用者が大丈夫と言っていたため、鈴木と相談して誰にも報告していなかったということだった。
今回、たまたま利用者からケアマネジャーがその事故について聞いて、ステーションに電話をかけてきたから発覚したのだった。石原は前任管理者や高見から怒られるのが怖く言い出せなかったと泣き出してしまった。
医療事故の報告が適切に行われる体制を構築するために新任管理者が検討すべきこと
山代さんは何よりもまず、発覚した医療事故について適切な対応をすることが必要です。加えて長期的に見れば、このような医療事故が起きないようにする取り組みと、起きた場合にはすぐに報告が行われる体制を構築しなくてはなりません。その際、鍵となるのが心理的安全性です。
ケースの状況を心理的安全性のある訪問看護ステーションの7つ特徴から解き明かす
山代さんが着任した時のステーションの問題点は、ヒヤリハットを報告したことで叱責されるのでは無いかという不安から報告や情報共有がされていない状況であったということが分かります。また、そもそもスタッフ間のコミュニケーションもほぼ皆無であったため今回のような事故報告だけではなく利用者に関する日常的な状態変化やケア、時間の変更等についても情報共有に抜け漏れがあったことも容易に想像できます。
前回ご紹介した心理的安全性のある訪問看護ステーションの7つの特徴に当てはめてみると、鈴木と石原にとってこのステーションの心理的安全性は確保されていなかったと言えるでしょう。

特に、
1. ミスをしても咎められない
2. 分からない時、困っている時に支援を求められる
3. 問題や課題だと思うことを率直に意見できる環境
については、全く備わっていなかったことがわかります。
職場に心理的安全性を作るために山代さんはどのように動くべきか
このステーションに心理的安全性を生み出すために、山代さんがやるべきことを「心理的安全性を作る3Steps」としてご紹介します。

(1)土台を作る
まずは、山代さんからスタッフ全員に繰り返し「訪問看護という意義深い仕事を行う上で、率直に意見を話すことは看護の質向上や事故予防において欠かせない業務の一部である」ということを伝えて、共通認識を持ってもらいます。
(2)参加を求める
土台を作ったら次は、率直な発言の実践の場を作って参加を促します。まずは月1回でも構わないので定期的に全員が参加するミーティングの開催をスケジューリングします。また「この会議では必ず1人一回は率直な発言をする」や「疑問や提案はしても良いか、批判はしない」等、安心して発言するためのルールを共有するようにします。また、ルールだけではなく山代さん自ら自分も知らないことがあるから教えてほしいという姿勢を示し、率直な発言を引き出し広げたり深めたりするために「どういう状況でしたか?」等と質問を知るとより話しやすくなります。
(3)生産的に対応する
最後に、いくら話しやすい雰囲気を作り環境を整えても、職場の文化や参加者自身の過去の経験から、すぐには率直に意見を言うことが難しいということも多いと思います。そのため山代さんは、発言してくれたスタッフに対して「言い出しにくいことを教えてくれてありがとうございます」等というように勇気を出して発言してくれたことに感謝の言葉をかけ続けることが重要です。
前回からご紹介してきた心理的安全性が高い職場とは、「対人関係のリスクを取っても安全だと信じられる職場環境であること」です。心理的安全性のない職場では、今回の事例のように医療事故の増加や事故発生時の対応の不手際、看護師の離職により看護の質が低下し、その結果連携先からの評判が悪くなり、業績悪化につながる可能性があります。
このような状況にならないためにも、管理者や経営者は「心理的安全性を作る3Steps」を用いて職場に心理的安全性を構築する必要があります。
次回は、山代さんがスタッフと信頼関係を築き、質の高い訪問看護を行うための教育支援手法として、訪問看護ステーションにおける1on1ミーティングについてご紹介します。
参考文献
エイミー・C・エドモンドソン著 野津智子訳(2021)『恐れのない組織』,英治出版