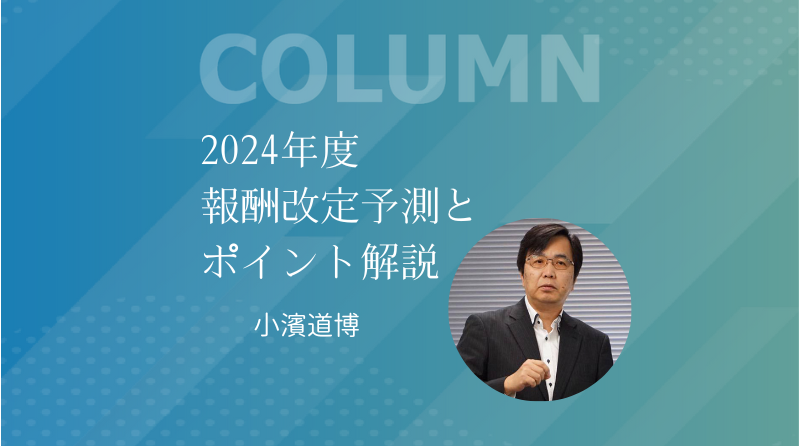2024年度の介護報酬改定の全容が決まるまで、およそ半年と迫っている。
物価高などによる影響で事業者の経営環境悪化が進む中、改定の行く末についてこれまでの関連審議や政府方針から考察する。
また、処遇改善加算の1本化やケアマネジャーの処遇改善、LIFEと成果報酬の関連付けといった、今後注目のポイントについて予想を交えて概説したい。
1.介護保険法改正を巡り残された論点と始まった令和6(2024)年度介護報酬改定審議
5月12日に令和6年(2024)度介護保険法が通常国会で成立した。
しかし、残された3つの論点
- 一号介護保険料を高所得者について更に引き上げし、低所得者の保険料を引き下げる件
- 自己負担2割の対象者を、現行の利用者全体の20%から30%に対象を拡大する件
- 介護老人保健施設と介護医療院の多床室料を全額自己負担とする件
の審議が、7月10日の介護保険部会から再開されている。
その結論については、6月16日に閣議決定された骨太の方針2023において、年末までに出すものとされている。
介護保険法の審議に並行して、令和6年度介護報酬改定の審議が始まった。現在は4つの主要な論点について、一巡目の審議が行われている。
*関連記事:【2024年度介護報酬改定】通所介護で実質的減算となった入浴介助加算に見直し要望
【2024年度介護報酬改定】ショートステイの利用長期化や医療ニーズの高まりに分科会が着目
8月頃までに一巡目の審議を終了して、9月に業界団体ヒアリング。
10月から12月にかけて二巡目の審議を行う。この二巡目で多くの論点は取り纏めされるが、一部の論点について三巡目の審議を行う。
12月中旬には、介護給付費分科会としての意見が取りまとめられて結審となる。12月下旬に令和6年度介護報酬改定の改定率が示される。
年が明けて、2024年1月下旬、遅くても2月初旬に、令和6年度介護報酬単位が答申される。
算定要件である解釈通知とQ&Aは3月初旬となる見込である。これが、今回の介護報酬改定のスケジュールである。

(【画像】第107回社会保障審議会介護保険部会の資料より)
2.令和6(2024)年度介護報酬は厳冬の改定に?~骨太方針の記載から読み解く
皆さまは、令和6年度介護報酬改定率がプラス改定とマイナス改定のどちらになると予想しているだろうか。長期化したコロナ禍の影響とウクライナ情勢に端を発した物価高騰もあって、楽観的にプラス改定を予想されている方が多いと感じる。しかし、コロナ禍は実質的に5月8日の5類移行で収束しているし、物価高騰も流動的な一過性の問題である。これらは介護報酬ではなく、補助金や助成金の類で対応する問題だ。
6月16日に閣議決定した骨太の方針2023における記載はこうである。
「次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては、物価高騰・ 賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・ 保険料負担の抑制の必要性を踏まえ、必要な対応を行う。〜中略〜医療・介護分野の課題について効果的・効率的に対応する観点から検討を行う」
問題は、改善や引き上げと言った文言が一言も無い事である。「効果的・効率的に対応する」という記載は、介護報酬全体を引き上げること無く、定められた枠組みの中でやり繰りが行われる事を示唆している。重要な部分を引き上げ、その原資として他の部分を引き下げると言うことだ。明確に「引下げ」という言葉が入らなかっただけでも良しとしなければならない。
というのは、国としての政策転換の影響が大きい。現在、国の施策の重要課題は少子化対策である。その資金3兆円の出所が決まっていない。その資金源泉として、当然に社会保障費用の削減も覚悟しなければならないだろう。すなわち、令和6年度介護報酬改定は、厳冬の改定となる可能性を捨てきれないのだ。
3.2024年度介護報酬改定の概観~処遇改善加算の1本化、居宅介護支援への同一建物減算の適用
さて、ここからは介護報酬改定について複数のサービスに影響しそうなポイントや積み残しとなっている論点について5つ取り上げたい。
第一に、現時点で3種類ある介護職員処遇改善加算の一本化の審議である。
一本化と言っても簡単では無い。3つそれぞれに異なる算定要件があるからだ。最も現実的なのは、現行の3加算を廃止して、新たな処遇改善加算を創設する事だ。6月28日の審議では、居宅介護支援事業所のケアマネジャーへの処遇改善加算の創設を求める声も出ている。この論点については、3年前の令和3年度改定審議でも実現ギリギリまで行ったが、ケアプランの有料化と紐付きだったため、ケアプラン有料化が先送りされたことから自然消滅している。今回は、紐付きでは無いため、実現の可能性は決して低くは無いと考える。
第二に、5月11日の財政審(財務相の諮問会議)・財政制度分科会において提言された、居宅介護支援事業所への同一建物減算の適用と、訪問、通所サービスの減算の厳格化である。これも、今回の審議の重要な論点となっていくだろう。
第三に、訪問サービスと居宅介護支援事業所へのLIFE加算の創設である。これについては、昨年と一昨年にモデル事業が実施されている経緯から、実現は確実と思われる。
第四に、在宅サービスへの身体拘束廃止未実施減算の拡大である。この点については、昨年12月20日に取りまとめられた介護保険部会意見書での記載と、すでに障害福祉サービスでは訪問サービスを含めての適用となっている事から確実と考える。
第五に、介護報酬改定の中で取りまとめられる、12年ぶりに創設される新たな複合型サービスの全容である。現時点では、デイサービスと訪問介護の組み合わせを予想する声が多い。もうひとつ、デイサービスと訪問介護、訪問看護の3サービスの組み合わせも視野に入ってきた。この想定の場合、既存の看護小規模多機能型、小規模多機能型、通所介護、訪問介護への影響は避けられない。これが、新たな業界再編に繋がる可能性もある。特に注目せざるを得ないだろう。

(【画像】)財政制度分科会(令和5年5月11日開催)資料より
4.LIFEの位置付け変更や機能訓練加算の強化…介護給付費分科会での注目点と予測
7月10日までに社保審・介護給付費分科会で論点が示されたサービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護の11サービスである。
この中で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護については、近い将来の統合、一本化についての議論が始まる。
小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については、国の重点化サービスで有ることから、その普及促進策が重要なテーマとなる。同時に、令和6年度介護保険法において、多機能型が機能訓練の場であることが明記されたことから、機能訓練関連の加算や算定要件の強化が行われるだろう。
通所介護と通所リハビリテーションについては、LIFEの活用と共に、自立支援への取組が更に求められるだろう。ただし、LIFEの正常化が遅れていることもあって、成果報酬の具体的な導入はあまり進まないとみている。同時に、令和3年度介護報酬改定で細分化された入浴介助加算の区分Ⅱにおける算定率が10%以下と低すぎるため、単に報酬を引き下げただけという批判が出ている。何らかの対策が取られるだろう。
今後、訪問サービス、施設サービスの論点が示されるが、やはりLIFEの位置づけに注目せざるを得ない。4月にスタートしたケアプランデータ連携システムとLIFEのシステム連携という話も入って来た。LIFEは、今後はケアマネジャーが主宰するサービス担当者会議での活用もみえてきた。LIFEの立ち位置が一気に変わる可能性が高い。
いずれにしても、令和6年度介護報酬改定審議はスタートした。その審議経過をしっかりと追っていきたい。