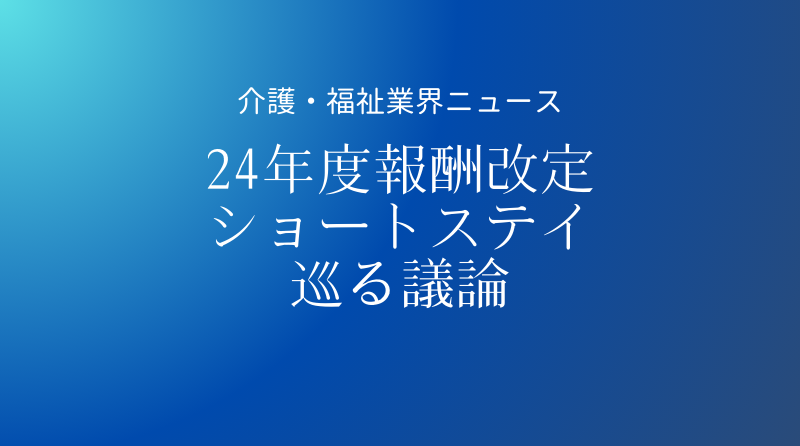2024年度介護報酬改定に向け、各サービスの現状と課題の整理や具体的な論点の洗い出しが始まっています。
短期入所系サービスが議題となった7月10日の社会保障審議会・介護給付費分科会では、コロナ禍の影響や医療ニーズの変化等を踏まえ、基本報酬の見直しや加算の拡充を求める声があがりました。ショートステイについてはほかに、利用の長期化や医療ニーズの高まりへの対応が焦点になりそうです。 また、短期入所療養介護では、21年度改定で創設された「総合医学管理加算」についての意見が集中しました。
コロナ禍による利用者数減が目立つ短期入所系サービス
厚労省は同日の分科会で、短期入所生活介護および短期入所療養介護の現状をまとめたデータを提示。どちらのサービスも、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大した19年以降、利用者数が3年連続で減少傾向となったことを示しました。

(【画像】「第219回社会保障審議会介護給付費分科会資料4(上)5(下)」より(※赤枠は編集部で追加)
また、短期入所生活介護に関しては22年度決算における収支差率が前年度から2.1%低下した事実も示されています。この点に関連して委員からは短期入所生活介護の収支の悪化が、併設施設全体の経営に悪影響を及ぼしている可能性について懸念する声があがりました。
全国老人福祉施設協議会の古谷忠之委員は、「電気料金の値上げや物価高の影響が非常に大きい」と指摘し、賃金アップのための基本報酬の引き上げや、基準費用額の物価スライド等の検討を要請しました。
短期入所生活介護:長期利用・医療ニーズが増加、専門職種との連携強化を
短期入所生活介護を巡って専門家からの注目を集めたのが、利用実態についてです。
連続利用日数別利用者数の推移をみると、22年度の調査では19年度の調査と比べて長期利用者が増加していることが明らかになりました。
【令和4年度「短期入所生活介護におけるサービス提供の在り方に係る調査研究事業」による長期利用者状況】- 「31日以上」の利用者割合:10.6%(令和元年度調査では8.6%)
- 「15日~30日」の利用者割合:10.7%(令和元年度調査では7.0%)

(【画像】「第219回社会保障審議会介護給付費分科会 資料4」より
また、全体的に医療的ケアの対応割合が高まっている結果も示されています。

(【画像】:同資料4より)
こうした状況をふまえ、委員らからは医療的ケアや機能訓練の充実のほか、訪問診療・訪問看護サービス等との連携強化、関連する加算へのインセンティブ強化を求める意見があがりました。
日本介護支援専門員協会の濵田和則委員は「新型コロナの感染拡大以降、利用前や利用当日の健康チェックや外部医療機関との連携、急変時の対応など、通常の長期利用と比べ明らかに介護の手間は拡大している。これらの点も考慮した改定が必要では」と提言しています。
短期入所療養介護(療養ショート):21年度新設加算の認知度が約3割と低迷
短期入所療養介護(療養ショート)については、2021年度改定で新設された「総合医学管理加算」の認知度が低迷している点について意見が出ました。
総合医学管理加算は、医師が診療計画に基づき必要な診療や検査等を行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な医学的管理を評価するものです。

(【画像】「第219回社会保障審議会介護給付費分科会資料 5」より)
介護老人保健施設において医療ニーズの高い利用者の受け入れを促す目的で新設されたものの、医療機関を対象とした認知度調査の結果は約3割と低迷していました。

(【画像】同資料5より)
日本慢性期医療協会の田中志子委員は「まだ7割もの医療機関に知られていない。周知されれば訪問診療のバックベットとして活用の道があると考える」と療養ショートの可能性について言及したうえで、「高齢者は治癒までに時間がかかるため、そもそも7日間という(算定日数の)限度が短く使いにくいのでは」と指摘しました。
また、全国知事会の寺原参考人は「検査等にかかった実費が(総合医学管理)加算で得られる収入を上回った」との県内事業者の実情を示し「急性期一般病棟や地域包括ケア病棟を補完する機能として強化するのであれば、加算認知度の向上とともにさらなるインセンティブ強化が不可欠では」と提言しました。