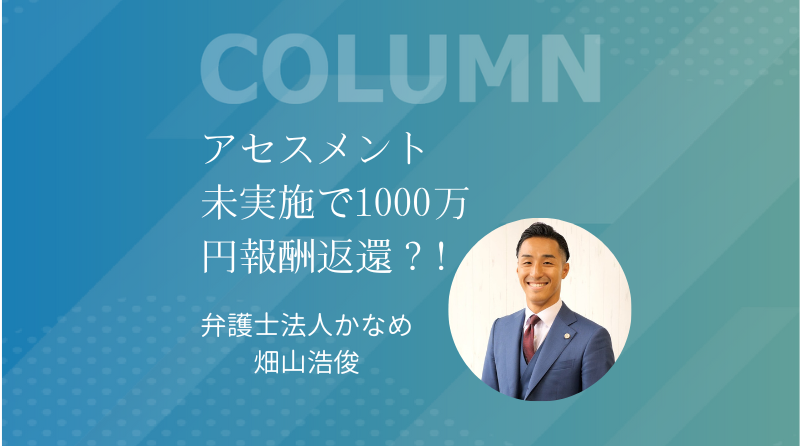1.アセスメントシートが抜けているから減算指導に?
今回は、ケアプランセンターの運営指導で、多額の報酬返還の指導を受けたケースの解説です。
2年前には、平成30年4月改正への対応の不備を指摘された件を紹介しておりますので、そちらの記事も併せてご覧下さい。
今回の事例は次のとおりです。
【ケース】
先日、介護保険課の運営指導を受けました。
実に1000万円もの報酬を返還するよう指導を受けており、驚いています。
弊社のケアマネAが担当している一部の利用者について、アセスメントシートが抜けていることが発覚しました。
介護保険課の担当者から、「一部の利用者について、アセスメントシートが確認できませんでした。アセスメントをしていないことは運営基準減算の対象なので、過去5年分の記録を自主点検して、報酬を返還してください」と指摘されました。
ケアマネAは「アセスメントをしていないことはないと思います。でも、確かにアセスメントシートが無いですね。どうしましょう」と顔面蒼白の様子でした。
ざっと計算したところ、1000万円程度の報酬を返還する必要があることになり、驚愕しています。
弊社のケアマネは、ご利用様のご意向を確認し、丁寧にケアプランを作成しています。それなのに、アセスメントシートが抜けている程度のことで、1000万円も返還しないのは納得できません。
1000万円もの返還をするとなると事業継続が困難になります。
本当に返還しないといけないのでしょうか。
2.アセスメントに定められている基準とは
弁護士法人かなめでは、このような相談に数多く対応しています。
今回の問題で重要なのは行政担当者の指導の根拠を確かめることです。
アセスメントについて、法令上どのように定められているのでしょうか。
介護保険法に基づき定められる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下、「指定基準」)13条6号、7号には以下のとおり定められています
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。(6号)
- 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。(7号)
他方、モニタリングについては、指定基準13条14号で、以下のとおり定められています。
介護支援専門員は、第13号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。
ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
(2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
(ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること。
(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
このように、モニタリングに関しては、「記録すること」が指定基準上義務付けられていますが、アセスメントについては、指定基準上は、その記録を残すことまでは要求されていません。
そのため、アセスメントシートがなかったとしても、アセスメントをしていたのであれば、指定基準違反ではありませんし、当然運営基準減算の対象ではありません。
弁護士法人かなめが担当したケースでは、担当ケアマネは、毎月利用者様のご自宅にお伺いし、アセスメント、モニタリングをしていました。
そしてモニタリングについてはきちんと記録されていました。モニタリングの記録があるということは、アセスメントを実施していることの裏付けになります。通常、「モニタリングだけ行って、アセスメントは実施しない」という事態は想定できないからです。
そこで、我々は、介護保険課に対して、「自主点検の結果、アセスメントを実施していたことが確認できました。」と伝えたところ、介護保険課の担当者は、「実際にアセスメントとされていたのであれば、運営基準減算に基づく報酬返還の必要はありません。」と回答があり、自主返還の指導は取り下げられました。
3.運営指導の際に気を付けるべきこと
運営指導の際に、行政担当者から指導を受けた際、全てを鵜呑みにすることは禁物です。
指導に根拠となる法令があるのか、そして、その法令解釈は正しいのかを確認する癖をつけるようにしましょう。
今回のケースのように1000万円もの自主返還を行うと事業継続に支障を来たす事業所もあるはずです。介護事業者だけで対応が困難と感じる場合には、介護行政対応に強い弁護士に相談するようにしましょう。