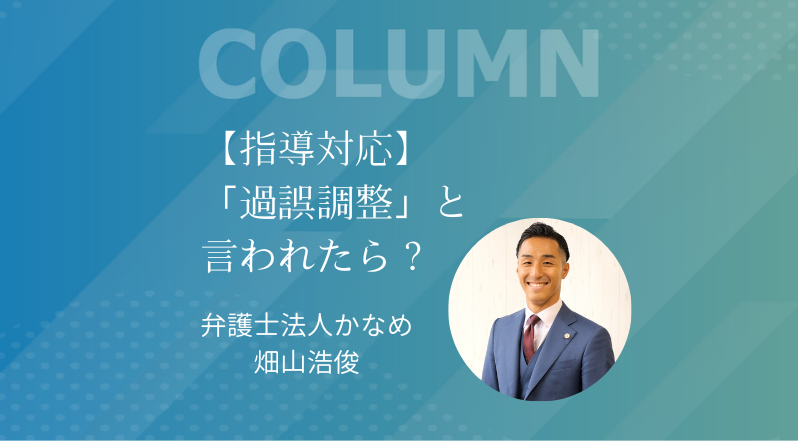1.実地指導から運営指導へ
2022年度から、「実地指導」という名称は「運営指導」に変更されることになりました。
これは、実地でなくても確認できる内容(「最低基準等運営体制指導」及び「報酬請求指導」に限る)の全部または一部事項にかかる確認については、オンライン等を活用して実施することも可能であるとして、名称を変更したものです。もっとも、施設・設備や利用者の状況などはもちろん実地での確認が必要ですし、あくまで原則は、実地で行うことが想定されています。
そのため、名称が変更されたからと言って、従来の実地指導から大きく内容が異なることはありません。
22年3月に厚生労働省老健局総務課介護保険指導室から『介護保険施設等運営指導マニュアル』が公表されていますので、一度、目を通しておきましょう。
(編集注:vol.1062介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)の送付について)
本稿では、2022年度以前に実施された実地指導の対応事例を紹介しますが、今年度から名称変更されたことに伴い、「運営指導」と表記を統一します。
2.運営指導に対応する際の心構え
運営指導は「介護サービスの質の確保」と「保険給付の適正化」を目的として実施されるものであり、行政担当者はこの目的に沿って運営指導を行います。
行政担当者は、介護保険法、それに基づき制定された人員基準・運営基準、そして、各種マニュアルや厚生労働省が出している事務連絡等に則って指導を行っているので、行政担当者から運営面について指摘を受けた場合は、真摯に受け止め、改善していくことが原則です。
もっとも、行政担当者自身が、法令解釈を誤ったり、明確な根拠が無い状態で運営指導を行ったりしている場合があります。そして、時に、誤った法令解釈を元に、介護報酬の自主返還を指導するケースもあるため、注意が必要です。
本稿でお伝えしたいのは、運営指導を受ける際の以下のような心構えです。
【運営指導を受ける際の心構え】
行政から受けた指導だからと言って、全て鵜呑みにするのではなく、指導の根拠を介護事業者側でもきちんと把握し、理解した上で、改善すべき点は改善していこう。
もっとも、根拠が不明で納得できない場合は、行政に対して説明を求め、反論すべき点は反論していこう。
3.ケアプランセンターでの運営指導例
ここでは、筆者が過去に居宅介護支援事業所(本稿ではケアプランセンターと表記します)で実施された運営指導へ対処した事例を紹介します。
2018年度介護報酬改定において、「ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保」の観点から、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、ケアプランセンターでは、以下の説明が義務付けられました(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第4条2項前段、以下、「本件説明義務」といいます)。
・利用者や家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること
・当該事業所をケアプランに位置付けた理由の説明を求めることが可能であること
これらに違反した場合は介護報酬の減算を受けたり、加算が取り消されたりすることになるなど、介護報酬の返還が求められることになります。
筆者が対応した運営指導では、対象のケアプランセンターが、本件説明義務の履行ができていないとの指摘を受け、報酬を自主返還するよう指導を受けました。金額にして、実に約1,500万円です。在宅中心の小規模のケアプランセンターでしたので、この金額を返還するとなると、廃業を避けられない状況でした。
行政は、本件説明義務を履行したと言えるためには、「文書を交付して説明しなければならない」ことを前提として指導を行っています。この指導は、行政から交付された文書の指摘文言等に鑑みれば、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知、以下「本件課長通知」といいます。)に基づくものと解されます。
4.行政組織内部における命令と法規範性
ここで吟味しなければならないのは、本件説明義務を果たすために、「文書を交付して説明する」ことは、介護保険法やそれに基づく法令上の義務か、という点です。
あくまで、介護事業者が拘束されるのは、介護保険法やそれに基づく法令であって、行政が組織内部で作成したマニュアルや事務連絡は、それが法令に基づいて制定されたものでない限り、法的拘束力はないはずです(図参照)。
では、介護保険法やそれに基づく法令は、本件説明義務の履行について「文書を交付して説明する」というところまで求めているのでしょうか。
ここで確認すべき条項は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「本件基準」といいます。)第4条2項前段です。本件基準は、介護保険法の一部として構成されるものであるため、法的拘束力があります。そして、本件基準4条2項前段では、「説明を行い、理解を得なければならない。」と規定されており、「文書を交付して説明する」という点までは要求されていません。
すなわち、本件課長通知は、あくまで、法令に基づくものではなく、行政組織内部における命令に過ぎず、法的拘束力は無いと解釈すべきです。
そう考えると、本件課長通知が規定する「文書を交付して説明する」という手段は、本件説明義務を履行する上での一つの方法・手段に過ぎないと捉えるべきであり、それを実践していないからといって、直ちに本件説明義務違反があると考えるべきではありません。他の方法でも、「説明を行い、理解を得なければならない。」という義務を履行できているのであれば、法令は遵守していると考えることが可能です。
筆者が、今回指摘を受けたケアプランセンターのケアマネジャーからヒアリングしたところ、ケアマネジャーは利用者との契約開始時に、本件で求められている説明を、口頭で一人一人、丁寧に行っていたとのことでした。
たしかに、口頭での説明では、明確な証拠が残らないため、本当に本件説明義務を履行したと言えるのかは微妙です。集団指導においても、行政担当者は、「文書で説明しよう」ということを告知していた訳ですから、ケアプランセンターに一定の落ち度があると言わざるを得ません。もっとも、「文書で説明」という方法は、法令に該当しない本件課長通知に記載されている一方法に過ぎないため、それをもって運営基準違反があると断定することまではできないはずです。
そこで、筆者は、ケアプランセンターの利用者に対し、利用開始時に本件説明義務が履行されたかについて、一人一人書面で確認を取りました。そうしたところ、利用者からは「きちんと説明を受けていたし、その説明を理解していた」という確認を取ることができました。この確認文書を行政担当者に交付した上で、本件説明義務の違反はないと主張した結果、約1,500万円の自主返還の指導は、取り下げられることになりました。

疑問に感じたら介護行政対応に強い弁護士へ相談を
今回、紹介したケースのような本件説明義務違反を争った裁判例は、筆者の知る限り過去にありません。
仮に、裁判で法廷闘争になった場合、筆者の言い分と行政側の言い分のどちらに軍配が上がるのかは、司法判断を待つほか無い状況です。
もっとも、行政法の一般原則から考えると、筆者の主張内容は充分法的に戦うことのできる論理構成です。
大切なことは、行政担当者から運営指導の際に指摘を受けた内容が、全て法的に正しい指摘だとは言えないということです。特に、多額の介護報酬返還を伴う指導があった場合には、事業継続に関わる大問題ですから、慎重に対応する必要があると言えるでしょう。
本稿で紹介した運営指導を受ける際の心構えを踏まえて、行政ときちんと根拠に基づき対話していくことが大切です。
介護事業者だけで対応が困難と感じる場合には、介護行政対応に強い弁護士に相談するようにしましょう。