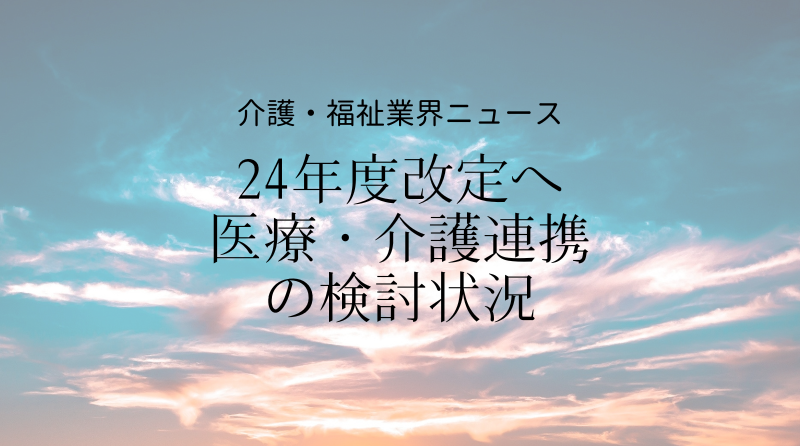社会保障審議会・介護給付費分科会では、2024年度の医療介護同時改定に向けて、医療と介護の連携をさらに促すための施策が検討事項の一つとなっています。
厚生労働省が示した基本的な方向性としては、医療機関には「生活」の視点を踏まえた情報提供を、介護現場には「医療」の視点を含めたケアマネジメントを求める姿勢が打ち出されています。
また、ケアマネジメントの過程や介護施設で”人生の最終段階”における利用者の意思決定支援に関わる立場からは、適切な表現やタイミングの共有など、現場の懸念を払しょくさせるサポートを求める声がありました。
社会保障審議会・介護給付費分科会におけるサービス横断的な検討テーマ
社保審・介護給付費分科会では、8月末からサービス横断的な事項についての検討を進めているところです。厚生労働省がこれまでに示してきた議題は以下の通りです。
【地域包括ケアシステムの深化・推進(第222回・8月30日)】
1.認知症への対応力強化
2.医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護
3.新しい複合型サービス
4.地域の特性に応じたサービスの確保
【自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進(第222回・8月30日)】
【介護人材の確保と介護現場の生産性の向上(第223回・9月8日)】
1.介護人材の処遇改善等
2.人員配置基準等
3.介護現場の生産性向上の推進/経営の協働化・大規模化
4.外国人介護人材に係る人員配置基準上の取り扱いについて
こちらのページでは、8月30日に行われた【医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護】を巡る検討についてまとめています。
医療・介護連携:医療側からの情報提供には「生活」の視点を
まず、前段の「医療・介護連携」を巡って、厚労省が示した論点は以下の通りです。
- 要介護高齢者が、在宅・高齢者施設・医療機関のいずれの場においても、必要なケアを受けることができるよう、関係機関の連携を充実させる観点からどのような方策が考えられるか。
- 特に、医療においてはより「生活」に配慮した質の高い医療を、介護においてはより「医療」の視点を含めた介護を行うために必要な情報提供の内容や連携の在り方について、どう考えるか。
2040年にかけて医療と介護どちらのニーズも有する高齢者が、双方のサービスを利用する機会はさらに増える見込みです。そこで、医療と介護の関係者、関係機関同士が、相互の顔の見える関係を構築し、情報提供・共有を効率的に行うことが益々重要となります。
介護報酬上でも、介護施設と居宅や医療機関との間を行き来する上で情報連携を図ることを評価する加算などがさまざまに創設されてきました。

(【画像】第222回社会保障審議会・介護給付費分科会資料2より(以下・同様))
これに関して健康保険組合連合会の伊藤悦郎委員は、情報連携に関連した評価のうち、算定率が低いものもある点を指摘。そのうえで、「報酬上の評価だけで改善するのではなく情報連携の体制の整備を早急に進めるべき」と提言しました。
具体的な施策として、医療と介護で共有すべき情報内容や様式などを整備すること、医療DX・介護DXの視点を踏まえたICTの活用推進策を検討することなどを提示しています。
医療・介護連携に関する加算を見直す切り口としては、厚労省側も算定に用いられる一部の様式は、「現病歴等の診療状況に関する情報を記載する項目が中心であり、生活歴等を記載する項目が比較的乏しいもの」があることを指摘しています。
また、介護給付費分科会での検討が始まる前に、診療報酬についての検討を行うメンバーと行われたすり合わせ(同時報酬改定に向けた意見交換会)では、「医療側の「生活」に配慮した視点がかけている」という指摘もあったところです。
医療ニーズを持つ利用者の「生活」に着目した情報連携を可能にする方策が、今後”検討の視点”として示されています。

人生の最終段階における医療・介護:現場の不安を和らげるサポートを
もう一つの議題が、「人生の最終段階における医療・介護」です。論点を以下に示します。
- 本人が望む場所でより質の高い看取りを実施できるようにするためには、どのような対応が考えられるか。
- 本人の尊厳を尊重し、意思決定に基づいた医療・介護を提供するための医療・介護従事者の連携や支援の在り方、情報共有の在り方についてどのように考えるか。
”人生の最終段階における医療・ケア”を巡る概況
近年は自宅や介護施設等における死亡割合が増加しており、2021年における死亡場所は、医療機関が67.4%、自宅が17.2%、介護施設等が13.5%となっています。
特に、介護施設等の割合が近年上昇していることから、施設における”人生の最終段階における医療・介護の在り方”が中心的な検討事項の一つといえます。

このテーマに沿って2021年度介護報酬改定を振り返ると、ターミナルケアに関する要件として「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める見直しが実施されました。一方でガイドラインに基づいた対応がなされた割合については、施設種別でばらつきがあります。

また、人生の最終段階における医療・ケアに関して話し合った内容について、医療・介護従事者と共有していると答えた者の割合は一般国民で15.8%となっています。

”人生の最終段階”に向かう意思決定支援の難しさ
「本人が望む場所でより質の高い看取りを実施」するための意思決定支援を図るうえでは、介護現場の従事者が比較的健康な頃から利用者にアプローチしていくことも求められてきます。
日本介護支援専門員協会の濵田和則委員は、早い段階から看取り期のケア等を想定した意思を確認することについて、「死を意識させ不快な思いを抱かせないか、誤解を招く恐れがないか」という懸念が強いことが想定されると指摘。
こうした誤解を招かない促し方や表現、タイミング、仕組みなど、懸念を払しょくさせるような意思決定支援の検討を求めました。
他にも、「利用者本人の価値観を尊重し意思決定を支えると同時に、その意思を尊重できる体制整備が重要」、「ご本人の意思が聞き取れない状況になってからの在り方について、もっと明確に示すべき」といった意見があがっています。
*ACPに関する記事のご紹介
以下のページでは、現場従事者のみなさまがACPの目的についての理解を深め、利用者らとの適切なコミュニケーションに活かすためのプロセスについて紹介しています。
併せてご参照ください。
*「自分の人生を生きるためのACP」~I.訪問看護従事者・介護福祉関係者のACPに関する知識を見直そう~