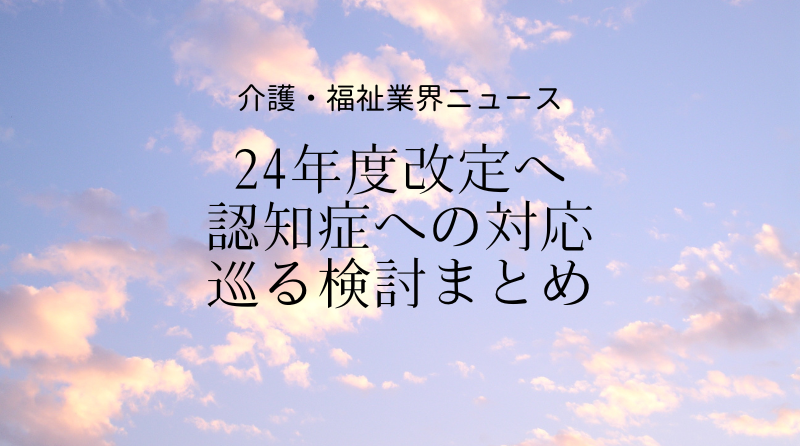2024年度介護報酬改定にむけ、8月末から9月にかけてはサービス横断で対応すべき事項についての検討が進んでいます。
本記事では「地域包括ケアシステムの深化・推進」を図る切り口の1つである「認知症への対応力強化」について、社会保障審議会・介護給付費分科会での論点や検討状況を整理します。認知症関連加算の算定率の低さを踏まえた要件の見直しや、エビデンスに基づくBPSDへの対応への評価を求める声などが出ています。
地域包括ケアシステムの深化・推進と認知症対応力強化を図るための論点
222回の同分科会(8月30日開催)にて、厚労省が示した議題は以下の通りです。
【地域包括ケアシステムの深化・推進】
1.認知症への対応力強化
2.医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護
3.新しい複合型サービス
4.地域の特性に応じたサービスの確保
これに加えて、【自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進】を図るためのテーマとして、LIFEについても取り上げられています。
本記事で整理する「1.認知症への対応力強化」について、厚労省が提示した論点を下記に示します。
- 今後、増加が見込まれる認知症の人に対し、認知症になっても、本人の意思が尊重され、尊厳をもって暮らし続けることができるように、在宅の要介護者も含めた認知症対応力を向上させていくことが求められるが、こうした観点から、認知症関連加算の算定状況や在り方について、どのような対応が考えられるか。
- 在宅や施設で生活する認知症の人のBPSDの予防を進め、重症化の緩和を図る観点から、BPSDの更なる理解促進や対応力向上が求められるが、事業所・施設等における体制構築強化に向けて、どのような方策が考えられるか。
- 現在調査研究においてその有用性を検証・分析している認知症の認知機能・生活機能に関する評価尺度について、今後、介護現場においてどのような活用が考えられるか。
算定率が低迷する認知症専門ケア加算、要件を見直しへ
介護施設や事業所の.認知症への対応力強化を図るうえでは2021年度介護報酬改定でも
- 訪問系サービスへの「認知症専門ケア加算」の創設
- 「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を多機能系サービスに創設
- 介護職員のうち、医療・福祉関係の無資格者に対して、認知症介護基礎研修の受講を義務付け
といった見直しが実施されました。
しかし、認知症専門ケア加算は、訪問介護で加算(I)の算定率がおよそ0.01%、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では0.7%と算定率は低迷しています。

厚労省は算定率が著しく低い背景について、「算定要件の一つである認知症自立度の利用者割合が、必ずしも各サービスの利用者実態と合致していないケースがある」としています。
こうした現状に対し、複数の委員から算定要件の見直しを求める意見があがりました。また、要件にある「認知症ケアに関する専門研修」について、「希望してもなかなか受けられない現状」を算定率低迷の一因と指摘し、さらなる受講環境の整備を要望する意見もありました。
根拠あるBPSDケアに報酬上の評価を:委員の意見
続いて、認知症の認知機能・生活機能に関する評価尺度を巡る検討です。
厚労省はこの日、2021年度・2022年度実施の調査研究事業にて、BPSDの予防・軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する検証を行い「有効性が示された」ことを明らかにしました。


これは、全国の施設・事業所(介護老人保健施設6施設、特別養護老人ホーム28施設、認知症対応型共同生活介護27施設の計61施設)を利用する認知症の人を対象に、「BPSDの客観的評価」「全人的アセスメント」「Plan-Do-Check-Act(PDCA)サイクルで繰り返すチームアプローチ」の3つの要素に準じたケアを行う介入群と通常ケアを行う対照群を比較したものです。21年度の事業でまとめたBPSD予防ケアのためのチェックリストに基づいたケアをチームで展開し、検証したところ、BPSDの軽減について一定の有効性が確認されています。
また、別の切り口としては介護現場のスタッフが簡便に評価できる認知症の「認知機能・生活機能」に関する指標の開発も進められています。


全国老人福祉施設協議会の古谷忠之委員は、BPSDケアに対する調査について「非常に有効性が認められる結果だと受け止めている」と述べました。その上で、成果の普及に向け、報酬上の評価の検討や、BPSDケアに関する研修カリキュラムの整理、受講しやすい環境整備等を求めました。
日本医師会の江澤和彦委員も、BPSDの予防や出現時に早期に対応する適切なケアを「次回改定で評価してすすめていくべき」と言及しました。
さらに江澤委員は、認知症の新たな評価尺度について、「生活機能に着目し、できる可能性のあることに視点を置いた認知症ケア、あるいはケアプランにすることが重要だ」とも述べました。
全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は、現在の評価尺度である認知症高齢者の日常生活自立度を「認知症の方のできないこと・迷惑度・手間のかかり度に目をつけたもの」だとし、「尊厳を守っていることにはつながらない」と指摘。
認知症の方の認知機能・生活機能を適切に評価する尺度の必要性を述べたうえで、医療・介護で共通して使用するべきだと提言しました。