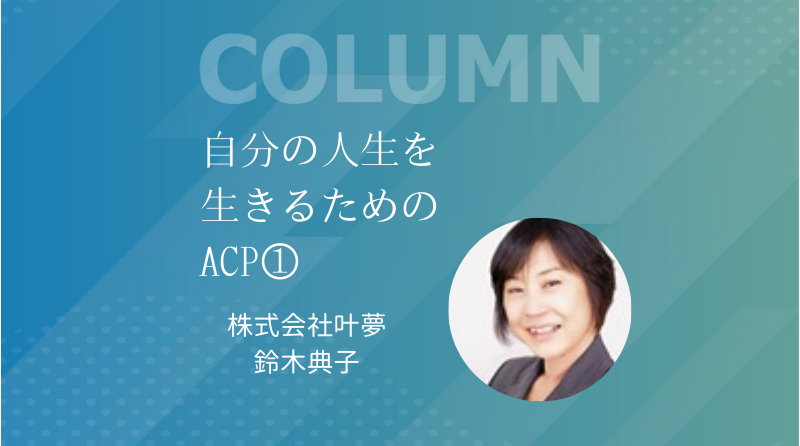最近やたらに「ACP」という言葉を見ること・聴くことが多いと思います。ACPは正式にはアドバンス・ケア・プランニング―日本語では人生会議といいますが―について、医療関係者や介護福祉関係者でも理解を深めている方は少ない現状にあります。
医療者や介護福祉関係者がACPの目的を改めて認識し、患者・サービス利用者らとの適切なコミュニケーションに活かし、1人1人の「生き方」の実現を支援するためのヒントをお伝えします。
ACPは病気になってから考えるだけのものではない
医療現場や施設には、ACPをはじめ、BSC やICなど様々な英単語の略語・頭字語があります。この中には、似たような意味合いの略語・頭字語も多く存在します。
例えば、Informed consent(IC;インフォームドコンセント)は、日本語では「説明と同意」を意味します。医師が病気の現状や病名、治療方法について説明して、患者らがそれらを理解し納得・治療の同意をするという意味合いです。
また、Best supportive care (BSC;ベストサポーティブケア)とは、患者の希望に応じて積極的治療(例えば、がん治療の場合は外科治療、化学療法、免疫療法、放射線治療、遺伝子治療のこと)は行わず、痛みをとったりQOLを高めたりすることを意味します。ここでもQuality of life(QOL;クオリティー・オブ・ライフ)という言葉が出てきます。これは「生活の質」を意味します。
では、ACPというのも病気などになったご本人またはご家族に対して医師や医療者が治療の意向や希望を聞き、それに沿った治療方針等を計画するものなのでしょうか。
多くの医療者は、ACPとBSCは違うものと受け止めていることでしょう。それでも、何がどう違うのかは良く分かっている方は少なく、どちらも「人生の終末における時(命の危機が迫った時)のもの」と捉えがちです。しかし、ACPは病気になってから考えるだけのものではありません。
医療者だけでなく、介護福祉関係者もACPが何を意味しているのかはっきり分かっていないことが多いのではないでしょうか。そこで、医療関係者・介護福祉関係者らケアに関わる立場の方から見た時のACPの目的について、イメージを示していきたいと思います。
ケアに関わる立場から見たACPの目的と「もしも」の後に続く生活
ACPの目的は、加齢や疾患にかかったときや障害を持ったときに自分がどのように生きていきたいかや、もしもの出来事があっても最期までどのように生きて行きたいかについて本人(医療現場では対象が患者、福祉現場では利用者にあたると思われます)がその思いや考えを、家族や医療・福祉の人たちに意思表示できるようにすることです。
日本人には「もしもの時」を考えるのは「不吉」だと思う人が多くいます。それは、「もしもの時=死」とイメージするためでしょう。実際に、医療者・介護福祉関係者が深刻な意図を持たずに尋ねても、拒否感を示す方は多く、自分の意思を家族にも伝えていないというケースも度々あります。
しかし、「もしもの時」を考えないようにしていても、予期しない事態は突然起こり得ます。身体の異変が起き、自分が意思表示できなくなったときに思いもよらない処置やケアをされてしまうことがあると思います。
ご本人が明確に意思表示されていない場合は、医療・福祉等に携わる人たちがご家族やそれに近い方々に対して、今、現時点での状態・状況の説明し、その後の医療的処置を含め、ご家族らの意向を確認することが多いです。そのため、その先に続く生活のことが考慮されずに、緊急時の情報だけでご家族らの判断がなされたり、意向が示されたりしやすくなってしまいます。結果として、ご本人やご家族が「思いもよらなかった人生」を迎えることもある訳です。
ACPとBSCの違い―自分の人生を生きるための意思表示
医療者にとっては、ICを行いその場の状況に対して命をつなぐ適切な医療処置をすることが優先事項となります。その後の治療過程において、治療の効果が少ないと判断した場合、再度ICを行い、ご家族の意向でBSCを行っていくこともあると思います。
例えばがんの治療を行っていた方が、その効果が得られず今後の治療を期待できないと医師が判断した時にICが行われ、BSCとなることが多くあります。
ここでのBSCがACPと混合されがちです。
治療は中止し、緩和ケアを行う方針が採られる際に、「BSCなので治療はせず、痛みのコントロールを中心としていきます」「自宅に帰りたいというので、訪問診療や訪問看護でお願いします」といった内容で申し送りがあることがほとんどです。
緩和ケアの中でも、「残された時間をどう生きていきたいか」まではイメージが及ばないことが未だ多いのが現状です。
人の体形や顔立ち等が異なるのと同じように、生き方も人それぞれに異なります。たとえ夫婦や親子、兄弟であっても生き方や考え方は同じではありません。
しかし、自分の生き方やその方向性について意思表示をしていなければ、「思いもよらない結果」を迎えることになるかもしれません。それでもその中で生きる楽しみを見つける方も多くいらっしゃると思いますが、「こんな体になってまで、こんな苦しみが続くのなら助けてほしくなかった」とその後の人生を生きる力が無くなってしまう方がいらっしゃるのも事実です。
そのような思いをしないためには、自分の意思表示や価値観を伝える事が必要であり、それがACPだと言えます。
ACPを活かしたコミュニケーションと医療・介護福祉職の役割
ACPはあくまでも「生きていく」過程」の意思表示です。年齢や状況・環境等によって生きていく過程は変化し、自分の考えも変化していきます。現場で出会う方々がACPを書き留めていたとしたら、その内容を確認しながら「いつ書き留めたものなのか」「その(書き留めた)時のご本人の状況や環境はどうだったのか(背景を確認)」「ご家族またはそれに近い人もそれの存在(書き留めたもの)を知っているのか」「これからに向けた生活の希望はどのように考えているのか」等、会話の中でさりげなく話題にしてみることも大切です。また、自分で意思表示できない方のご家族様に「本人の考え」を書き留めたものから確認していくことが必要だと思います。それらの内容を確認しつつ、これから「生きていく・行きたい」あり方の実現を手助けするための多様な可能性・情報を提供しながら、その都度バージョンアップをしていくことが大切です。
ACPはあくまでも「その人の生きるストーリーの方向性・過程」だと言えます。決して治療を決めるアイテムではありません。本人の生き方や生きる道に対しての原案になるのではないでしょうか。