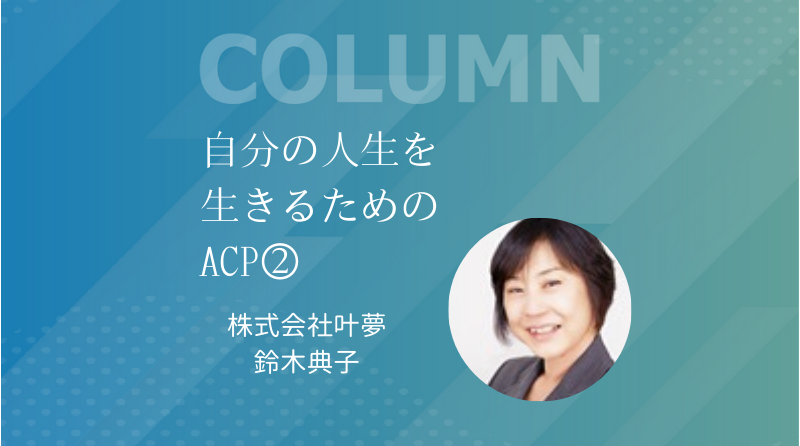「ACPについてアプローチする」と考えると、高度なスキルが必要と捉えがちです。
しかし、訪問看護従事者や介護・福祉関係者があまり難しく考えてしまうと、その支援を受ける側は更に難しく受け取ってしまいます 。
ACPは将来の変化に備え、将来受ける医療やケアについて、本人を主体に、そのご家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援するプロセスのことですが、言い換えればそれぞれの生き方です。堅苦しく考えるものではありません。
生活の場でサービスを提供している訪問看護従事者・介護や福祉の関係者だからこそできるACPについて考えたいと思います。
「暮らし・生活」を支える専門職としてACP支援を考える
看護や介護・福祉の仕事を続けていると、たくさんの方の人生に関わります。医療機関や介護施設などその場所も様々です。
例えば病院には、病気や怪我をした人が訪れます。状態や年齢、性別などが様々な相手に対し、私たちは、治療をサポートし、療養生活の中で患者の健康状況を安定させ、自宅へ戻り地域で暮らしていけるよう働きかけます。
時には、人生の終末期に向かう方に対して、最期までに向けて最善の医療や看護を提供する役割を担います。
介護・福祉施設では、高齢の方や障害を持っている方たちが施設で生活を継続していけるようサポートことが最大の役割です。その人がどんな状況にあっても尊厳を持ち生活できるように支援します。
このように専門職として対象と関わる場所は異なっても、その相手が「人」であること、そしてその人が障害や病気を抱えていても、より良く生き、暮らしていくために治療や看護・介護を提供することは共通しています。
では、「暮らし・生活」を支える訪問看護従事者あるいは介護・福祉関係者として、どのようなACP支援ができるのでしょうか。
サービス担当者会議はACP支援に向けた第一歩
訪問看護従事者や介護・福祉関係者がサービス対象者に関わるきっかけは、病院(施設)から退院(退所)をする時や、何らかの原因で対象者に障害が生じた時、または加齢で今までのような暮らしがしにくくなった時が多いと思います。
人間関係を構築していく前の「初めまして」の段階で、いきなり「人生会議について」といった話はできないでしょう。
まず訪問看護などのサービスが始まる時には、「サービス担当者会議」が開催されます。その後サービス対象者(またはその家族)と事業所が契約を取り交わすことが多いと思います。
もちろん、この場面でいきなり「人生会議」はできませんが、実はサービス利用者とその家族がこれからどのように暮らしたいか明記されている資料があるのです。
それが、担当者会議の前にケアマネジャーが作成している居宅サービス計画書です。計画書の第1表には、「その人やその人の家族の生活に対する意向」という項目があり、ケアマネジャーはその意向に沿ったサービス計画を作成しています。
ここへ記載されている情報は、対象者と関わり、支援していく立場からすると有用な情報の宝庫です。
会議をしている時に、その書類やその場の言動から相手の今までの生活が垣間見えます。
これがACP支援に向けたファーストステップです。
「これからの人生をどう生きていきたいか」を問う
担当者会議の後に契約を取り交わしながら、これからのサービスに向けて、どのような支援を必要としているかなど、対象者から情報収集をすることになります。
ここがACP支援に向けたセカンドステップです。
通常、情報収集するの内容は、身体状況や生活歴、趣味やこだわり等、サービス開始に至るまでの病気や生活上での問題点等を聞き取ることが多いでしょう。
その時、本人やご家族に必ず質問しておくべきことがあります。
それは「これからの人生をどう生きていきたいですか」ということです。
たとえ初対面であっても、話が進む中でさらっと聞けるフレーズではないでしょうか。
もしこれから、現状より身体状況が悪化した場合に積極的治療を望むのか、自宅に居ながらできる治療をしていきたいのか、もう治療をせず苦痛なく暮らすことを中心に考えているのか等話を膨らませて確認することもできるかもしれません。
しかしここで注意していただきたいのは、この時に希望していることが全てでないということです。
「今、その時点」の思いや意思を確認しておくことが重要なポイントとなります。
ここは、家族の思いや希望も同時に確認するタイミングです。
またこのとき、本人やとその人のご家族の思いや意思に対して、訪問看護従事者や介護・福祉関係者がどのように支援ができるのか等の情報を提供することも大切です。
ACP支援のタイミングは日常の中に
ACP支援に向けたてのサードステップは、何気ない日常の中にあります。
例えば、会議と契約が終わり、サービス提供が始まって交わす日常会話や雑談の中でも、「どう生きていきたいか」を聞くことができるでしょう。対象者との関わりを積み重ねていく中で、その人の人生観や死生観、価値観等も理解できていくことと思います。
安定したサービス継続の中でも新たな発見や機会はあります。今の時代、どのお宅でもテレビがあり、1日中テレビがついているお宅が殆どです。マスメディアの情報はどの年齢でも認知できます。突然発生する災害や経験のしたことの無い感染症流行等の情報に触れたときは、「もしも災害になったら」「もしも自分が感染したら」と非常時の対応に関する話題へと繋げやすいタイミングです。このような時ももしかしたらACP支援に向けた絶好の機会かもしれません。
ACP支援をする中で使ってはならないフレーズ
ACP支援をする中で注意することがあります。それは言葉の使い方です。
私たち訪問看護従事者や介護・福祉関係者の言葉の使い方で、マイナスイメージを与えないことが必要です。何かきっかけを掴み、これからの人生をどうしたいか私たちから問いかける時、「もしも」や「万が一」というフレーズは使用しない方がいいでしょう。
「もしも」は特に起こってはならないこと(特に死)を想像してしまう可能性があります。
「万が一」も、悪い事態を仮定するときに使われることが多い言葉です。気軽に使いがちな言葉ですが、ネガティブなイメージを連想するフレーズを使うことによって、患者・利用者(またはその家族)がこれから先の人生をどのように生きていきたいか、前向きに考えられなくなる恐れもあります。私たち専門職がACP支援をする場合は、言葉の使い方や態度等、細かいところにも気遣う姿勢をもって対応しなくてはいけないことを理解する必要があります。
ACPとは、患者・利用者(またはそれら家族)が生き方を考えるツールです。専門職側から見ると、彼・彼女らの人生の節目でのサポートです。私たちには、患者・利用者らの状態や状況が変化したときその変化に気づき、その変化を分かち合い、その後の暮らしを共に考え、その生活を支援していく役割があります。
ACP支援のきっかけをタイミング良く作っていくことから始めてみるべきではないでしょうか。