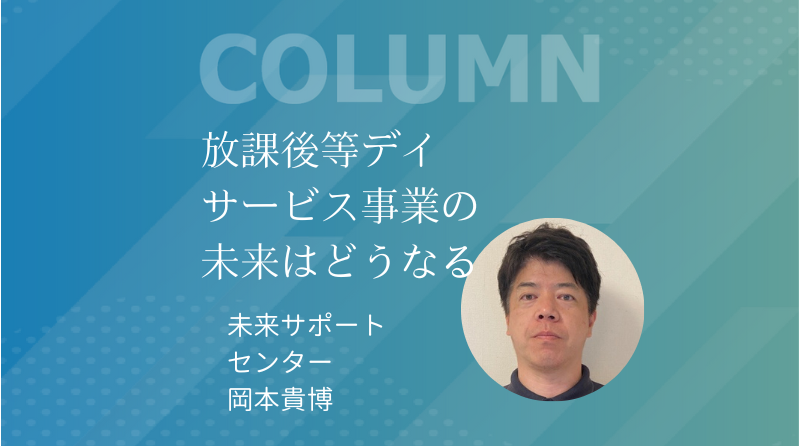皆様、初めまして。障害福祉サービス、特に障害児通所支援事業所様の支援を中心に活動している行政書士の岡本貴博です。「役所目線で事業所とお付き合いしていく」ことをスタンスとして、運営指導のサポート等に取り組んでおります。
ときには事業所の方と言い争いになることもありますが、全ては経営者、従業員、利用者とご家族のみなさまのためと考え、日々のご相談に対応しております。
介護経営ドットコムではこれから、この業界の動向について2024年度障害福祉サービス等報酬改定の影響や近接領域サービスの動き等も踏まえて解説していきます。 皆様に貢献できるよう取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願い致します。
放課後等デイサービスを巡る2024年4月の報酬改定方針とその対応
まず、24年4月にあった障害福祉サービス・児童福祉事業の報酬改定についてです。この中でも児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護は大きく制度が変わり、既存の事業所からは「もう運営できない」というお声も聞こえてきます。
今回は、放課後等デイサービスを巡る2024年4月改定の主要方針は、以下のとおりです。
「質の高い発達支援の提供の推進」
「支援ニーズの高い児童への支援の充実」
「家族支援の充実」
「インクルージョンの推進」
もし、こうしたワードにピンと来ない事業所があれば今後、運営が厳しくなってしまうかもしれません。「ピンとこない」と言うことは、今まで放デイの制度について十分理解しないまま事業所を運営されてきたと言うことです。
では、改定を踏まえ、これからの事業所運営はどのように行っていけば良いのでしょうか。
これからの放課後等デイサービス事業所運営に欠かせない4つのアクション
報酬改定への対応を含めてこれからの放デイ事業運営に不安を感じている、あるいは、今後の参入を検討していたりする事業者には、まず以下の4つを必要なアクションとしてお伝えします。できることから取り組んでいただければと存じます。
①従業員の信頼を勝ち取るためにも経営者自身が放課後等デイサービスの制度・法令を理解する
今までは、子どもたちを預かっているだけでも事業所運営ができていたでしょう。しかし、今回の障害福祉サービス等報酬改定によって「支援の質」「事業所運営の透明化」「家族支援」「インクルージョンの推進」が明確に求められるようになりました。
これらの方針に対応し、経営を安定させるうえでも今まで以上に制度と法令への理解が必要です。従業員から法制度やその対応に関する質問を受けた際に答えられないようであれば、事業所運営は困難です。
なぜなら従業員の皆様は、経営者が思っている以上に他の事業所とのネットワークをしっかりと築いています。また、SNS等によって他事業所の情報がすぐに入ってきます。さらに、放デイの運営を担う児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者は今、引く手あまたです。
だからこそこれからの経営者は、児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者以上に、制度・法令の理解することが必要です。また、子ども達の有する障害特性についての理解も求められるでしょう。
②従業員の定着率をアップさせて報酬単価の向上も目指す
今回の改定(児童指導員等加配加算の見直し)によって、従業員の保有資格、経験年数、常勤職員の人数により報酬単価が大きく変わります。急に従業員が退職した場合、月20万から40万円の報酬を失うこともあります。
報酬改定により、多くの事業所で運営が厳しくなったという話を聞きますが、実は、正社員(常勤職員)・勤続年数が長い従業員が多い事業所の報酬は上がっています。
これから安定した運営を続けるには、従業員の定着率を上げていく必要があります。
定着率を上げる手法としては、人材育成カリキュラムの導入や職場環境の改善などが定番ですが、退職金制度がある事業所は少ないようです。制度の創設もご検討ください。
③児童発達支援管理責任者が業務に専念できる環境を作る
今回の改定、法改正により児童発達支援管理責任者の責任の範囲が拡大、業務量も増加しました。
しかし、現場の状況に目を移すと児童発達支援管理責任者が、「ほとんど現場に出ている」「運転手をしている」一方で「個別支援計画書は全ての同じ内容」―。このような事業所は多いのではないでしょうか。
制度改正に対応した個別支援計画書を作成するだけでもかなりの時間を要します。加えて、関係機関との連携や家族支援、インクルーシブの推進、現場のスタッフの教育への対応となると、現場に出る時間はありません。
求められる役割が明確化したほか、業務範囲も拡大している環境下で児童発達支援管理責任者が現場に出ている状況が続いているようでは、自治体の実地指導には耐えられません。経営者も児童発達支援管理責任者の仕事を理解し、現場で直接支援に当たる職員との摩擦が起きないようにするマネジメント能力を身に着けることが求められます。
④ライバルは放課後等デイサービス事業所だけではない―学童保育や学習塾に負けない強みを持つ
事業所数が増加し、多くの自治体で重症心身障害児以外の放デイ事業所の総量規制がかかっています。大阪市を例にすると、現在、1区あたり40近くの事業所が存在しています。
ここまで増えると、事業所を維持・発展させていくには、今まで以上に、「競合他社への対応」「集客」「顧客満足の向上」を意識し、注力する必要があります。
各事業所では、周辺にある放デイ事業所を意識した差別化を意識しているかと思いますが、これからは、「児童いきいき放課後事業(“いきいき教室”、大阪市)」、「のびのびルーム(堺市)」のような取り組みを含めて、公的・民間を問わず学童保育(以下、「学童保育等」という)が競合になる時代がきます。
こうした流れを引き起こす主な要素は以下のとおりです。
- 国は放課後等デイサービスが増えすぎたため財源の見直しを始めている。
- 預かることが目的の事業所が増えているが、預かりのニーズを満たすだけなら放デイである必要がない。
- 発達障害の可能性がある児童生徒は通常の学級に在籍する小中学生全体の8.8%という文部科学省の発表(2022年)。
こうした要素から、公金の投入によって学童保育等を強化する動きが全国で進むことが予想されます。そしておそらく、学童保育等が強化されると、「放デイを利用する理由がない」と判断する保護者様も増えてくるでしょう。現に、ある自治体では、放デイを利用する前に、「まずは学童保育等を利用して、学童保育等ではお子様の成長や安全が確保できないのであれば、放デイの利用を検討する」という流れを促しています。
また、③の8.8%問題に着目し、放デイの制度を利用せず、「発達障害に特化した学童保育+学習塾」、「大手学習塾による発達障害に特化した教室(クラス)の運営」、「eスポーツを活用したスクール」、「通信学校による専門的なカリキュラムの提供」を実施する事業所が現れるでしょう。
放デイ事業所としては、学童保育等や児童福祉の認可を得ていない事業者にはない、明確かつ独自の強みを持ち、子ども・保護者・地域・自治体から必要とされる事業所であることが必要です。 まずは、「保護者が月5万円を払ってでも来てくれる事業所になること」を意識してみてはいかがでしょうか。