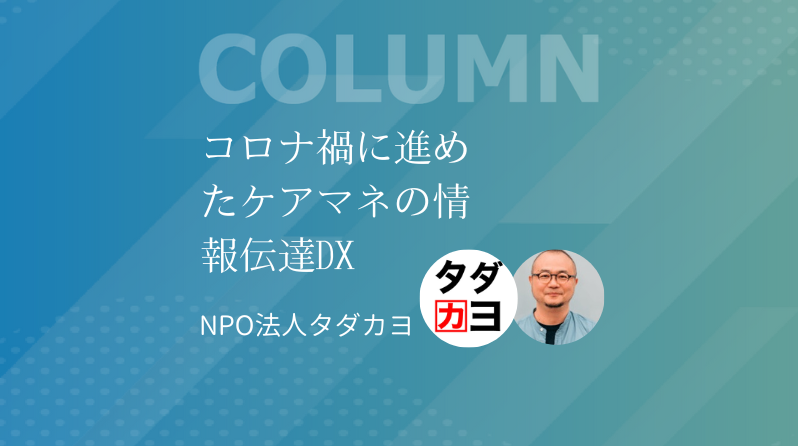私は、NPO法人タダカヨ理事の次田芳尚と申します。現在は、完全テレワーク型居宅介護支援事業所の代表取締役をしております。キャリアは在宅介護支援センターのソーシャルワーカーに始まり、老人保健施設の相談員、グループ全体の広報企画室長など幅広い職種を経験させていただきました。
私が専門学校を卒業した年は、「ウインドウズ95」というOS(オペレーティング・システム)が発表され、パソコンが一般業務に用いられるようになった時期でした。
めんどくさがり屋の私は「仕事はコンピュータに任せれば良い」という不純な理由で活用を始めたのを思い出します。
こんな私が、IT(インフォメーション・テクノロジー)・ICT(インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー)の活用を前提とした完全テレワーク型居宅介護支援事業所を立ち上げ、NPO法人タダカヨに賛同してJOINすることになった経緯と今後の展望についてお話しさせていただきます。
「書類への転記作業を減らしたい」から始まった業務効率化の取り組み
私は、株式会社279の起業に至るまで、介護現場やコンサルティングサービス、介護業務ソフトの開発会社と幅広い分野で経験を積んできました。
介護現場で初めて具体的な業務効率化に取り組んだのは、在宅介護支援センターに併設されていた特養のショートステイを担当していた時のことです。ショートステイでひとたびご利用者様の入所が決まると、様々な書類を作成するために、お名前やご住所、生年月日や性別などご利用者様の情報を何回も記載しなければいけません。めんどくさがり屋で字を書くのがとても苦手な私はこの仕事がとても苦痛でした。
そこで、「パソコンで入力をして、その入力データを選ぶだけで全ての書類が出来上がれば時間短縮にもなるし、汚い字で書く必要もない」と考えました。具体的には、ファイルメーカーというデータベースソフトを使って、自らショートステイの予約管理システムを作ることにしました。
このシステムを使って業務改善をした結果、予約受付からの処理はソフトに日付を登録するだけで、ほとんどの書類作成ができるようになりました。さらに全体的な業務改善が進んだ結果、月間稼働率をほぼ100%を維持することができ、返戻なども年間で数回という結果を出すことができました。
手書きが不要になった業務
- ベット管理表に線を引く
- 短期入所予約票を記入する
- 食事処方箋を作成する
- 介護記録用の用紙を準備する
- バイタルチェック表を用意する
- 短期入所介護サービス計画書を作成する
- 入所前にご利用者様に状態を確認させていただくお手紙を作成する など
ISO9001という認証との出会い
私にとってさらに大きな経験となったのは、ISOの取得に組織的に取り組んだことです。
みなさんは、ISO9001という認証をご存知ですか?簡単にいうと「ちゃんとした組織はこういう仕組みがあって品質が保たれている」という活動をしている組織を認証する制度です。
工場やサービス業などでは認証をとることがよくありますが、医療や介護においてもサービスの品質保証・向上のために取得する組織が一時期増えていました。私が所属していた法人グループでもISO9001の認証取得を目標として規定やマニュアルの整備を進めるにあたり、プロジェクトメンバーを務めさせていただくこととなりました。この経験によって、組織に必要な活動の種類や品質向上のための活動の基礎を学ぶことができました。実は、これがITやICTを使った生産性向上に大きく役立っています。
なぜなら、ISO取得では業務プロセスを「見える化」するか仮定があるからです。事故やヒヤリハットを整理し、助言を受けながら組織の業務プロセスを見直して改善していきます。その結果として生産性や品質の向上が実現するのです。この業務プロセスを見直す際に、デジタル技術を用いることがDX(デジタルトランスフォーメーション)のノウハウ取得に繋がります。とても良い経験をさせていただきました。
ケアマネジャーの仕事の確立とパソコンの普及
話は変わりますが、私は、介護支援専門員の資格を持っています。「ケアマネジメント」に初めて触れたのは、就職して初めての仕事である、在宅介護支援センターのソーシャルワーカーとしてでした。日本にケアマネジメントという言葉・手法が輸入され、広めなければいけないという時期に、在宅介護支援センターとしてケアマネジメントを地域で実践していました。その後、2000年に介護保険制度が施行され、今のケアマネジャーの仕事が確立してきました。ケアマネジャーの仕事は、正しくケアマネジメントを実施してご利用者様のニーズとサービスをリンケージ(繋げて)いくことです。介護保険が施行されると共に、介護の現場では一気にパソコンの利用が始まりました。あえて、パソコンの利用と書きますが、当時、インターネットはまだまだADSLで回線を引くのが一般的で、光回線が普及し始めてきた時期です。パソコンは使うが、まだインターネット技術はなかなか使われていない時代でした。インターネットは、単に「検索して調べる」ためのツールだった時代です。
「ケアマネジャーの働き方を変えたい」テレワークケアマネの事業所を創ったきっかけ
それから時代が10年ほど経過し、2007年にiPhoneが登場、2010年にiPadが登場しました。これらのプロダクトを生み出したスティーブ・ジョブズが世界を変革したと言っても過言ではないでしょう。これによって時代が一気に変わりました。
このころ私は、”事務所に出勤して仕事をして、その後ご利用者様のご自宅にモニタリングや介護サービス調整のために訪問し、再び事務所で残務等を行い帰宅する”というケアマネジャーの働き方に疑問を持つようになっていました。「ITを活用すれば、事務所で行う仕事は出先で行うことができる。それならば出勤の必要もないのではないか」と思うようになったのです。
そして、同じ思いを持った仲間と、テレワークケアマネの事業所を立ち上げようと思い至ったのが、2021年のことです。奇しくも時代はコロナ禍に突入していく時でした。この頃にはITの役割も検索ツールに留まらず、テレワークができる技術が多数出現し、一般的に使われてました。
居宅介護支援事業所の立ち上げに伴い、私たちが掲げたスローガンは、「ケアマネジャーの働き方改革」です。これを実現するために、「事務所にものは置かない」という選択からはじめました。例えば、ワードやエクセルなどのMicrosoftofficeソフトは使わず、GoogleWorkspaceを活用し、インターネット上の仮想パソコンに各ケアマネジャーのパソコンを設置、remotedesktopという方法で手元にある自身のパソコンやタブレットで仕事をする。こうした仕組みを取り入れることでパソコンの機種や、OSを問わずに作業ができるようにしました。電話はクラウドPBXを使用していて、固定電話を置いていません。外部との情報のやり取りにはインターネットFAXや、ビジネスチャットを使う―。こんな方法を確立してテレワークケアマネを始めました。
ケアマネジャーの1日の働き方とその変化
自宅〜事務所〜訪問〜事務所〜自宅
↓
自宅〜訪問〜自宅
完全テレワークを実現したことで時間に縛られない働き方を実現
みなさんはITを使って業務の効率化ができていますか?そして、その恩恵として働き方はどのように変わっていますか?
私たちは、IT、ICTを使った働き方を取り入れたことで「出勤時間」、「退勤時間」という概念がない雇用契約を実現しています。勤務時間についても、会社が定めた勤務時間を働いたとみなすという管理方法をとっています。裁量労働制という雇用契約です。
というのも、ケアマネジャーの仕事は、スケジューリングが第一だと思っています。ケアマネジャーそれぞれが最適なスケジューリングを行い、決まった仕事を的確にこなすことがまず必要です。これを実施するのに、出勤は不要だと考えました。そのため、全ての仕事はテレワークで実施します。当然会議もあれば事例検討会も行います。これらの開催にはGoogle Workspaceのビデオ通話やビジネスチャットを活用しています。
働きやすい労使関係を構築するための認証資格の取得
こうした取り組みが、働きやすい職場の証明になるように弊社では現在、「北海道働きやすい介護の職場認証制度」「トモニン」という制度の認証を受けています。さらに認証取得に向けて整備しているのは「エルボシ」と「健康優良法人」です。2024年度取得を目標に活動しています。
第三者機関の認証は、働いているケアマネジャーも経営陣も安心に繋がります。「所属している会社はしっかりしているのか?」また「自分たちが経営している会社は間違っていないのか?」という不安を払拭するシンボルにもなります。こうした、「心理的安全性」の確保は組織が最も注力すべきことだと思っています。
このように、働き方を自由にしながら労使関係もしっかり保つことで会社組織の基盤を固めています。
<注記:裁量労働制について>
裁量労働制には、決められた対象になる職種が決められていますが、残念ながら「ケアマネジャー」は含まれていません。また、この裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画型裁量労働制」があります。
このうち、「企画業務型裁量労働制」は、事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場に導入することができ、企業の経営に大きく影響を及ぼす職種などを対象に適用することができます。事前に法人や事業場(所)が所在する監督の労働基準監督署等に相談の上、手続きが必要です。
*参考:厚生労働省WEBサイト「企画業務型裁量労働制」https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/
志を同じくする仲間とこれからの介護業界のスタンダードを牽引する
ここでやっと、NPO法人タダカヨとの出会いの話になります。
NPO法人タダカヨは2025年までにタダでITを全国24万件の介護事業所に届けるという活動をしている団体です。何度か、私がタダカヨが主催する無料オンラインPCスクール・タダスクで、「テレワークケアマネの創り方」と題して、弊社の活動を発表させていただいたことから関係がスタートしました。2000年頃から、「介護IT」を掲げて、Apple銀座のセミナーホールでiPadを活用した介護の記録のことや「介護IT」をテーマに、ライトニングトークを繰り広げる集まりを仲間と行ってきました。今、やっと世間に自分が行ってきた活動が認知され始められ、介護業界のスタンダードとして動き始めたんだと強く認識しました。
ITやICTの活用と口にするのは簡単です。ただ、これらを使うだけでは働きやすい職場環境や生産性向上は実現しません。今回、私の実体験を書かせていただいたのは、皆様の現場で取り入れられるヒントを少しでも得て欲しかったからです。
私がテレワーク型の居宅介護支援事業を形にできたのは、「面倒くさがり屋」で「書くのが苦手」だったこと―、それと「ISO9001の品質管理の手法」を知り、「業務プロセスの見える化」に取り組んだ経験が「インターネット」によって結びついたことに始まっています。そして現在、自身の事業所で「働き方の改革」と「心理的安全性の確立」に取り組んでいるところです。
IT、ICTを使うことそのものは目的ではありません。「組織の目的を実現するためのIT、ICT活用とは何なのか」を今一度考えていただければ幸いです。