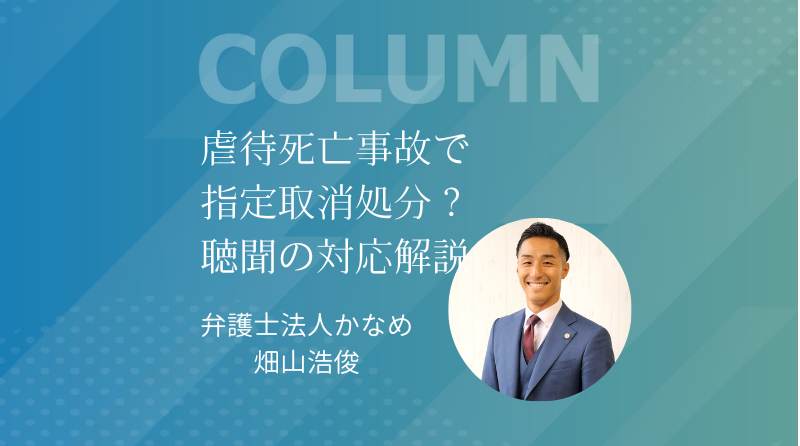今回は、虐待による死亡事故が起きてしまった介護施設を舞台に、指定取消処分をどのように争って事業継続ができるのか、という点を考察してまいります。
このような事故が起これば、施設は世間のバッシングを受けることになり、それに同調する形で行政も指定取消処分にするケースがあります。
しかし、取消処分の前提で必要とされる手続きを正しく理解していれば、不当に重い処分を避け、他の利用者や家族、職員らを守ることができる可能性があります。
筆者が複数の虐待事例や指定取消事例をベースに作成した架空の事例から考えてみましょう。
1.突如発生した傷害致死事件と監査の後に届いた通知書
ここは、とある介護施設。
ある日、非常勤で勤務していた男性職員Aが、利用者の入浴介護中、中々言う事を聞いてくれない利用者に対して苛立ちを覚え、熱湯をかけるという虐待行為に及んだ。
重度の火傷を負った利用者は救急搬送されたが、ほどなく死亡してしまった。
男性職員Aは、警察に傷害致死罪の容疑で逮捕され、この事件は全国で大きく報道された。後日分かったことだが、どうやら男性職員Aは、他の利用者にも軽微ではあるが、身体的虐待を複数回行ったことがあったようだ。
捜査機関への対応、マスコミからの取材対応、地域住民からの苦情電話対応等々、この介護施設の運営会社は怒涛のように押し寄せる対応に追われた。
高齢者虐待防止法に基づき、行政に通報し、重大な虐待事件であることから、行政の監査が実施された。
行政の監査の実施後、行政から一通の文書が届いた。
その文書には、「聴聞通知書」との題名が付されており、予定される不利益処分の内容に、「指定の取消」と書いてある。
これを見た介護施設の経営者は驚愕した。
「指定の取消!?他の利用者の方もいるのに、施設運営を強制的に終了しないといけないということなのか?一体どうすれば良いのだ・・・」
この事例を読んで、「いつ自分のところで発生するか分からない虐待事件だ」と感じた読者も多いのではないでしょうか。
「利用者に熱湯をかける」という身体的虐待行為は、悪質極まりない蛮行です。死亡という重大な結果も相まって、マスコミは全国で大きく報道することでしょう。 行政も、監査を実施し、当該介護事業者に法令違反が無いか徹底的に調べ上げます。
この事例では、行政側は、監査の実施後、聴聞という手続きを実施しています。
「聴聞通知書」という文書には、指定取消という文言が記載されています。
指定が取り消されると、国保連に介護報酬を請求することができなくなるため、介護事業を継続することはできなくなります。これに加え、指定の取り消しを受けた介護事業所は、取消処分を受けてから5年間、新たに介護事業所の指定をとることができません。最も重い処分です。
多くの介護事業者にとって、聴聞という手続きなど聞いたことも無いのではないでしょうか。
だからこそ、いざ聴聞通知書が手元に届いても、どのように対応すれば良いか分からず、行政側が淡々と手続きを進めていき、気付けば指定を取り消され、事業を廃止せざるを得なくなるケースも多く存在しています。
たしかに、法令遵守が求められる介護事業運営において、重大な虐待事件が発生した場合、何らかのペナルティがあることはやむを得ません。しかしながら、指定が取り消されてしまうと、その介護事業所を利用している他の利用者、そのご家族、そこで働く職員らの関係者全てに重大な影響が生じてしまいます。
果たして、行政から聴聞通知書が届いてしまったら、もはや指定取消という結果については、争うことはできないのでしょうか。
この記事では、指定取消処分を聴聞段階で争う方法について解説します(他にも争い方は複数ありますが本稿では聴聞に焦点を絞り、他は割愛します。)。
2.指定取消処分と聴聞
聴聞とは、行政庁(ここでは地方公共団体の意)が許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときに実施しなければならない行政手続法上の手続きであり、不利益処分(今回では指定取消処分)が行われる前の最後の反論の機会です(行政手続法第13条1項1号イ)。
法的には、行政庁に対する不服申立てや取消訴訟等、後日、指定取消処分の是非を争う手段はあるものの、一度指定取消処分が出されてしまうと、それらの手続きでは中々勝ち目がないのが現状です。取消処分が出される前の段階で、如何に行政に有効な反論を試みることができるかが最重要ポイントになります。
今回は、指定取消の場面ですから、この聴聞手続きの中で反論をしていく事になります。
3.聴聞への対処法
逆説的ですが、まずは、聴聞手続きの中で一番やってはいけない方法を紹介します。
それは、
・頑張っている事業所なので、取消処分だけは勘弁して下さい。
・指定取消になると、多くの利用者や職員が路頭に迷います。
という、いわば『お涙頂戴』の戦法のみを用いて処分を軽くしてもらおうという方法です。残念ながら、これは、全くもって無意味です。
筆者は、元公務員で聴聞に参加経験のある人から「既に取消処分を出す内部決裁は通っています。聴聞は単なる儀式と思っている職員が多数です。」との話を聞いたことがあり、これが実態(もしくは実態に限りなく近い実情)だと思います。
ですから、お涙頂戴戦法は全く無意味です。
必要な戦い方は、法的な論争です。
つまり、聴聞手続きにおいては、行政庁が指定取消処分と判断した根拠が何か、それが法的に正しいのか、行政庁が適用した法令について、その解釈が法的に正しいのかを徹底的に分析し、介護事業所側の法的見解を真正面からぶつけ、行政庁側に処分の内容を「法的に再考させる」ことが必要なのです。
(1)聴聞期日前に必ず資料の閲覧、謄写を求める。
徹底した準備をするために必要なことは、行政庁の不利益処分を根拠付ける資料の確認することです。行政手続法第18条1項に基づき、聴聞通知があった時から、文書等の閲覧を求めることが可能ですから、必ず実施しましょう。なお、資料は膨大な数になることが多いことから、単に「閲覧」ではなく、「謄写」まで求めると良いでしょう。行政手続法には「謄写が可能」とは規定されていませんが、謄写を依頼すると応じてくれる行政庁もありますので、謄写を依頼して下さい。
(2)聴聞期日の場で主催者の許可を得た上で、質問権を行使する。
資料の閲覧、謄写により取得した資料を基に、いかなる理由で不利益処分を行おうとしているのかを法的に分析し、行政庁が指摘する不利益処分の理由に、法的な理論構成の不備が無いか徹底的にチェックします。その上で、法的に疑義がある点について、行政庁に対する質問状を作成します。
具体的な質問権の行使の方法としては、聴聞期日当日に、聴聞主宰者の許可を得て、作成した質問状を行政庁の職員に交付した上で質問します(行政手続法第20条2項)。
一例を挙げます。
ケースの事例では、行政庁は、男性職員Aが利用者に熱湯をかけて死亡させたという事実、その他、男性職員Aが他の利用者にも複数回身体的虐待を行っていたという事実を、介護施設に人格尊重義務違反(介護保険法第78条の10第6号等)があったことを理由として指定取消処分相当と判断しています。もっとも、この条項に該当するには、介護事業者が人格尊重義務に違反したという点を満たす必要があります。
少し分かりにくいかもしれませんが、問題とすべきなのは、介護事業者の人格尊重義務違反であって、職員個人の人格尊重義務違反ではありません。つまり、同条号に該当すると言えるためには、職員個人の行動の問題性だけではなく、その問題行動について、介護事業者の組織的関与があったかどうかを議論する必要があります。
ケースの事例のように突発的に生じた身体的虐待は、管理者にとっても全くの想定外であることが多く、組織的関与が無い場合も多いです。しかしながら、行政庁は、利用者に熱湯をかけて死亡させるという結果の重大性から、職員の虐待行為が介護事業者による組織的関与によるものかという検討をせずに、直ちに「介護事業者に人格尊重義務違反がある」と認定する場合があります。この認定は、法解釈を誤ったものであり、問題があります。
そのため、聴聞の場では、行政庁の職員に対し、介護事業者が日ごろから、虐待研修を行っていたか、虐待防止のマニュアルがあったか、他に虐待行為は無かったのか、それを他の職員や管理者は見過ごしていなかったか等の組織的関与の有無・程度を、行政庁がどの程度調査しているのかについて、きちんと質問する必要があります。
上記はあくまで一例ですが、行政庁の判断過程には、時には重大な事実誤認があったり、上記のように法令解釈を誤解したりしている事例も散見されます。聴聞通知書に記載されている行政側の言い分を読むと、如何にも全て介護事業者側に非があるように見えるかもしれませんが、きちんと資料を閲覧謄写して、法的な観点から分析することが大切です。
(3)聴聞期日を続行に持ち込むことが大切
上記のように、質問状を行政庁の職員に交付して、口頭でも補足説明を加えながら、行政庁の予定する処分の内容に法的に疑義があることを伝え、さらに行政庁に対して、質問状に対する回答を書面で行うように伝えます。行政庁としても、処分の名宛人である介護事業者から具体的に質問を出されたにもかかわらず、これを無視して簡単に処分に踏み切ることはできません(実際には無視する行政庁もありますが、その際の対応は紙面の関係上割愛します。)。
聴聞期日を一回で終わらせず、続行に持ち込むことができれば、続行期日までの期間、行政庁も質問状の内容を精査し、自らの行おうとしていた処分内容を見直し、場合によっては、予定されていた処分内容が変更され、介護事業者にとってはより打撃の小さい処分になることがあります。
実際、ケースに類似した事例では、虐待行為に関する組織的関与の有無について論争した結果、行政庁側も、虐待事件に関する組織的関与が無いと判断して、指定取消処分を取りやめると方針変更したことがあります。介護事業者にとっては、事業継続が可能になる訳ですから、非常に大きな結果といえます。
4.疑問に感じたら聴聞対応に詳しい弁護士へ相談を
本稿では、指定取消処分が実施される前の聴聞段階で、如何に行政庁と議論し、処分内容の変更を求めるのかについて考察しました。もっとも、お気付きの通り、上記対応は高度な法的素養が求められます。また、弁護士の中でも介護行政対応に慣れていない弁護士でないと対応が困難です。
行政処分の内容に違和感を覚えた介護事業者の方々は、諦めずに聴聞の場を有効に活用して下さい。その際、介護行政対応に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
最後に、弁護士法人かなめの運営する介護業界に特化した法律メディア『かなめ介護研究会』では、より詳しく介護事業の指定取消し、指定の効力停止処分等に関する詳細な解説をしております。こちらの記事も合わせてご覧下さい。