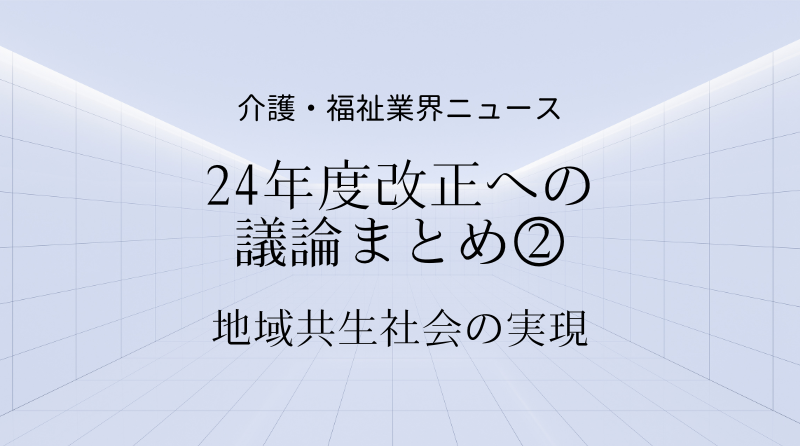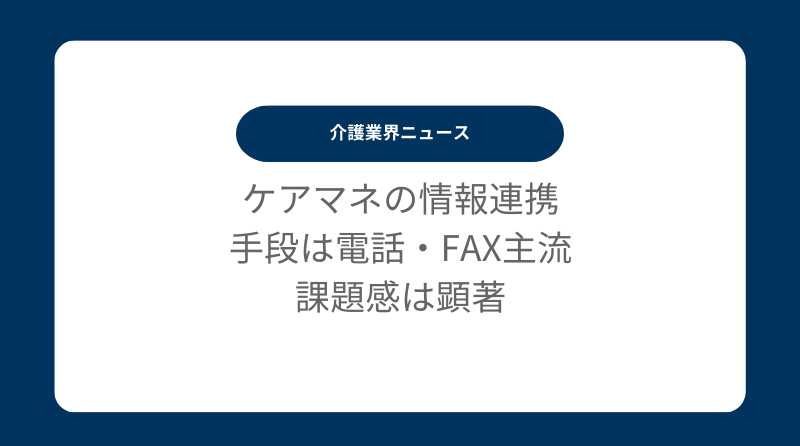2022年末にまとめられた社会保障審議会・介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」には、「共生社会の実現」のスローガンの下で第9期介護保険事業計画期間中に市町村の地域支援事業を充実させていく方針などが記載されています。これは、要介護1・2の人への生活援助サービス等を保険給付から外すかどうかの結論を、27年4月までに出すとされたことともつながります。また、介護保険制度の今後の動向を示すポイントとして、ケアプランにおける介護保険外サービスの位置付けも抑えておきたいところです。今年からは介護報酬改定に向けた検討が始まります。これまで明らかになっている内容について総点検しておきましょう。
地域支援事業の充実化と地域包括支援センターの業務負担軽減が主な施策に


同部会の意見書に沿うと、24年度の制度改正は「地域包括ケアシステムの深化・推進」と「介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」の大きく2つの柱を掲げて行われることになります。
(*こちらで介護サービス等の基盤の整備について、こちらで小濱道博氏による意見書全体のポイント解説を紹介しています。)
前者には、介護サービス等の基盤整備のほか、「様々な生活上の困難を支え合う共生社会の実現」と「保険者機能の強化」に関する施策が盛り込まれています。さらにひとつひとつの項目に目を通すと、地域包括支援センターの体制整備と市町村の地域支援事業に関する記載が目立ちます。
総合事業への要介護1・2向けサービス移行は27年4月までに結論
介護保険制度改正の趣旨としての「地域共生社会の実現」
”地域共生社会の実現”は16年以降の福祉改革(障害福祉や困窮者支援分野を含む)で掲げられているコンセプトです。近年は、高齢者の生活を支える”地域包括ケアシステム”もこの地域共生社会を実現するための基盤として位置付けられています。
こうした方向性のもと18年介護報酬改定では、障害福祉の指定を受けた事業所が介護保険の訪問介護や通所介護、短期入所生活介護の指定を受けられる特例的な基準が新設されました(共生型サービスの創設)。その後21年の制度改正(20年の介護保険法や社会福祉法の改正)では、8050問題など地域住民が抱える複合的な課題への市町村の対応力の強化が図られるなどしています。
では24年度に迫った次期改正では、この文脈に沿ってどのような改革が行われるのかみていきましょう。
(基本的な視点)
〇介護保険法において、国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされている。地域支援事業は介護予防・重度化防止や自立した日常生活の支援のための施策を、地域の実情に応じて多様な主体の参画を得つつ実施する事業であり、これらの取組を推進していくことは、様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現を図っていく上でも重要である。
(総合事業の多様なサービスの在り方)
〇介護予防・日常生活支援総合事業は、既存の介護サービス事業者に加えて、住民主体の取組を含む、多様な主体によって介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるようにすることで、 市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行えるようにすることを目的とした事業である。平成26年法改正から一定期間が経過しており、総合事業の実施状況等について検証を行いながら、地域における受け皿整備や活性化を図っていくことが必要である。
〇この観点から、従前相当サービスやそれ以外のサービスの事業内容・効果について実態把握・整理を行うとともに、担い手の確保や前回制度見直しの内容の適切な推進も含め、総合事業を充実化していくための包括的な方策の検討を早急に開始するとともに、自治体と連携しながら、第9期介護保険事業計画期間を通じて、工程表を作成しつつ、集中的に取り組んでいくことが適当である。 また、自治体が総合事業などを活用した地域づくりを行う際の参考となるよう、取組を進める趣旨や方法をわかりやすく、体系立てて示すとともに、自治体の取組事例の分析結果等について周知することも重要である。
〇その際、介護保険制度の枠内で提供されるサービスのみでなく、インフォーマルサービスも含め、地域の受け皿を整備していくべきであり、生活支援体制整備事業を一層促進していくことが重要である。 また、生活支援・介護予防サービスを行うNPOや民間企業等の主体が、生活支援体制整備事業における協議体へ参画するに当たって一定の要件を設けるなど、多様なサービスについて、利用者やケアマネジャーがケアプランの作成時に適切に選択できる仕組みを検討することが適当である。
「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下・総合事業)については、要介護1・2の人に対する訪問介護・通所介護サービスを移行するのかどうかが注目されてきました。24年度改正での実施は見送られたものの、意見書では今後の方針として、27年4月までにこれを結論づけることが示されています(給付と負担の見直しについてまとめた章)。

地域共生社会の実現にむけた施策をまとめた章でも、前述の通り、総合事業を含む地域支援事業の充実策について多くの言及があります。ここでは、第9期介護保険事業計画期間(24年4月~27年3月)の間に、総合事業の充実化に向けた取り組みをスケジュールを決めて確実に進めることが強調されています。
これは、要介護1・2の人への訪問介護・通所介護の移行に反対する理由として、総合事業が移行先の受け皿として不十分であるとされてきたことと関係しています。言い換えると、今回、総合事業への移行のためのロードマップが描かれたといえるでしょう。
インフォーマルサービスのケアプランへの位置づけ
また、 総合事業の整備に関しては、本意見書でインフォーマルサービスにも言及されています。ここではさらに、ケアプランとの関連についても明記されています。具体的には、ケアプラン作成時において、インフォーマルサービスを含む「多様なサービス」を”選択肢に組み込む仕組みづくり”を、24年度改正に向けた検討事項としています。こちらは、23年から始まる議論の動向が注目されます。
居宅介護支援事業所で介護予防支援の指定や相談窓口の一部を受けられるように
(地域包括支援センターの体制整備等)
〇地域包括支援センターは、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする機関であり、地域の関係者とのネットワークの下、総合相談支援などの包括的支援事業や介護予防支援等の支援を行うとともに、 こうした取組を通じて市町村と一体となって地域課題の把握やその対応策の検討等を行うことが期待されている。 また、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、重層的支援体制整備事業において、介護分野に限らず、障害分野、児童分野、困窮分野 も含めた、属性や世代を問わない包括的な相談支援等を行うことなども期待されている。
〇認知症高齢者の家族を含めた家族介護者の支援の充実のためには、こうした地域包括支援センターの総合相談支援機能を活用することが重要であるが、 総合相談支援機能を発揮できるようにするためにも、センターの業務負担軽減を推進するべきである。また、家族介護者支援においては、地域包括支援センターのみならず、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走型支援、認知症カフェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護の両立支援などの取組との連携を図ることが重要である。
〇 こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地域包括支援センターが地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援センターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大することが適当である。 また、総合事業において、従前相当サービス等として行われる介護予防ケアマネジメントAについて、利用者の状態像等に大きな変化がないと認められる場合に限り、モニタリング期間の延長等を可能とすることが適当である。
また、総合相談支援業務について、センターの専門性を活かした効果的な実施等の観点から、居宅介護支援事業所などの地域の拠点のブランチやサブセンターとしての活用を推進することが適当である。総合相談支援業務はセンターが行う根幹の業務であることを踏まえ、質の確保に留意しつつ、センターの業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を可能とすることが適当である。
〇センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏まえ、3職種(保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者)の配置は原則としつつ、センターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数拠点で合算して3職種を配置することや、「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当である。
地域包括支援センターは24年度改正で業務に関わるルールや人員配置要件など多くの改革が行われそうです。また、その連携先の居宅介護支援事業所にも新たな対応が求められるようになりそうです。特に、包括支援センターによる一定の関与(実施状況の把握など)の下で、居宅介護支援事業所が要支援1・2の利用者を直接担当する仕組みが導入されるという点は大きな変更と言えます。ただ、これがどこまで広がるかは介護予防支援費の動向次第で、これから始まる社保審・介護給付費分科会の検討でも焦点となるでしょう。


(画像:24年度制度改正における地域包括支援センターの変更点に関する参考資料。※第105回社会保障審議会介護保険部会参考資料より)