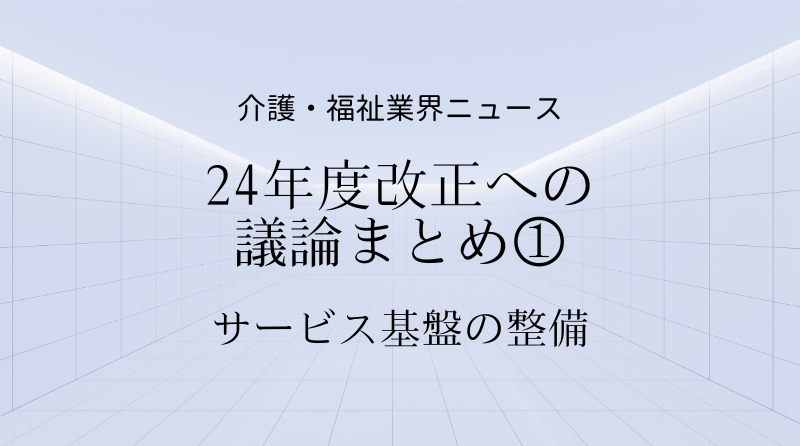社会保障審議会・介護保険部会は20日、2024年度の介護保険制度改正に向けた審議の結果を「介護保険制度の見直しに関する意見」にまとめています。今後、介護保険法の改正案などもこの内容に大きく影響されながらまとめられることになります。
最終的な部会の審議結果の概要と、介護施設や事業所の運営や展開に影響しそうな「介護サービスの基盤整備」の方針に関する記載について、概要と関連するサービスを整理します。
2024年度改正に向けた「介護保険制度の見直しに関する意見」の全体像


(【画像】社会保障審議会介護保険部会意見(概要)より※赤枠、赤枠内の文字を編集部で追加)
同部会の意見書は、「地域包括ケアシステムの深化・推進 」と「介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」の主に2部構成となっています。前者では、地域差のある将来の介護サービスへのニーズに応じつつ、効率的なサービス提供体制が確保できるよう国による施策の実施や都道府県・市区町村の計画策定を促しています。課題認識や方針の説明にある”医療需要への対応”、”DXの推進”、”予防や社会参加の促進”などといったキーワードは概ね前回改正と同様のものが使われています。
(*こちらで小濱道博氏による介護保険部会意見書のポイント解説を紹介しています。)
ここからは、「意見書」のうち、介護サービス等の基盤整備の記載を1つずつ確認していきます。
在宅サービスの基盤整備
関連サービス:通所介護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護
〇地域の実情に合わせ、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を進めていくことが重要。
〇 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護の更なる普及に加え、例えば、特に都市部における居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、 複数の在宅サービス(訪問や通所系サービスなど)を組み合わせて提供する複合型サービスの類型などを設けることも検討することが適当。 また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護など、機能が類似・重複しているサービスについては、将来的な統合・整理に向けて検討する必要がある。
〇 看護小規模多機能型居宅介護は、主治医との密接な連携の下、通い・泊まり・ 訪問における介護・看護を利用者の状態に応じて柔軟に提供する地域密着型サービスとして、退院直後の利用者や看取り期など医療ニーズの高い中重度の要介護者の在宅での療養生活を支えている。今後、サービス利用機会の拡充を図るため、地域密着型サービスとして、どのような地域であっても必要な方がサービスを利用しやすくなるような方策や提供されるサービス内容の明確化など、更なる普及を図るための方策について検討し、示していくことが適当。
個別にサービス名が挙がっている項目としては、訪問や通所系サービスなどを組み合わせたサービスの創設や看護小規模多機能型居宅介護の普及の強化・継続を図る方針が記載されています。
機能が類似・重複しているサービスの統合・整理についても検討が行われてきましたが、こちらは「将来的に検討」という記載に留まり、24年度の改正では結果として見送られる方針です。
ケアマネジメントの質の向上
関連サービス:居宅介護支援
〇法定研修のカリキュラムの見直しを見据えた適切なケアマネジメント手法の更なる普及・定着を図るとともに、オンライン化の推進や受講費用の負担軽減を含め、研修を受講しやすい環境を整備していくことが重要。
〇各都道府県における主任ケアマネジャー研修の受講要件等の設定状況を踏まえ、質の高い主任ケアマネジャー養成を推進するための環境整備を行うことが必要である。 また、介護サービス全体として、科学的介護が推進されているところ、ケアマネジメントについてもケアプラン情報の利活用を通じて質の向上を図っていくことが重要。
〇現在、マイナンバー制度を活用した「国家資格等情報連携・活用システム(仮称)」の構築について検討が行われているところであり、ケアマネジャーに関する資格管理手続の簡素化等に向けて、こうしたシステムが活用できるような環境整備が必要。
居宅介護支援については、ケアマネジャーに求められるスキル向上を支援するための国や自治体の方策などがまとめられています。 この中では、24年4月から予定されている法定研修のカリキュラムの見直しを見据え、受講費用を含めた負担軽減を整備していくことの重要性も明記されています。また、具体的な時期の記載はありませんが、マイナンバー制度を活用した資格管理に向けて環境整備が進められていく方針です。
福祉用具の貸与と販売の選択制の導入
関連サービス:居宅介護支援、福祉用具貸与
介護保険制度における福祉用具については、別に集中的な専門の検討会が立ち上げられ、今後の見直しについて一定の整理が行われています。
(*参考記事:次期介護保険制度改正へ福祉用具販売と貸与の「選択制」導入など検討事項とりまとめ)
ここでは、特に歩行補助つえや手すりなどの一部の品目を「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」のどちらの制度を使うか利用者が選択できるようにすることの可否について検討を進めていくものとしています。
「医療・介護連携」「地域における高齢者リハビリテーションの推進」「かかりつけ機能との連携」
これら項目では主に、在宅医療・介護連携の推進など方針に沿った自治体の体制づくりなどについて記載されています。医療保険制度の方向性なども踏まえ、別稿で整理します。
また、これまで、社会保障改革や医療保険制度の改正に向けて「かかりつけ医機能」の制度上の位置付けを明確にするための議論が行われてきました。この結果、都道府県がかかりつけ医の役割を持つ医療機関を公表する方針が打ち出されています。この要件には介護サービスとの連携が含まれることが想定されますが、詳細は来年以降に議論されます。
「施設入所者への医療提供」「施設サービス等の基盤整備」
関連サービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護
〇特別養護老人ホームにおける医療ニーズへの適切な対応の在り方について、配置医師の実態等も踏まえつつ、引き続き、診療報酬や介護報酬上の取扱いも含めて、検討を進めることが適当。
〇介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援の機能、介護医療院の医療が必要な要介護者の長期療養・生活施設としての機能をそれぞれ更に推進していく観点から、必要な医療が引き続き提供されるよう取組を進めることが必要
〇介護施設について、既存資源の有効かつ効率的な活用の観点から、地域のニーズを踏まえた在り方や更なる役割・責務を考えていくことは重要。
〇特別養護老人ホームの入所申込者数については、足元の状況をみると、全体としては減少傾向がみられ、地域によっては、高齢者人口の減少のために空床が生じている場合や、人手不足により空床とせざるを得ない場合等もあるとの実態が生じている。その中で、要介護1・2の高齢者に係る特例入所については、地域によってばらつきがあるとの報告もある。
〇特別養護老人ホームが在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等を踏まえ、特例入所の運用状況や空床が生じている原因などについて早急に実態を把握の上、 改めて、特例入所の趣旨の明確化を図るなど、地域における実情を踏まえた適切な運用を図ることが適当である。
〇混合型特定施設入居者生活介護については、実利用定員に「7割を超えない範囲で都道府県が定める割合」を乗じたものを推定利用定員とし、都道府県の介護保険事業支援計画において定めた必要利用定員総数を超えるような指定は行わないことができるとされている。 自治体によっては、混合型施設に7割以上の要介護者が入居している場合もあるため、推定利用定員の算出については、より柔軟に地域の実情に合わせることが適当である。
介護保険施設や入居型サービスについては、報酬改定に向けてそれぞれの機能強化や分化が議論の俎上にのりそうです。特養の特例入所についての規定や、既存施設の活用など利用者層の減少を見据えた記載も目立ちます。また、自立・要支援者・要介護者の入居ができる混合型特定施設の総量規制の柔軟な運用についても言及されています。
住まいと生活の一体的支援
独居の困窮者・高齢者等の住まいの確保を社会保障の重要な課題として位置づけ、本格的に施策を展開すべきとしています。支援対象者のニーズや背景、各地域で活用可能な資源がさまざまに異なることを踏まえ、国や自治体での介護保険部局や住宅部局等の連携や役割分担について、検討を継続する方針が示されています。
「介護情報利活用の推進」「科学的介護の推進」
介護レセプトや要介護認定情報、LIFE(科学的介護情報システム)情報、ケアプランの情報などを電子的に管理し、全国どこからでも閲覧したり、共有したりするプラットフォームを構築するための検討が進んでいます。今回の意見書には、この情報収集や提供が市区町村の事業として行われる方針であることが記載されています。
また、LIFEに関しては、フィードバックの改善と収集項目の精査について重要性が指摘されています。事業所・施設側の入力負担軽減についても触れられており、加算算定などに必要な情報を絞っていくことが示唆されています。
「介護現場の安全性の確保」「リスクマネジメントの推進」
介護現場の安全性を確保するための自治体による取組を広げるため、具体的な方策を進めます。介護事業者に対する規制等には言及されていません。
高齢者虐待防止の推進
関連サービス:サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム/在宅サービス
サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、介護保険法の規定に寄らない高齢者向けの住まいに対して、虐待防止措置を講じるための指針の整備などが検討される方針です。
また、在宅サービスにおける身体拘束の適正化を図るための「介護報酬上の取扱い」も検討事項となっています。
これとは別に、介護サービス事業所・施設の職員や家族らの心理的負担の軽減策の推進についても重要性が指摘されています。
24年度介護保険制度改正・介護報酬改定に向けた検討へ状況まとめ
部会の結論として、今後の検討が「適当」とされたものは、24年度介護保険制度改正・介護報酬改定での対応に向けて詳細を詰めていくものと考えられます。
ここまでに紹介した項目のうち、事業者との関係が深いものを振り返ります。
- 複数の在宅サービス(訪問や通所系サービスなど)を組み合わせて提供する複合型サービスの類型の設置
- 看護小規模多機能型居宅介護の更なる普及を図る方策
- 福祉用具貸与・販売種目の在り方や福祉用具の安全な利用の促進
- 特別養護老人ホームの配置医師の取扱い
- 特別養護老人ホームの特例入所の趣旨の明確化と運用の見直し
- 混合型特定施設入居者生活介護の総量規制についての柔軟化
- LIFEに関する入力負担の軽減、収集項目の精査
- サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等が虐待防止措置を適切に講じるための方策の推進(指針の整備など)
- 在宅サービスにおける身体拘束の適正化を図るための介護報酬上の取扱い
これらの動向について具体的な動きがあれば、引き続き介護経営ドットコムで紹介してまいります。