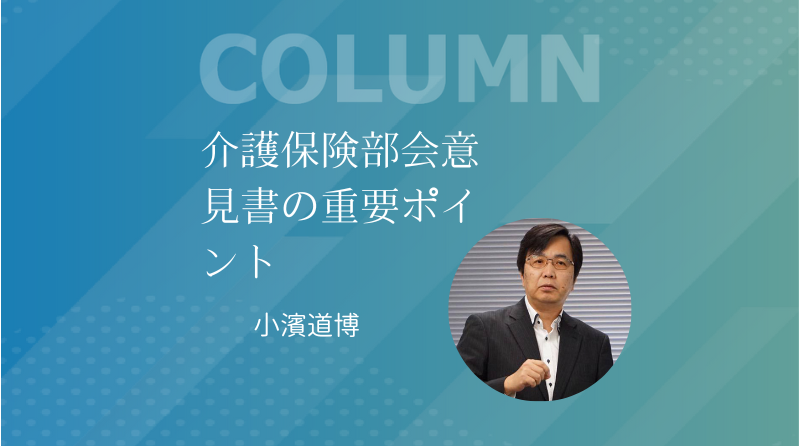1,多くの論点が先送りされる改正に
12月20日に社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられた。しかし、自己負担2割の拡大、1号保険料負担の高所得者の標準乗率の引上げ、介護老人保健施設などの多床室の自己負担化などの論点は、「次期計画に向けて結論を得ることが適当である」とされて遅くとも来年夏までに結論を出す事とされた。また、軽度者の総合事業への移行や、ケアプランの自己負担化の論点が3年後の審議に持ち越されたことから、軽微な介護保険法改正に留まったという介護事業経営者の声を聞くことが多い。では、その中身はいかなるものか。
2,12年ぶりに在宅サービスに新型サービスが創設
まず、2012年改正で創設された、定期巡回随時対応型訪問介護看護と複合型サービス(現在の看護小規模多機能型居宅介護)以来、12年振りに在宅サービスに新型サービスが創設される。これは、訪問介護と通所介護の複合型であると言われる。複合型としては、すでに小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合である看護小規模多機能型居宅介護が存在している。訪問介護と通所介護の複合型(まだ未確定である)については、今回の審議においては、24年度から新サービスとして創設される事のみが決まっている。その詳細や指定要件、報酬体系などについては、23年度において介護給付費分科会において行われる令和6年介護報酬改定審議の中で検討されることとなった。
また、「複合型サービスの類型などを設ける」と記載されていることから、複数の組み合わせが検討される可能性も低くは無いだろう。
訪問介護と通所介護の複合型サービスについて、現在のサービスで最も近いイメージは、小規模多機能型居宅介護からショートステイを除いた形態であろうか。
現行の小規模多機能型居宅介護の
・施設ケアマネジャーが配置されていること
・訪問サービス担当者は、初任者研修修了者などの医療福祉関連の資格が求められないこと
・介護報酬が月額定額制であること
・地域密着型サービスに位置づけられていること
といったポイントを踏まえ、新設サービスの訪問サービス担当者に医療福祉関連の資格を求めないとした場合、大きな制度上の転換となるだろう。訪問介護サービスは、介護職員の有効求人倍率が15倍前後という非常識な人材不足に喘いでいる。小規模多機能型同様に資格を求めない場合は、このサービスの普及が早期になされるだろう。
この点について、介護保険部会における厚労省の説明にあった、“コロナ特例としての通所介護の介護職員による訪問サービス”が大きなヒントになりそうだ。これは、コロナ禍の影響で通所介護サービスが休業等を行った場合、通所介護の介護職員が利用者の居宅を訪問してサービスを提供することが認められたものだ。この訪問を担当する介護職員には医療福祉関連の資格は求められない。これを踏まえると、今回の新サービスでも、訪問の担当者に資格が求められないことが期待出来そうだ。介護報酬については、間違いなく月額包括報酬が選択されるであろう。2000年に介護保険制度が創設されて以来、新たしく創設されたサービスはすべて月額包括報酬である。厚労省は、既存のサービスも月額包括報酬としていく見解を示していることからも明らかだろう。いずれにしても、その詳細は23年から始まる介護報酬改定審議の中で明らかになるので、期待を込めて審議を待ちたい。
3,財務諸表の公表義務化とそれに伴う事務作業の増加
「見直しに関する意見」では、24年度から、介護サービス事業者にも財務諸表の公表が義務化される方針も示されている。なお、この方針は、すでに骨太の方針2022や財務省の財制度分科会においても示されていた。介護事業者は、決算が終了すると、財務諸表等の経営に係る情報を定期的に都道府県知事に届け出ることとなる。この公表については、介護事業者が提出した個別の事業所情報を公表するのではなく、属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表するとされている。このため、一部で不安視されている、自事業所の経営状態や役員報酬の金額などが利用者・家族に把握されてしまうという懸念は杞憂である。
提出する財務諸表データは、単に税務署に提出した決算書そのものでは無いだろう。介護事業者は、「会計の区分」に従って財務諸表を作成しなければならないとされている。「会計の区分」とは、厚生省令37号などの解釈通知に規定された運営基準の一つである。同一法人で複数のサービス拠点を運営している場合は、その拠点毎に会計を分けなければならない。これを会計用語では「本支店会計」と言う。同一の拠点で複数のサービスを営んでいる場合は、それぞれを分けて会計処理を行う。これを「部門別会計」と言う。
会計を分けるとは、少なくても損益計算書をそれぞれの拠点毎、介護サービス毎に別々に作成するということである。このとき、収入だけではなく、給与や電気代、ガソリン代などすべての経費を分けなければならない。これは、税務署に提出する決算書には求められていない作業である。この作業は運営基準での規定であるため、すべての介護事業所において、毎期継続して実施している必要がある。厚労省の側から見ると、当初からの制度上の義務である事項のため、負担増にはならない。しかし、現実にはこれを実施している事業者は少なく、特に小規模法人での事務負担の増加が懸念される。
4,介護助手制度で介護施設の人員配置を緩和へ
厚労省が新たに設ける介護助手制度も重要なポイントだ。これは、地域の元気な高齢者を介護助手として雇用することによって食事の配膳や清掃業務などを担ってもらい、介護職員の負担を減らしていくことが目的とされる。介護施設では、介護職員は入浴介助や排泄介助などの本来業務と共に、食事の配膳、清掃、シーツ交換、入浴後の髪へのドライヤー掛け、備品の補充など、多くの間接的な業務も担当していることが多い。これでは、介護職員が何人居ても足りないであろう。このような間接的な業務を、地域の元気な高齢者や、子育てが終わった主婦層を介護助手として雇用して担当頂く事で明確な役割分担が実現し、介護職員は本来業務に集中出来る。組織全体の職員の頭数を減らすのではなく、施設内で役割分担を明確にして、介護職員の負担を減らすのが目的である。
一方で厚労省は今回、介護保健施設などの人員基準配置を、現在の三対一配置から、四対一配置に緩和する方向を示しており、その緩和要件として、ICT化の最大限の推進と介護助手制度の導入を検討している。また、今後の制度改正や介護報酬の算定要件等に位置づけることも検討中である。介護助手として雇用した職員は、その適性を見極めた上で、介護職員などにキャリアアップすることも可能で、職員確保の一手段となり得る。
5,令和6年(2024年)介護保険法改正は決して軽微な改正では無い
前述したとおり、今回の介護保険部会での取りまとめでは、利用者の自己負担2割における対象拡大など、給付と負担に関する項目の多くの結論が、来年の骨太方針2023まで持ち越しとなる異例の事態となった。これは、医療保険の自己負担拡大が重なっていることからの措置とされる。しかし、現内閣の支持率の低下と春の統一地方選の影響を回避したとの見方も出来る。利用者自己負担2割の対象拡大などについては、27年度制度改正まで持ち越すことなく、24年度改正で実現したいという強い意志を感じる。これらのことを含めて、24年の介護保険法改正は、近年に無い大改正であるといえる。