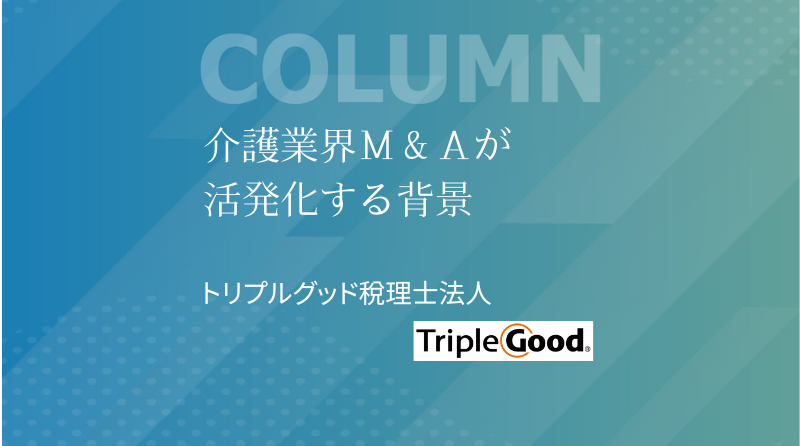介護業界では事業を売却する売り手側と、事業を買収したい買い手側、双方のニーズが高まり近年M&Aが活発になってきています。実際のM&Aで気になる流れ、ポイントについて解説していきます。
M&A市場は右肩上がりで成長
日本のM&A市場は、リーマンショックや東日本大震災などによる一時的な不況期を除けば一貫して増え続けている状況にあるようです。
売り手、買い手の目的はそれぞれ多岐にわたりますが、主だったものをご紹介しましょう。
介護事業売却の主な理由
【激化する競合他社との競争】
介護保険制度が開始した2000年から20年以上が経過した現在、介護業界にはさまざまな変化が起こっており、競合事業者との競争が激化しています。経営環境の変化や傾向、特徴としては以下のような要素があります。
・少子高齢化による市場拡大に魅力を感じた他業種の新規参入が増加
・労働者人口の減少に加え、他業界との労働条件や労働環境の相違による深刻な人手不足
・経営の効率化を図るためIT化への対応が迫られていること
・経営の安定化、効率化のため国から大規模化を求められていること
・規制産業であり、3年毎の報酬改定への対応が必要であること
こうした事情によって、介護事業者にとって経営の継続性確保が困難になりつつあり、M&Aを選択する主な要因になっているようです。
【経営者の高齢化による後継者不足】
東京商工リサーチの調査によると、21年の社長の平均年齢は62.77歳と過去最高でした。毎年平均年齢は上昇をたどり、社長の高齢化が進んでいます。
ここ数年は70代や80代の社長の割合も徐々に高くなっています。
介護業界でも後継者問題が顕在化するなかで、親族による承継、役員や従業員による承継とも、うまくいっていないケースが非常に多いようです。
M&Aで買い手企業に承継すれば、利用者や従業員に迷惑をかけずに経営は継続し、社長は引退することができます。
また、会社を閉じてしまうと、社長がこれまで築き上げたものを終わらせてしまうことになり、費用もかかります。
しかし、M&Aで売却をすれば事業の継続だけでなく、売却収入も入り、引退後の生活資金の確保も可能となります。
介護事業買収の主な理由
【経営資源(人、モノ、ノウハウ)の獲得】
買い手企業にとっては、M&Aによって買収する企業の人材、モノ、ノウハウを一挙に得ることができます。
経営環境が複雑化する昨今、経営資源を築くことは容易ではありません。
売り手から受けた事業所などの有形資産と、従業員の持つ効率的な業務の進め方などのノウハウのような無形資産を得ることでビジネスの成長が期待できます。
経営資源の獲得は、既存事業においては経営基盤のさらなる強化、新規事業においては、新領域の開拓の経営基盤の構築が実現でき、いずれの場面でも大きなメリットがあります。
【人材確保】
日本の人口は減少傾向にあり、総務省によると、2060年時点で8,674万人(2010年比4,132万人減(32.3%減))という試算があります。
少子高齢化の影響で若い働き手が減少傾向にあり、企業同士で取り合っている状況なので、中小企業は満足に人材確保ができていません。
そこで、M&Aで事業規模を拡大してスケールメリットを活かし、人材の採用、育成、定着を実現するため、つまり、人材戦略として活用する目的で、M&Aを選択するケースがあるようです。
【買い手候補数3万以上のネットワークを保有するカイポケM&Aはこちら】
売り手側のメリット・デメリット
【メリット】・事業の成長
売上アップやコストダウンなど、買い手企業とのシナジー効果が期待でき、事業の成長・発展につながります。
自社よりも規模が大きく、堅実な経営を実践できている企業の傘下に入り、買い手企業の経営資源を活用できれば、激化する市場で勝ち残る競争力がつきます。
・事業承継問題の解決先述した通り、中小企業の多くは、後継者問題に悩まされています。親族承継やMBO(役員や従業員による承継)が難しい中、M&Aを活用することでスムーズな事業承継が可能となります。
・従業員の雇用の継続M&Aが成約した場合、売り手企業の従業員は買い手企業から、これまでの雇用契約内容を維持したまま雇用されるケースが一般的です。
そのため、これまでの従業員の生活を守れるというメリットがあります。
・オーナーの株式売却による金銭的収入企業の売却によって、オーナーの手元に多くの現金を残すことができます。
M&Aでは会社の有する建物や土地などの資産を時価で評価し、さらに営業権を加味した結果、実際の純資産額よりも高い株価で売却できるケースは決して珍しくありません。
自社の株式を売却し、現金を得ることができるという点は、オーナーが引退後に充実したセカンドライフを送ることができるという意味でも重要です。
・経営の責任からの開放中小企業では、社長やその家族が、金融機関からの融資のために個人資産の担保提供や連帯保証を負っていることが少なくありません。M&Aの成約によって経営権が移動すると、この担保提供や連帯保証が解除されるのが一般的です。
また、従業員の生活、事業継続や事業承継などの責任は重く、社長の経営におけるプレッシャーは相当なものです。
M&Aが成約すれば、そういった経営者の責任から解放されます。
【デメリット(リスク)】・買い手がみつからない
M&Aは売り手、買い手の双方の合意により成立するものです。売り手企業が買い手企業を見つけるのは決して簡単なことではありません。
仲介会社に依頼したとしても、スムーズに買い手企業が見つからないケースは少なくありません。
・思っていた金額で売却できないM&Aにおいて、企業価値の算定方法はいく通りもあり、最終的には売り手買い手双方の合意により売却額が決定します。
現在の企業状況だけでなく、将来の収益なども考慮のうえ企業価値の算定が行われまるため、必ずしも売り手の希望価額だけで決められるものではありません。
・従業員や顧客の理解を得られないM&Aの事実を報告する際、従業員や利用者から不安や不満がでることがあります。
場合によっては、従業員が退職したり、利用者が事業所を変更したりすることもあります。
情報開示のタイミングや説明方法などには留意が必要です。
買い手側のメリット・デメリット
【メリット】
・事業の拡大M&Aを行うと、売り手企業の有する事業所、設備、人材、ノウハウなどの経営資源を獲得することができ、事業を効率的に拡大できます。
経営は、経営環境の変化に対応し、トレンドに合わせた経営資源を投下する必要があります。しかし、自社のみでこれを行い成長を続けるのは容易ではありません。
こういった経営課題の解決にM&Aは有効な手段です。
・事業の多角化自社の経営理念や経営戦略にマッチした企業を買収することで、事業の多角化が可能となります。
買収した企業の経営資源を活用して新規事業に算入することで、収益の安定化やリスク分散が可能となります。
・事業商圏の拡大自社が展開していないエリアの企業を買収することで、商圏拡大が可能となります。
自社で新しく拠点を展開するには、時間、コストが相当かかりますが、新規エリア特有の事業ノウハウを含めて獲得することができます。
・人材の確保未曾有の人手不足により採用コストは増え従業員の定着も難しい中、M&Aで売り手の優秀な人材確保が可能となります。
また、事業規模の拡大に伴いブランド力が向上し、新規の採用や定着にも有効です。
・節税対策M&Aでは、買い手企業側が節税できるというメリットもあります。
売り手企業が赤字を抱えていた場合、選択したスキーム次第では買い手企業が、その赤字を引き継ぐことができます。
赤字は発生した年から10年間は繰越可能で、翌年に繰り越された赤字は、自社の利益と相殺でき、法人税の節税が可能となります。
【デメリット(リスク)】
・期待したシナジー効果がでないM&Aで買収企業を選定する際、買収後にどれだけの収益やシナジー効果が見込めるかで買収価額を検討するのが一般的です。
ところが、期待していたほどの収益やシナジー効果が上がらず、離職者が増えたり、利用者が減ったり、管理コストが増えたりと、マイナスの影響が出てしまうこともあります。
・許認可を引き継げず事業継続ができない介護事業では、許認可を引き継げるかどうかは非常に重要です。
M&Aの成立後に対象企業の重大な法令違反が発見されるなど、売り手企業の粉飾を見落とすと、事業継続に影響がありますので、事前確認をしっかり行う必要があります。
・簿外債務などを引き継ぐ可能性M&A成立後に、貸借対照表には記載されていない、未払の給与や退職金などの簿外債務を引き継いでしまうことがあります。
また、利用者や業者など企業外部とのトラブルのように自社に不利益をもたらす債務を引き継いでしまうこともあります。
こういったことにならないよう、事前調査(デューデリジェンス)や、契約内容を整備しておくことが重要です。
・従業員のモチベーション維持M&A成約後は、売り手側の従業員は、買い手側に引き継がれ、雇用が維持されることが一般的です。
しかし、給与や勤務時間などの労働条件や労働環境の希望を叶えられないこともあります。
また、人事評価制度や福利厚生などが一変することで、従業員のモチベーションが下がるだけでなく、買い手企業の従業員とのトラブル、退職などに発展する恐れもあります。
そういった事態に陥らないためにも、M&A成約後の早い段階で、売り手側企業の現場のキーパーソンと信頼関係を築くことも重要です。
利用者へのサービス提供を続けていくための戦略が重要に
介護業界のM&Aが近年活発になってきている背景には、売り手側・買い手側双方のニーズの高まりがあります。さらに国からも規模化・協業化が推奨され、サービスの質の向上も求められています。大手の傘下に入りながらも地域密着で事業運営を続けていくことも選択肢になりつつある今、どのような戦略で利用者へのサービス提供を続けていくのかが今後重要になってきます。
カイポケが提供しているカイポケM&AサービスではM&Aに関するあらゆるご質問を受け付けております。 今後のM&Aも含めた戦略について気になる点がございましたら、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
*カイポケM&Aサービスはこちら