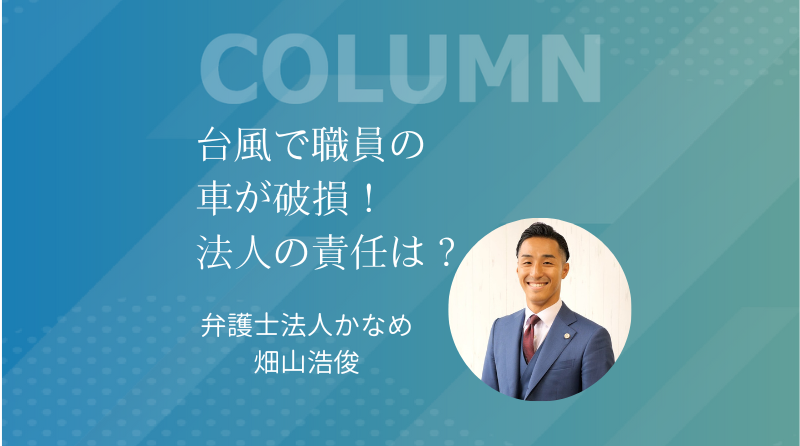2024年度からBCPの策定がすべての介護事業者で完全義務化されました。
特に台風が頻繁に発生するこの季節、自然災害BCPを実際に発動された介護施設も多いのではないでしょうか。もっとも、災害が発生したときは、BCP策定段階には想定していなかった事態が発生することもあります。
今回は、実際に特別養護老人ホームで発生した事例を解説します。同じような事態が発生した場合に備え、どのように対応するかシミュレーションしておくことが重要です。ぜひ、皆様の介護施設・事業所でも対応の在り方をご検討ください。
(※弁護士法人かなめ - 公式YouTubeチャンネルでも解説しています)
1.特別養護老人ホームに出勤していた職員の自家用車が台風で破損:ケース紹介
<相談内容>
私は特養の施設長です。
先日、非常に強い勢力の台風が上陸し、我々の施設にも大きな被害が出ました。
サービス提供は継続する必要があったため、台風接近の中でも、最小限の職員には出勤してもらいました。
我々の地域は車社会ですので、ほぼ全員車で出勤しています。
今回、施設の駐車場に停めていた職員の自家用車が、台風の影響で破損するという事故が発生しました。
どこから飛んでき来たのかわからない飛来物が車に当たり、ガラスが割れたり、ボディが損傷するなどの被害が出ています。
頑張って出勤してくれた職員を思うと不憫ですが、法人がこの物損被害について賠償義務を負うのか、よく分かりません。
このような場合、介護施設では法的に賠償責任を負うものなのでしょうか。
仮に負わない場合、何らかの補填をしてあげる方法はあるのでしょうか。
2.自然災害時における介護事業者の責任範囲:土地工作物責任の成否がポイント
仮に、上記の事例で、自家用車の破損の原因が、老朽化した介護施設の屋根が台風の風で剥がれて飛来したことにある場合、介護施設を運営する法人は、民法第717条1項本文の土地工作物責任を負うことになります。
民法第717条1項本文
➣土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
裁判所は、「台風のため屋根瓦が飛来し損害が生じた場合において、土地工作物に瑕疵がないというのは、一般に予想される程度までの強風に堪えられるものであることを意味」するとしています(福岡高裁昭和55年7月31日判決)。
要するに、たとえ非常に強い勢力の台風のような不可抗力とも思える自然災害であったとしても、そもそも建物の屋根等が、「非常に強い勢力の台風」レベルではなくとも「強風」レベルで剝がれて飛んでしまうような状況であれば、「瑕疵」があると認定され、土地工作物責任が肯定されるのです。
今回の相談事例で、仮に、飛来物が介護施設の屋根の一部であり、この屋根が今にも剥がれそうに老朽化していた場合や、風の強い日に実際に剥がれ落ちたことがあるような場合であれば、土地工作物責任は免れないでしょう。
法人の所有する建物ではなく、近隣住民の住宅の屋根や壁等が飛来した場合であれば、その所有者に対する土地工作物責任の有無を検討することになります。
3.土地工作物責任が無い場合、法人は賠償責任を負わない
上記のような土地工作物責任がない場合であれば、介護施設を運営する法人は、自家用車の損傷に対する賠償責任を負わないことが原則です。
読者の中には、「台風が接近するような危険な状況の中で出勤を命じること自体が許されないのではないか」と思われた方もいるかもしれません。しかし、介護施設である以上、たとえ台風が接近している状況であったとしても施設で暮らす利用者の方々にサービスを提供する必要性があります。
災害の状況にもよりますが、台風が迫る状況下で出勤を命じたことで、介護施設に直ちに責任が発生する訳ではありません。
4.保険は各自が備えるのが原則
台風により車両に被害が生じた場合、所有者が車両保険に加入していれば修理費用が保険金で補填されます。裏を返せば、車両保険に加入していなければ損害は補填されません。
車両保険自体の保険料が高いことを理由に車両保険に加入していない職員もいると思いますが、このあたりは、災害が頻発する昨今の状況を踏まえつつも、個人の判断に委ねられるところです。この点は、職員らに対して注意喚起をすることも検討しても良いかもしれません。
5.災害見舞金による手当の検討を
「台風の接近の中、頑張って出勤した職員に対して、何ら法人側が補償しないのはおかしいのではないか」と思う人もいるかもしれません。とは言え、なんらのルールもなくケースバイケースで補償をしてしまうと、職員間での不平等が発生するなど、法人として統一的な対応ができません。
ここでチェックしたいのは法人の慶弔規程です。
慶弔規程とは、結婚・出産・死亡・災害等の慶弔事象が発生した場合に支給するお祝い金・見舞金、支援する範囲や条件を定めた社内規程のことです。
この慶弔規程の中に「災害見舞金」という項目がないかチェックしてみましょう。
「災害見舞金」は、地震・台風・火災・風水害等の被害に関する見舞金です。
このような規定があるか否かは法人により異なります。
「災害見舞金」という規定自体が存在しない法人もありますし、規定自体があったとしても、被害の範囲を自宅の損傷に限定しているような法人もあります。
もし、慶弔規程の中に「災害見舞金」の定めがない法人や、定めがあっても、被害の範囲を自宅の損傷に限定しているような法人については、昨今の自然災害が頻発する状況を踏まえて、制度の新設を検討してみてはいかがでしょうか。
このような制度があること自体が職員に対する労いや感謝の気持ちを示すことになり、災害時における事業継続にも繋がると思います。